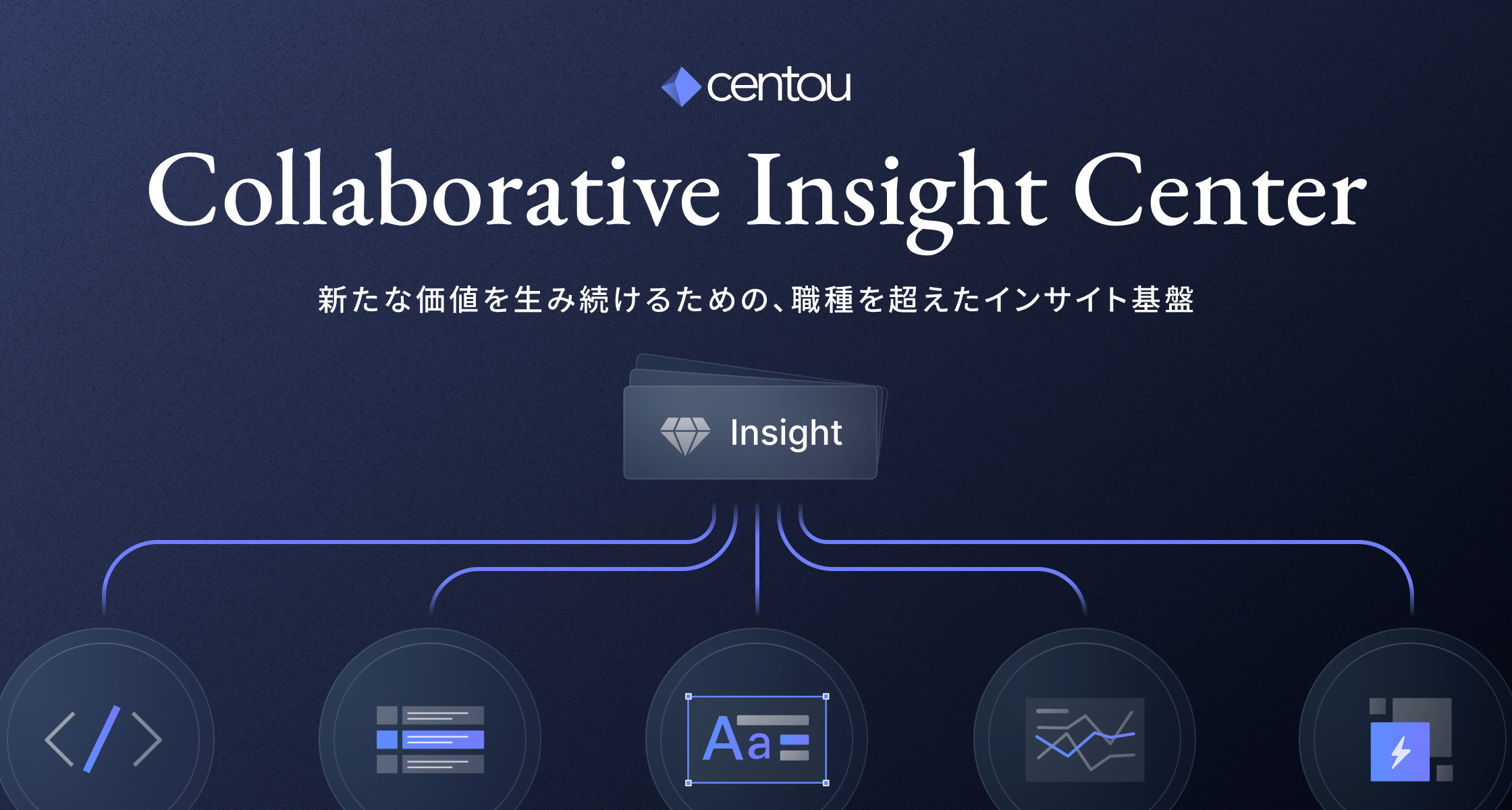スタディストのリサーチ&デザイン室で働くデザイナーのHANYU, Kojiです。
スタディストでは、AIを使った機能開発に大きく投資しています。AIエンジニアリング室という組織を置き、現在4名のAIエンジニアがAIを用いた新機能開発を事業横断で推進しています。
その一つのプロジェクトとして、2025年6月にマニュアル活用をAI技術で後押しする「Teachme AI」に大幅なバージョンアップを行いました。「おまかせ編集アシスタント」機能の誕生により、ユーザビリティも改善し、すでに導入いただいているお客様の2年目の継続が多く起こっています。
このプロジェクトにデザイナーとして参加した私は「AIを組み込んだプロダクトの開発において、デザイナーは何をしたらよいのか?」という問いに向き合いました。
結論としては、デザイナーとして「インサイトを繋ぐ」ということに絞って振る舞った結果、上手くプロジェクトを前に進めることができたので、その裏側をまとめてみようと思います。
プロジェクトの対象となったのは、「Teachme AI」というプロダクトです。
スタディストはAIプロダクト開発に注力していて、マニュアルの作成や動画の切り出しを、生成AIの支援により大幅に省力化する「Teachme AI」を2024年にリリースしています。
「Teachme AI」をリリースした当初は「マニュアル作成のハードルを下げるためのサポート機能」がメインとなっていました。
一方で、お客さまからのご要望として「マニュアルを作成するだけでなく、修正しやすくなるなど、マニュアル運用にも使いたい」という声をいただいていました。
そこで 、「マニュアル作成から運用まで、 Teachme AIの貢献範囲を拡げたい」と考えたAIエンジニアリング室のリーダー近藤が「AIアシスタントとチャットしながらマニュアルを作成する機能」のプロトタイプを開発します。
このような背景から、近藤がつくったプロトタイプを検証しながら、Teachme AIのバージョンアップをしていくプロジェクトが始まりました 。
このプロトタイプを検証しながら、Teachme Aiの大幅なバージョンアップを狙っていくプロジェクト
ここでプロジェクトに参加した私としては「デザイナーは何をしたらよいのか問題」に直面します。
幸いにもこのプロジェクトには、近藤をはじめとする、AI技術自体やそれを用いたプロダクトに精通したエンジニアが何人も関わっていて、彼らはAIに最適なUI設計やフロントエンド設計を自分でも行えるスペシャリストだったためです。
なので、彼らの持つ技術やノウハウを最大限発揮できれば、見た目だけをデザインする人はいなくても、お客様に大きく貢献できるAIプロダクトが生み出せると考えていました。(実際、最初のプロトタイプは近藤が1人でつくっています。)
そこで、デザイナーとしてどこに役割を持てば、チームがベストな動きを取れるのか?今までのプロダクト開発とは違い、デザイナーの価値発揮のポイントを新たに見つける必要があると考えていました。
ここで私はチームに足りない役割は何か考え、それは「インサイトを繋ぐ」ことだと整理しました。
過去のプロジェクトでは、ゴールやコンセプトを定義してインサイトを収集し、それにもとづき具体的なUIや仕様をチームメンバーと共に設計する…といった流れで進めます。
一方で、今回は私の参画時点で具体的なプロトタイプがあり、AI技術やフロントエンドに精通したエンジニアたちの手で日ごとに体験の改良が進んでいました。
この状況においてチームを更に加速させ、お客様により貢献できるようにするためには、お客さまがどのようなことを考え・求めているのか、つまりインサイトを把握することが必須で、ここに責任を持つ役割はチームに不在でした。なので私は、チームとお客さまを「インサイト」で繋ぐことに自分の役割を置くこととします。
インサイトを繋ぐために、私が取り組んだのは大きく分けると2つです。
「AIエンジニアをインサイトでサポートする」「インサイトを満たす顧客コミュニケーション」というポイントに絞って、今回のプロジェクトを進めていきました。
デザイナーは、お客さまにとってよりよいプロダクトの体験を考える、つくり手の視点に立つことが得意な職種です。
事業目線で売上を高めるための活動だけでなく、インサイトをチームで扱いやすく整え、プロダクトやコミュニケーションを行き来して、ベストな体験をつくりあげていくのは、デザイナーこそが適任だと考えています。
一つ目の役割は、AIエンジニアをインサイトでサポートすること。これは前述の通り、AIプロタクトの体験づくりに専門性を持つAIエンジニアたちが、お客さまの現状や課題に直接触れ、自分たちの作っているプロダクトを迅速に改善できるようにしていくことです。
まず、すでにAIエンジニアリング室の近藤が、マニュアル自動作成チャットのプロトタイプを用意していたので、これを活用しながらインサイトを集めることにしました。
すでにTeachme AIを導入いただいているお客さまにお願いして、プロトタイプを見せながらインタビューを行います。インタビューには、リーダーの近藤を筆頭にエンジニアも参加しました。
そこで分かったインサイトを整理して、プロジェクトの共通認識を獲得するためにValue propositionを作成し、チームや社内に展開しました。
同時に、プロトタイプから得られた(でも漠然としている)新たな価値を、リリースに向けて明確化していくため、インサイトをジャーニーや顧客像にまとめておきます。ここでは、スタディストのリサーチ&デザイン室で導入しているインサイトマネジメントツールCentouを活用しました。
その後は、AIエンジニアがプロトタイプを改良し、その時点で最新のものを使って顧客インタビューや社内で簡易な体験会を行い、得られたインサイトをもとにAIエンジニアがプロトタイプをつくり、、という流れを繰り返します。
合計11回のテストを通じ、プロダクトは磨き込まれ、また顧客社内でのマニュアル作成の実状への理解も深まりました。
例えば「画像の割り当て機能」は検証での学びから生まれました。これは、作業のタイトルや説明文に基づき、適切な画像を自動で割り当てる機能です。
インタビューを通じ、AIがたたき台をつくっても、各ステップに画像を割り当てるのが大変という声があがりました。
たたき台の作成は既存のTeachme AIの機能でも実現できていたので、それらを手直しする・仕上げる際の負担をなくすことがお客さまが求めていることだと捉えて、本機能を追加しました。
画像割り当てはチャレンジングな機能開発でしたが、お客さまへのインタビューからチームが直接得た上記のインサイトに基づき意思決定が行われました。 この機能がスコープに含まれたことで、マニュアルを「仕上げる」「品質を高める」ための編集アシスタント、という輪郭が明確になりました。
プロダクトの要件がまとまってきたタイミングで、ようやくデザインデータを整備します。とはいえ、すでにここまでの工程で、ほぼインターフェースは固まっているので、ここで私が行うのはリリースのために少し調整をかける程度です。
具体的には、ここでは「学習コストを下げる」ことを意識しました。
新しい体験であるため、お客さまが違和感なく使えるように、インタフェース自体は見慣れたものが好ましいと考えました。なので、Teachme Bizの既存UIを踏襲しつつ、類似のチャットAI系に近しい使い勝手となるように設計しています。
また、UIのライティングも同様で、前述した「画像の割り当て機能」はそのまま「画像割り当て」タブとして表現しています。変に何か例えるよりも、「これはなにをする機能か」をすぐイメージできる方がお客さまの学習が早くなると考えています。
ちなみに、私はフロントエンドの実装も行えるので、デザインデータを整えた後は、あらかた動くようになったフロントエンドのコードを直接手直しし、UIの微調整を行いました。
この方法を採用したことで、UIの磨き込みにかかる伝言ゲームは不要となりエンジニアに余裕が生まれます。それにより、エンジニアはパフォーマンス改善などにより多くの時間を割けるようになりました。
正式リリースの前に、改めてお客さまから「これなら『ウチのマニュアル』を作れる!」と思っていただけるのかをテストするために、現地調査を行いました。
プロジェクト開始当初行ったインタビューでは「AIは一般常識しか知らないから『ウチのマニュアル』を作るにはイマイチ役に立たない」といった指摘がありました。リーダーの近藤を筆頭に、チームでは「実際にお客様の手で『ウチのマニュアル』を作ってもらわないと最終的にプロダクトの良し悪しは判断できない」と考えていました。
なので、実際にマニュアルを作る方から「良い」と言っていただけるかどうかをリリース前に確かめておくために、チーム全員で現地調査をすることになりました。
AIエンジニアにはとにかくプロダクト開発に集中してもらいたかったので、私がお客様とやり取りをして、現地調査の段取りを調整しました。リサーチ項目やインタビューのちょっとしたノウハウなどもドキュメントにまとめ、これをチームに共有し、視察に向かってもらいました。
私はあいにく体調を崩し参加できなかったのですが、プロトタイプの頃からお客さまに向き合い続けてきたチームは、私不在でも何の問題もなく調査を終えて帰ってきました。
調査を通じてチームが直接得たインサイトをもとに課題の整理・重み付けを行いました。その後は着々と改善を行い、2025年6月24日、無事に機能リリースを行いました。
インサイトを扱う立場として、もう一つ役割としていたのは、顧客コミュニケーションの設計です。
AIエンジニアがどれだけ良い体験をつくっても、価値がきちんと伝わって使われなければお客さまに貢献はできません。特にAIを使った機能は、お客さまも「使うことでどのように自分の業務が変わるか」イメージが湧かないことが多いと思います。
なんでも自由にできてしまうサービスだからこそ、「最大限プロダクトが力を発揮できたイメージ」を持ってもらえている状態で、プロダクトを触り始めてもらうことが非常に重要です。
そこで、私はお客さまがどのような部分に価値を感じているのかをインサイトとして収集し、それをプロダクトを使う前のコミュニケーションに反映していくことに取り組みました。
お客さまに何度もプロトタイプを用いてテストを行っていた時に、プロダクト開発のためのインサイトだけでなく、実はプロダクトの見せ方のインサイトも回収していくようにしていました。
例えば、テストの際には、必ずプロトタイプを見せる前に、プロダクトのコンセプトや機能の説明を行うスライドを見せるようにしています。これは、AIを用いたプロダクトはできることが多様で、お客さまが自由に使える度合いが大きいので、こちらから「このように使うと、どのように業務が変わります」という期待値設定をしておくことが大事だと考えているためです。
なので、機能の説明だけでなく、「前提とする現状や課題は何か」「プロダクトを使うと現状の○○はどう変わるか」をあらかじめお伝えし、その反応を見ながら、伝え方の検証も進めました。
例えば、当初は機能の名前は「マニュアル作成アシスタント」としていました。しかし、お客さまからすると「作成よりも、手直しや修正が楽になる」ことが価値になることが分かってきたので、8回目のプロトタイプテスト以降は「マニュアル編集アシスタント」と名前を変えています。
他にも、サービスのコンセプトを事前に説明しやすくなるように、プロトタイプを触っているイメージを動画にしたり、課題やソリューションの説明の文言も毎回調整し続けました。
AIエンジニアが素晴らしい体験をつくってくれていたので、私は「最高に盛り上がった状態でプロダクトを触り始めてもらう」ことを目指して、リリース前にプロダクト外の体験をできる限り整えていきました。
プロトタイプを用いたコンセプトのテストを繰り返していったので、どのような言葉を使うとお客さまにプロダクトの価値が伝わりやすいのか、かなり解像度が高まっていました。
なので、リリース前にサポートドキュメントをまとめるところも私が行いました。ここでもプロトタイプの説明の時と同じように操作面というよりも、「このプロダクトを使うことで、どのように業務が変わるか」について重点的に説明するようにしています。
また、AIを使った機能は操作自体のシンプルさに対し、指示を工夫することで様々な振る舞いができるため、言葉だけでは「どのように業務が変わるか」を十分に伝えられないと考えました。
そのため、今回は利用イメージ動画を作成し、操作方法に加えて活用する場面や指示の具体的な例を示すこととしました。
動画をつくったことで、リリース後にCSや営業のメンバーから「お客さまに対して新機能の説明がかなり行いやすくなった」という声を多数もらっています。
他にも、BtoBのプロダクトでは、お客さま自身が同僚に機能の説明をする場面が起こりえます。動画の作成は負荷が小さくありませんが、AIプロダクトのように単に使い方を教えればOK…ではない場面においては有効な選択肢です。
少しプロダクト開発とは逸れますが、プロトタイピングのテストが落ち着いた頃に、エンジニアと協力して特許申請の手続きも行いました。特許申請においては、知財部門のスタッフや弁理士に機能やロジックを説明する必要があるため、この場面においては、インタビューや検証を通じて得た学びや、改良された説明資料が役に立ちました。
このようなプロセスを経て、インサイト駆動で進めたTeachme AIの大幅アップデートが完了しました。
当初からマイルストーンとして、初回バージョンで契約いただいていたお客さまの契約継続が起こることを目指していましたが、結果としてたくさんのお客さまに2年目の契約をしていただき、目標を達成できました。
また、今回のプロジェクトで、さらにいくつも機能開発のアイデアに繋がるインサイトを集められたので、リリース後も継続してTeachme AIの新機能開発を進めています。
AIプロダクトは、これまでにない新しい体験をつくります。一方で、自由度が高く新しい体験だからこそ、プロダクトの体験や、顧客コミュニケーションを丁寧に検証していくことが必要だと思います。
スタディストの場合、AIプロダクトの体験にこだわるスペシャリストとしてAIエンジニアがすでに揃っていました。彼らにAIの本領を引き出してもらうためにも、私はお客さまとプロダクトの間に立ち、インサイトをフィードバックすることにこだわりました。
また、AIの本領を引き出すためには、プロダクトへの適切な期待を持ってもらうことが重要です。「このように業務が変わる」という期待をとことん高められるように、インサイトをもとに顧客コミュニケーションを設計することにもこだわっています。
これらは、顧客目線で最適な体験をつくることにこだわるデザイナーだからこそ得意としている役割ではないでしょうか。
自分自身、まだまだ模索している中ですが、AIという新しい技術を用いてプロダクト開発に注力しているスタディストにおいて、これからも有効なデザイナーの振る舞い方を一つ示せたのではないかと思います。インサイトを活用したプロダクトづくりを、引き続き推進していきます。