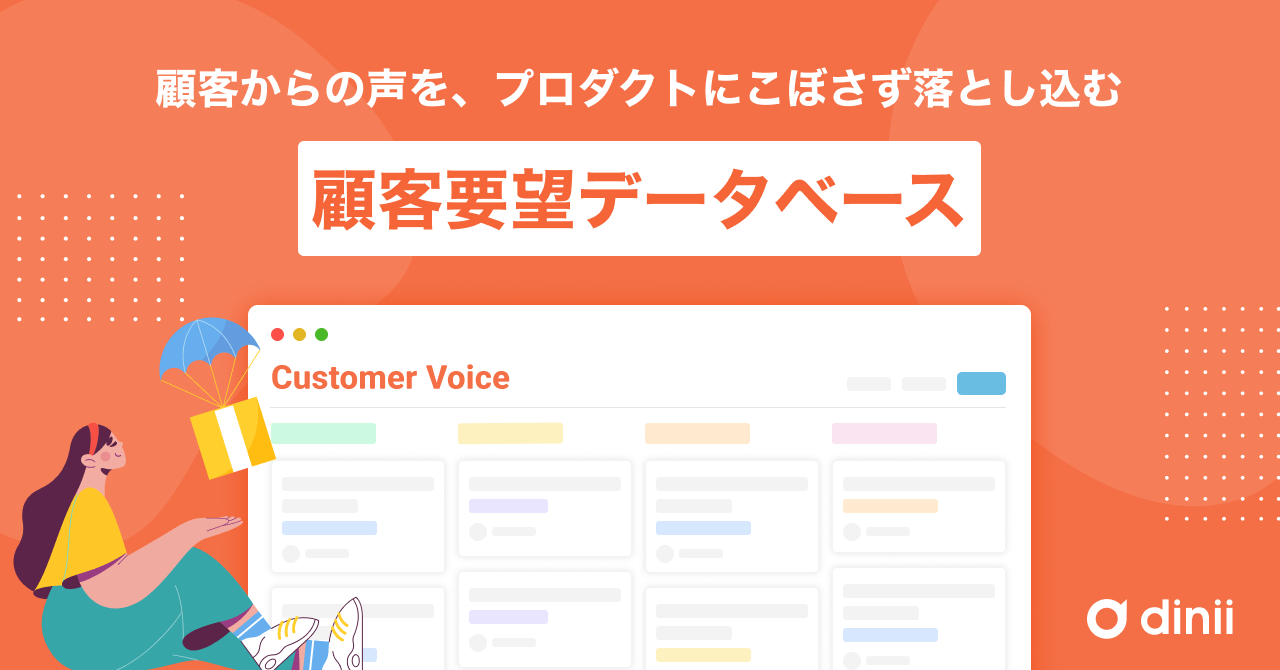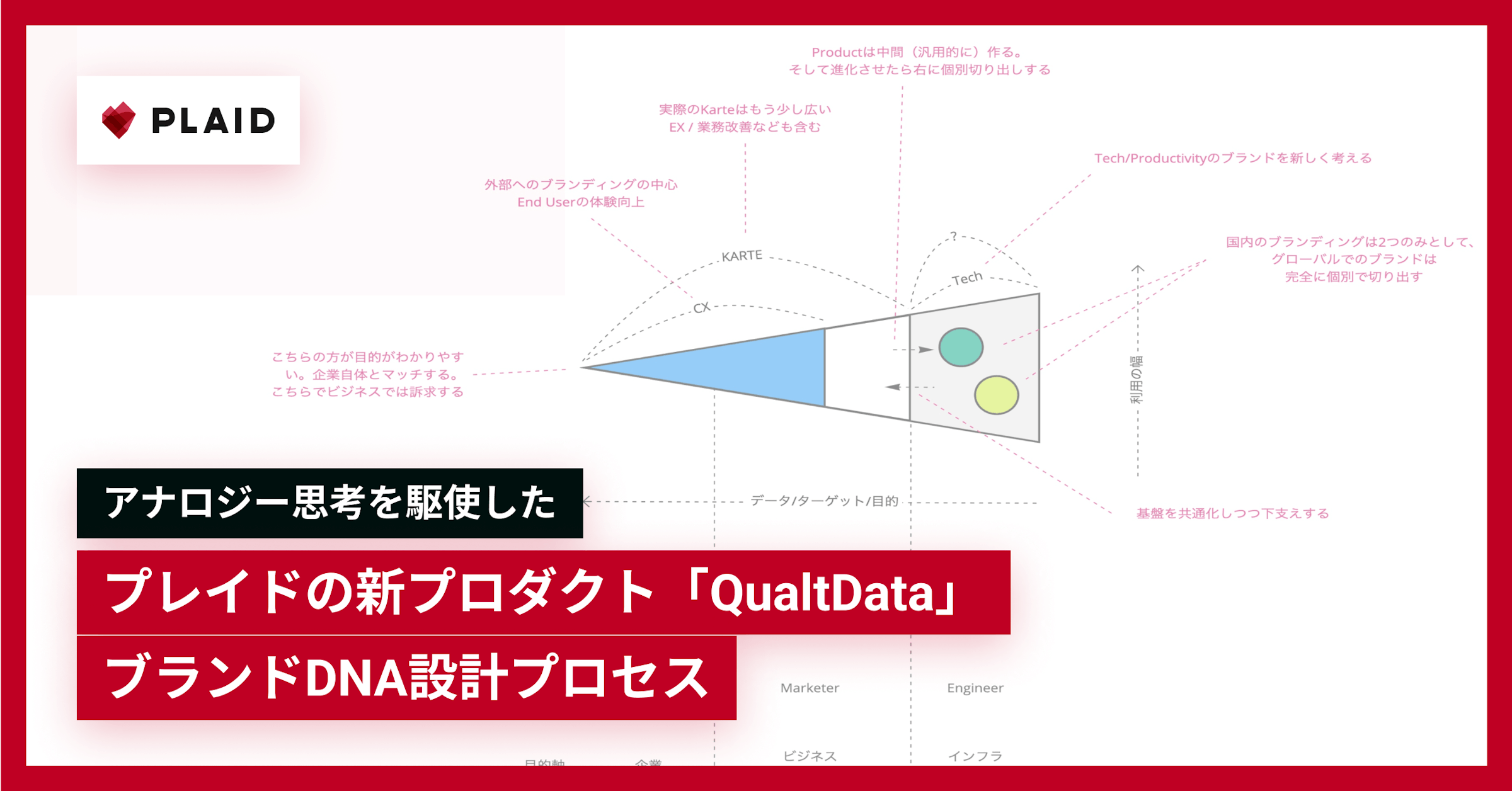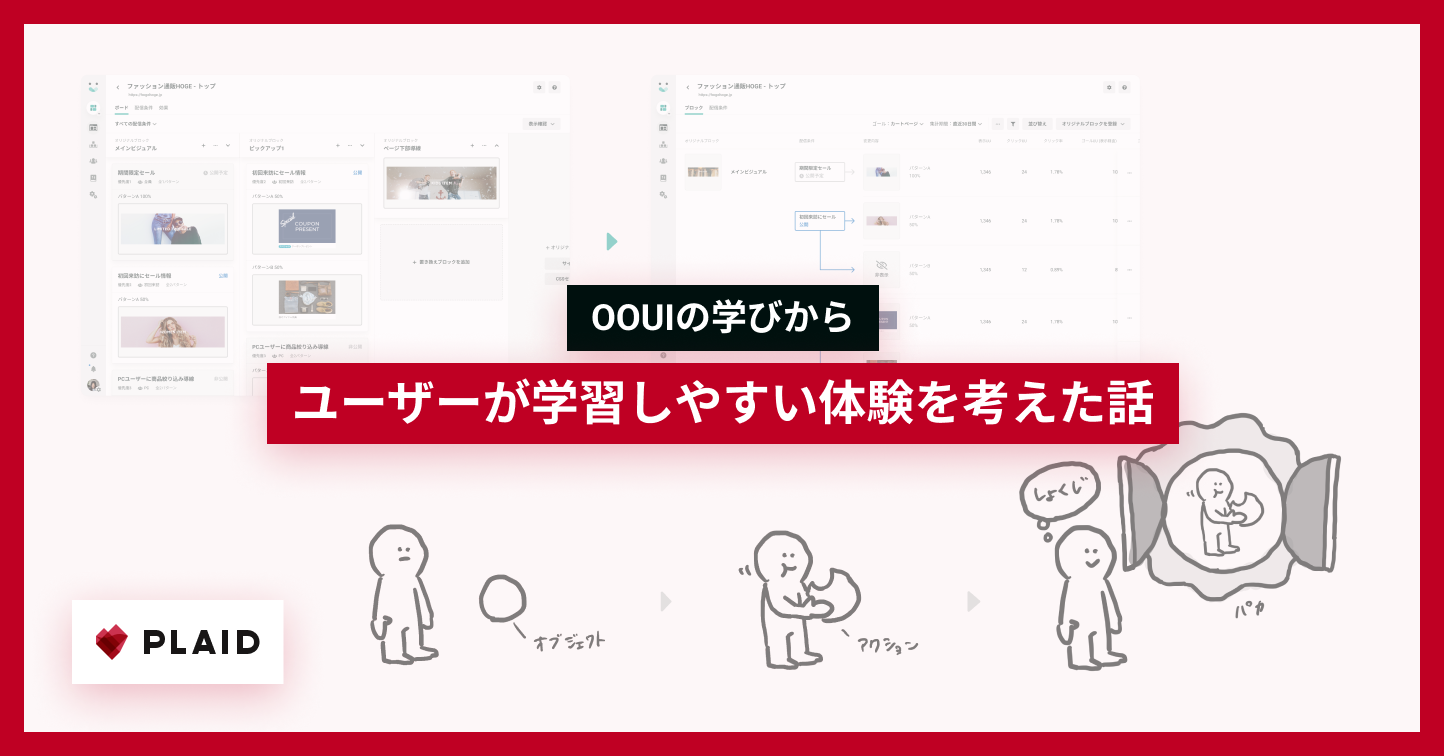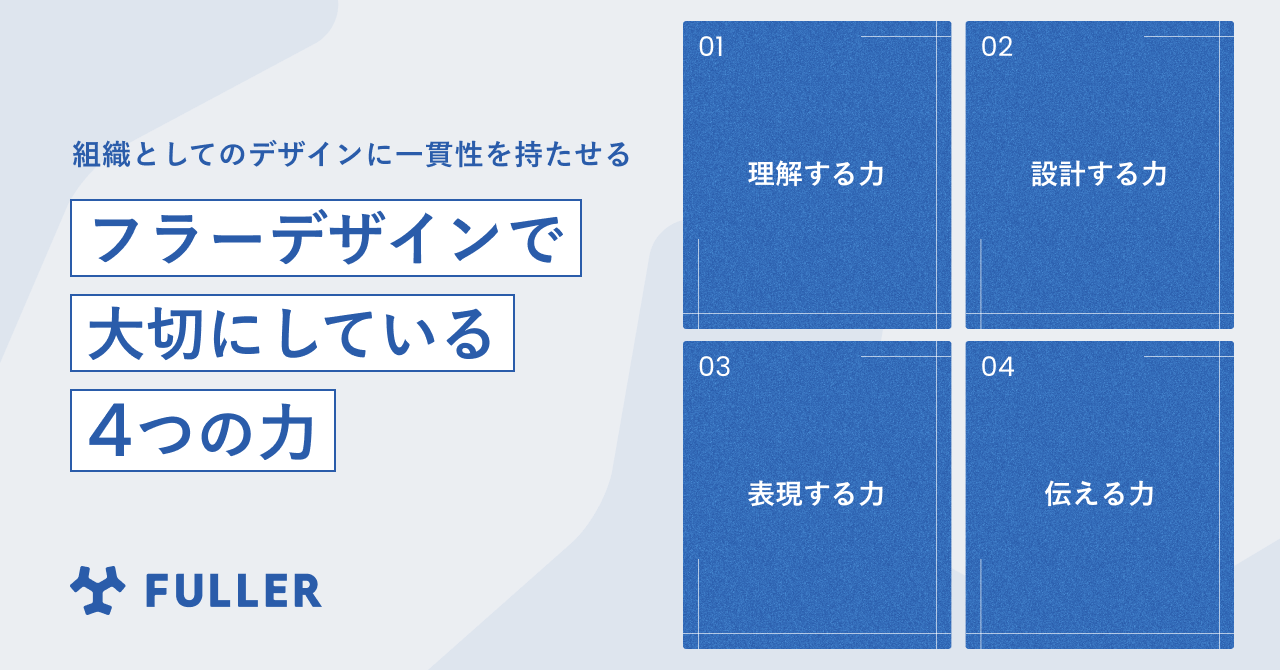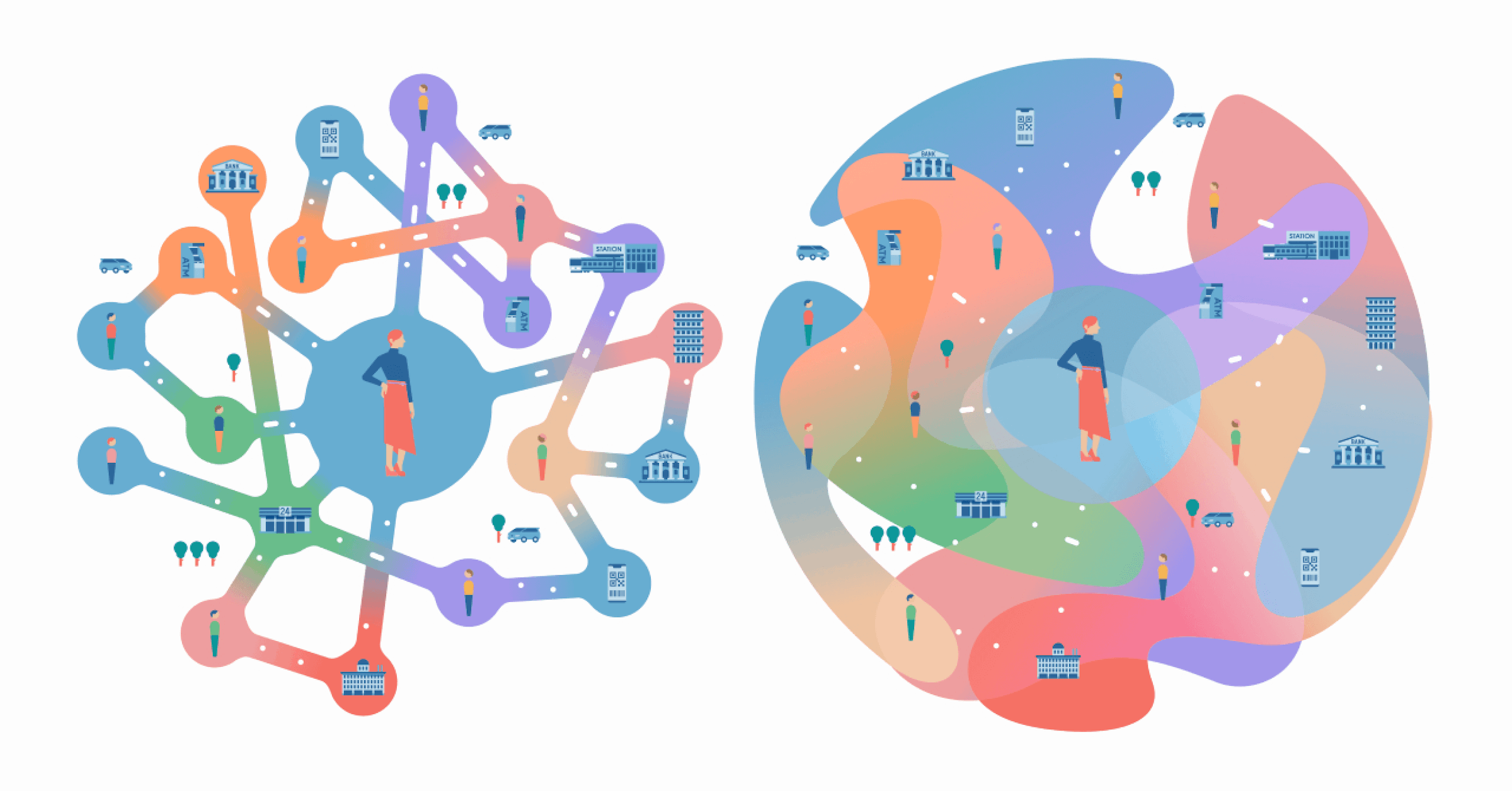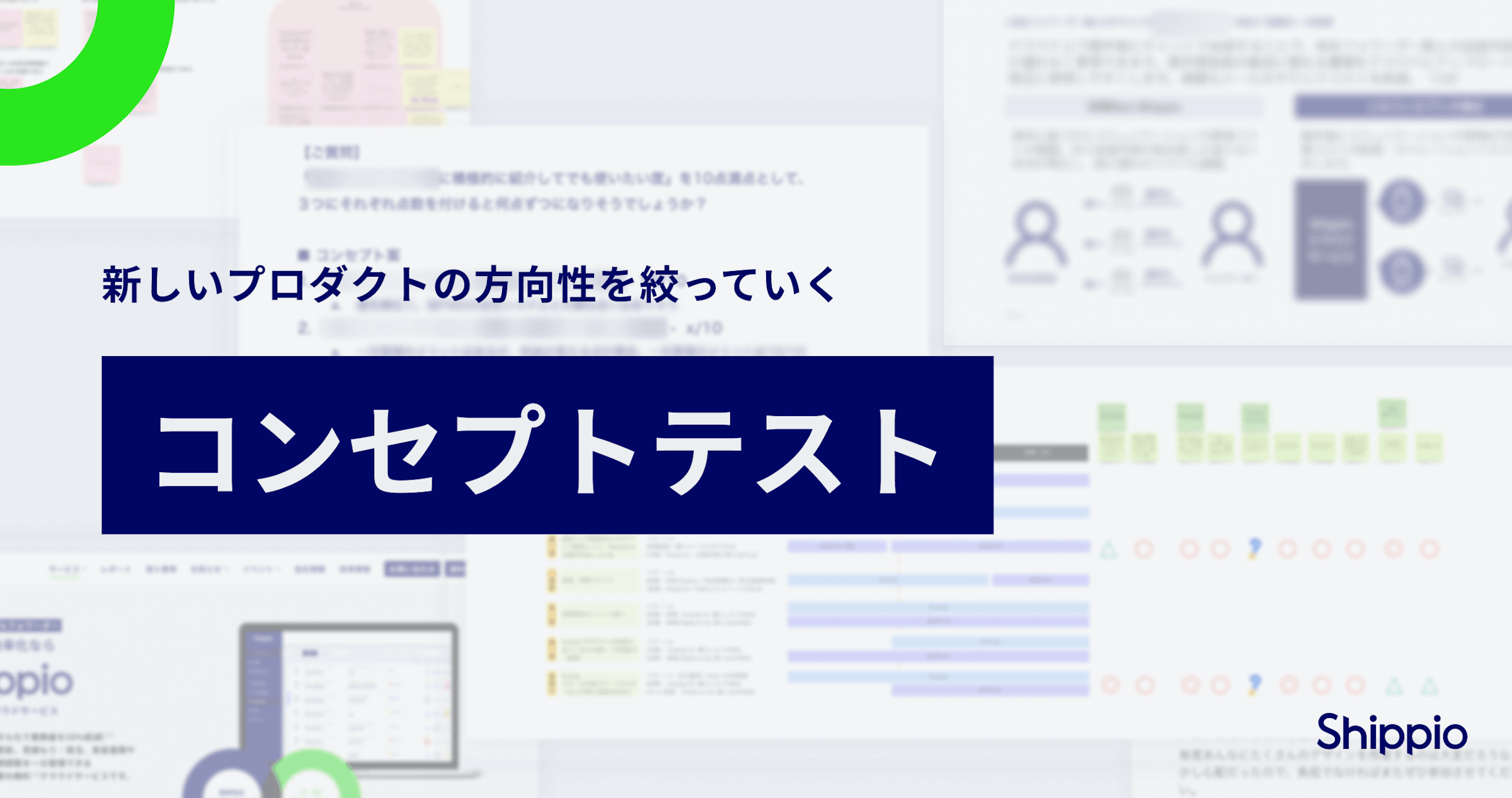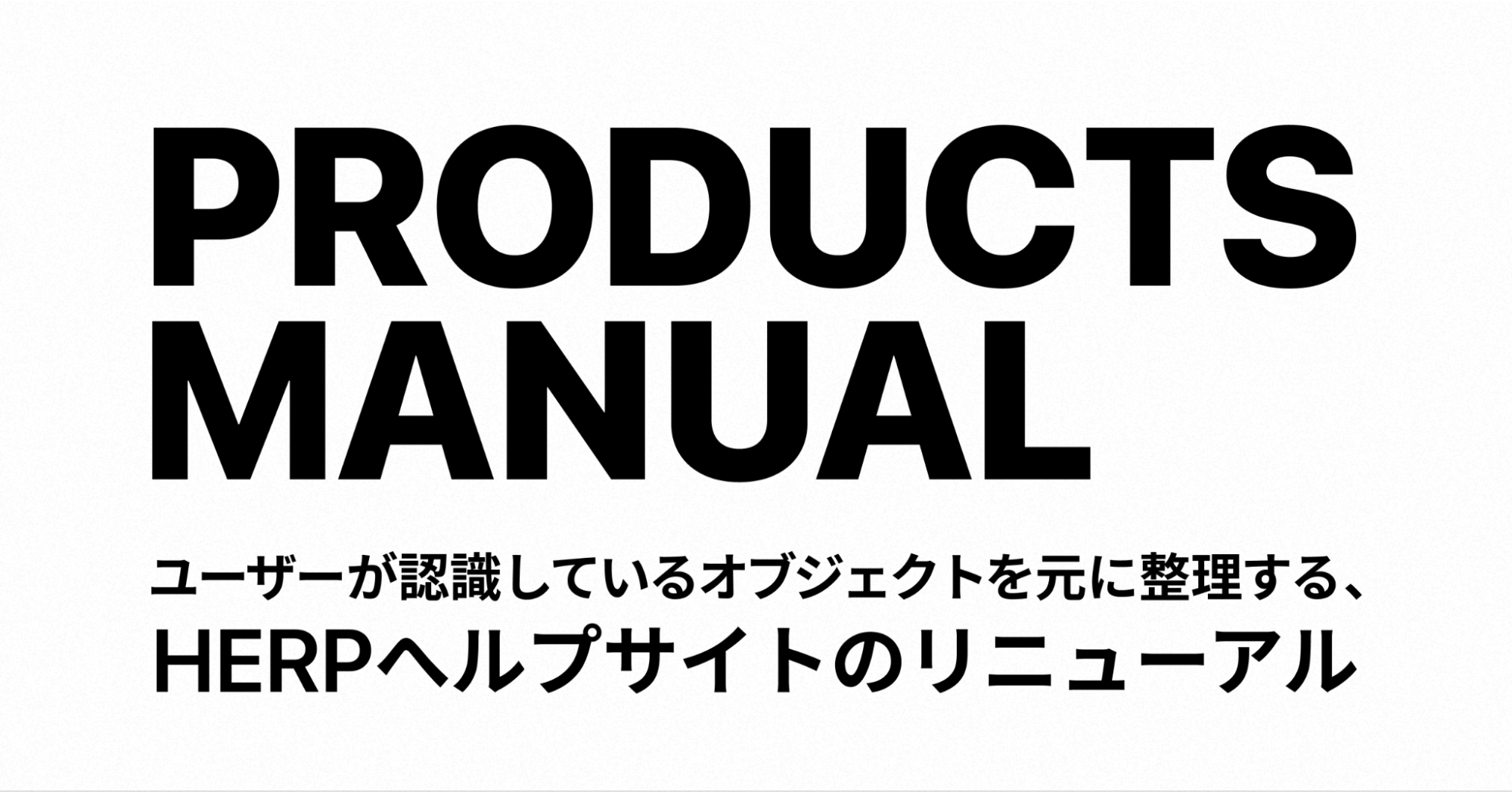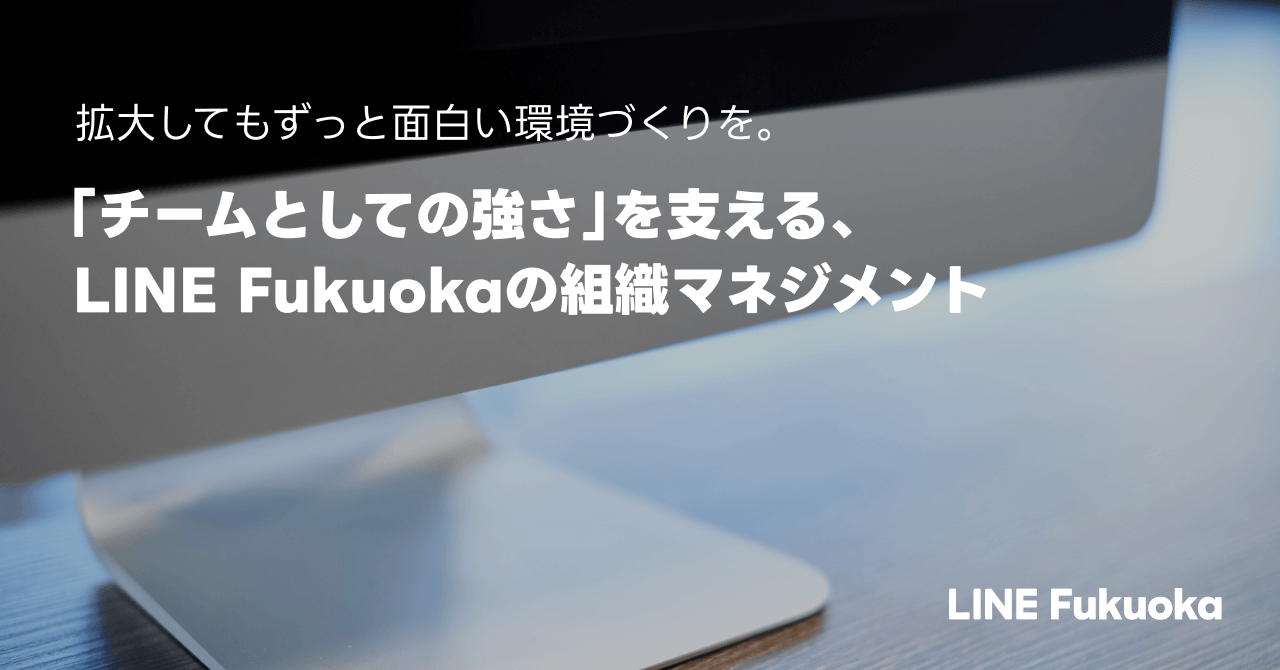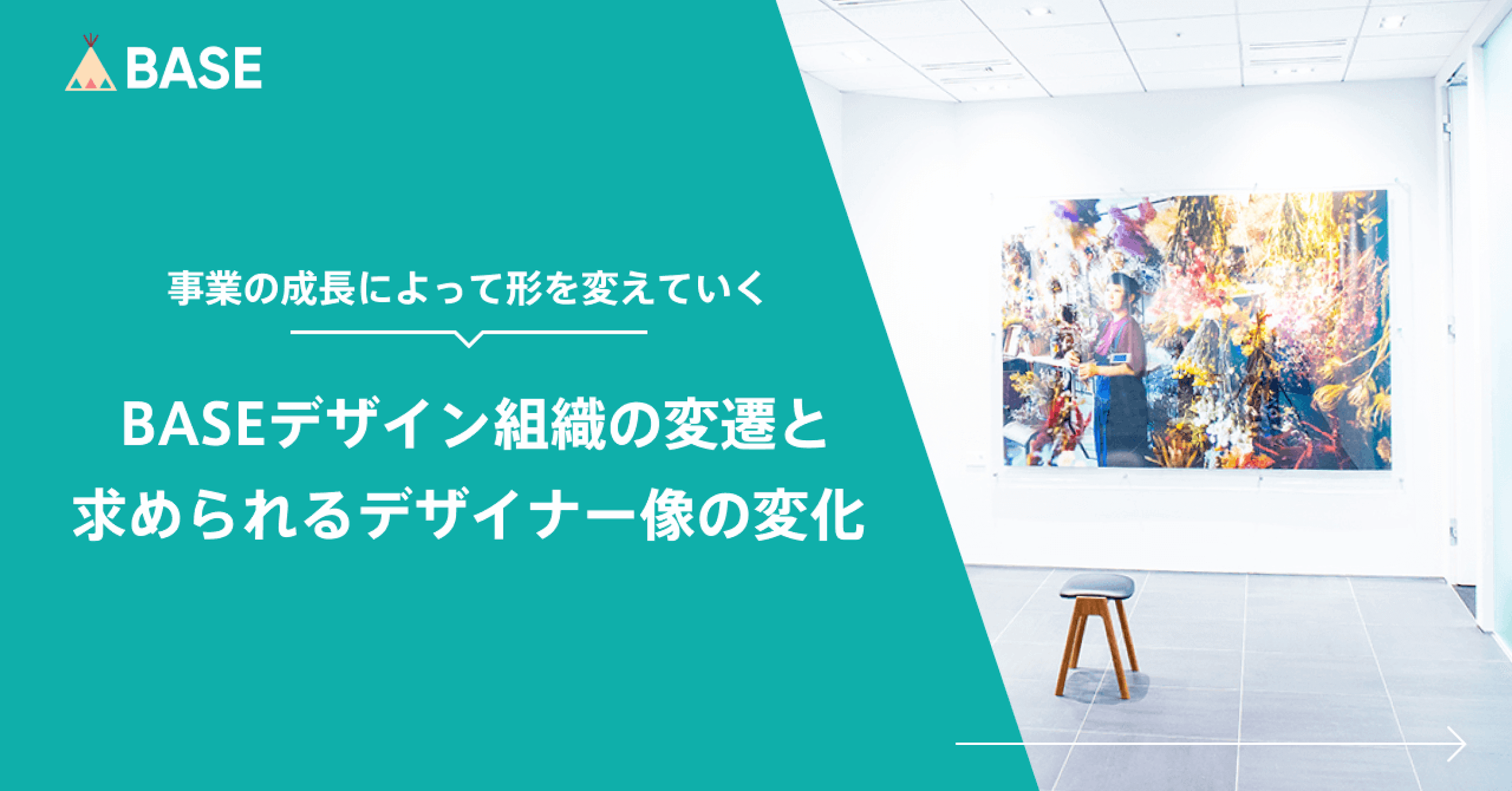SmartHRコミュニケーションデザイン
すべてのタッチポイントにデザインを。SmartHRのコミュニケーションデザイン職メンバーがお送りするデザインの裏側。 ブランドづくりからデザインシステム、あらゆるアイテムのすみずみまで広がる活動を、マイペースでお届けしていきます。
+ 他14名

不確実性の中で事業成果へつなげるディレクション。カンファレンス施策『SmartHR COMPASS』の舞台裏
2025年10月15日、SmartHR主催のビジネスカンファレンス『SmartHR COMPASS』を開催しました。「組織と人材の未来を担う、リーダーの羅針盤」というコンセプトを新たに掲げ、社内でも企画から制作まで数多くのメンバーが携わり、実現に至ったこのカンファレンス。私はディレクターとして、事業目的と社内外の制作を滑らかにつなぎながら、いかにカンファレンス自体の成功確率を高めていくかという視点で活動していました。私自身、カンファレンス施策のディレクターを務めるのは今回が初めてで、手探りなことも多くありましたが、少しでも参考になる方がいればと思い、試行錯誤の過程を残しておきたいと思います。

uchiko(Keiko Uchiyama)

事業成果と専門性をつなぐために。SmartHR コミュニケーションデザイン組織の体制変更
2024年初旬に、旧コミュニケーションデザイングループ(以下コムデ)から、コムデとマーケティング組織が合流した「ブランディング統括本部」へと組織変更を行いました。SmartHRにコムデ組織が誕生してから5年。「SmartHRのすべてのタッチポイントにコミュニケーションデザインを。」というスローガンをもとに活動してきた中で、なぜこの意思決定をしたのか。その狙いや今後の展望について、改めてまとめてみたいと思います。