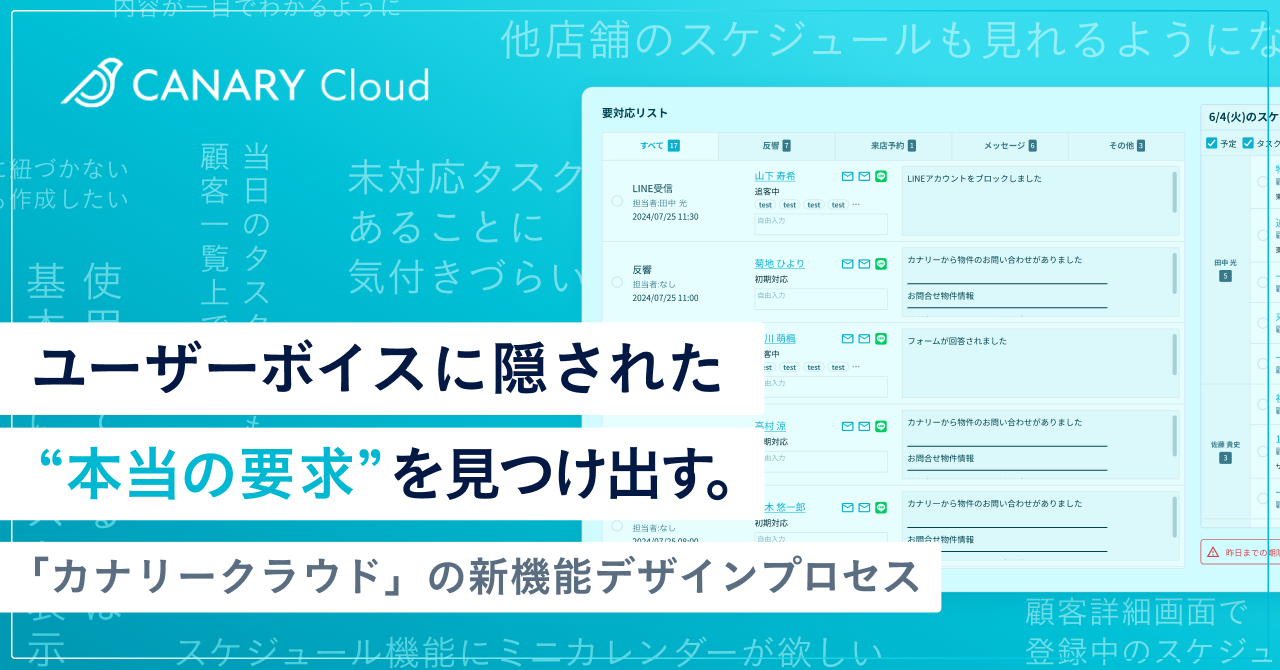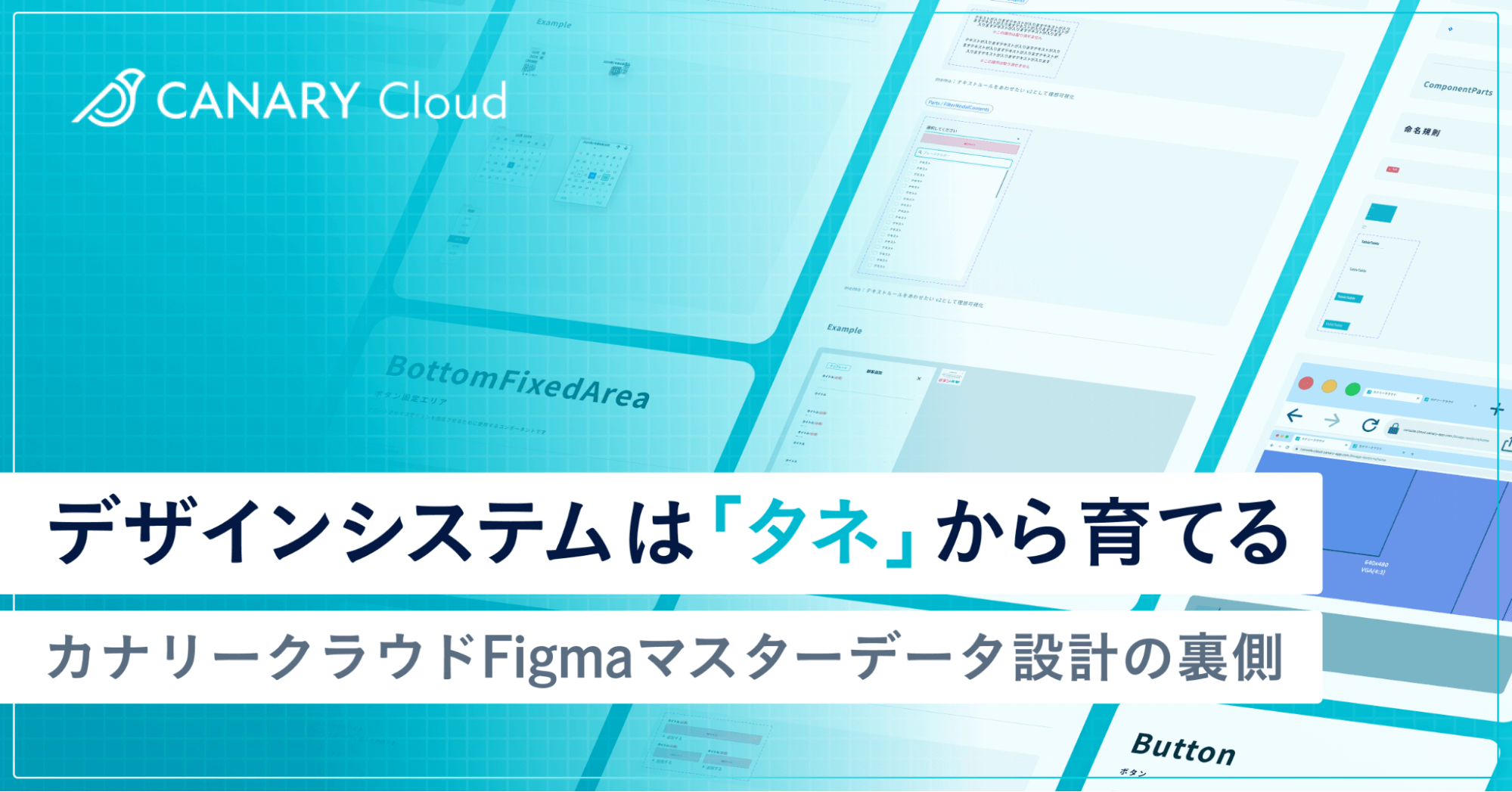カナリーで、約2年間デザインマネージャーを務めてきた小澤です。
私は、2023年6月に会社で初めてのデザインマネージャーとして入社し、デザイン組織の立ち上げを開始しました。
本事例の公開と時を同じくして、2025年3月に、小澤から後任の寺本へとデザイン組織のマネジメントの役割が引き継がれ、さらに拡大に向けて進んでいます。
私が入社するまでのカナリーは、デザインの重要性は会社全体で認識されていても、活用はほとんど進んでいない状態でした。
一方で現在のカナリーは、事業判断にユーザーの声が活用されるようになったり、コアな機能の検証をデザイナー発で推進したり、開発組織全体で活用するデザインシステムの構築が始まっていたりと、多くの場面でデザインが活用されるようになりつつあります。
これまでの約2年間で、カナリーのデザイン活用レベルを高めるために、たくさんの試行錯誤をしてきました。もちろん、失敗も多くあります。最初のデザインマネージャーとして行ってきた地道な取り組みの連続を、できるだけリアルにシェアしていきたいと思います。
前述の通り、デザイン組織が立ち上がる以前のカナリーでは、社内でデザインに対しての重要性は認識されていたものの、実態として活用が進んではいませんでした。
これは、当時はカナリーの中にデザインを軸に物事を進めていけるような人がいなかったため、社内で具体的なデザインの活用イメージがわいていなかったことが原因だったのではないかと思っています。
そんな中、私は業務委託のプロダクトデザイナーとしてカナリーに関わりはじめました。
関わり始めてから1ヶ月ほどで、「会社全体におけるデザイン機能を、小澤さんに集約したい」というオファーがありました。当初はフルコミットではなくプロジェクトごとにアウトプットを出したりアドバイザー的な関わり方にとどまっておりましたが、現場のメンバーから役員まで会社全体がデザイン機能を強めたいという思いが伝わってきたことで少しづつコミットを増やしていくことになりました。
そうして関わりが深くなっていく中、自分が前職を退職するタイミングで改めて熱意のこもったオファーをいただき、自分の状況としても今まで以上に大きな裁量と責任の中で、デザイン活用を推し進めることで事業を成長させられる環境に魅力を感じました。そこからデザイン組織を立ち上げ、拡大していくことをミッションとして、2023年6月にカナリー初のデザインマネージャーとして入社します。
実は、カナリーのデザイン組織立ち上げは、多くの失敗からスタートしています。
デザインマネージャーとして入社してすぐに、開発メンバーから営業メンバーまで、多くの社員と1on1をすることで事業と組織についての現状や課題について収集していくことから始めました。
結果、事業の方向性や、採用に関する悩みなど、幅広い問題意識をヒアリングすることができました。
これらを受けて様々な課題感が、多くのメンバーからヒアリングできました。その中でも採用・サービスの両側面においてブランド強度を引き上げていく必要性を感じているメンバーが多いように感じました。
そこからまずはインナーで事業の目指す未来や思想を強固に共通言語化していくための動きを始めたのですが、蓋を開けてみると、少しずつ物事は決まっていくものの、思っていた速度で推進することはできていませんでした。
今思い返すと当然のことですが、入社間もないタイミングでドメイン知識もまだまだ乏しい状況で、最上流から意思決定にコミットするような動き方をしたことで、多くのミスコミュニケーションが生まれてしまいました。その結果、意思決定からアクションにつながるスピード感が遅くなってしまったのです。
社内でのコミュニケーションを深め、ドメインの理解が進むにつれて、当時のカナリーという組織における合意形成の方法や、課題に対する解像度が深まっていきました。
これまでデザインの活用が進んでいなかったカナリーでは、デザイナーへの期待はあったものの、具体的に何をしてくれるのかは組織全体でイメージがついていない状態でした。
社内でデザイナーの役割に対して信頼が得られていない状態で、リブランディングのように定量的な成果が見えづらいアプローチを組織全体に向けて行うと、意図せず “飛び道具” のように感じられてしまいます。
このようなタイミングでは、本来は「もっと小さな範囲から地道に実績を出し、信頼構築をする」「デザインに注力することで、良いことが起こることを組織に癖付ける」ということから始めるべきです。
いきなり全社に向けたアプローチから始めるのではなく、「どんどん自由に進行してください。」と言われる範囲がどこなのかを見極め、ある意味勝手に進めて、結果で示していく必要がありました。
もともとデザイン組織は、開発組織に所属していました。それならば、自分が持っている権限の中で、最も影響しやすいのはプロダクトチームだろうと考え、改めてこの範囲でアウトカムを最大化するための動きに全力を尽くすことに決めました。
当時のプロダクトチームにもいくつもの課題があり、その一つとして、マネージャー陣とメンバー間において情報の非対称性が生まれ、意思決定の背景が見えづらくなっていたことがありました。
そこで、情報をよりアクセシブルに、透明性を上げていくこと。それによってチーム全体が事業とプロダクトに強固な共通認識を持った組織にしていくことを目標に定め、様々な動きを始めていきました。
まずは開発フローの中で「よしなに」ハイコンテキスト化してしまいがちだったところを、可能な限り徹底的にローコンテキスト化していくためにも、ドキュメント整備やフローを構築を進めました。
施策ドキュメントに常にあらゆる関連情報を添付する、一次情報としてのユーザーボイスからしっかりと要求を抽出するためユーザーストーリーを書くなど、メンバーと多くのコミュニケーションを取りながら改善を進めます。
また、PdMのリソース不足などが情報共有の漏れにつながる一つの理由でもあったため、プロジェクトマネジメントの負担をチームで分け合えるように、エピック単位でカナリーの開発ラインを切り分け、PdMが入らなくとも施策の意思決定が進むようにフローを変更しました。
これらの改善により、チームが一丸となって共通認識のもとソリューションに向けてコミットしていける環境が少しづつ整っていきました。
また、メンバー全体がチームを良くしたいというポジティブな思いを持っているにもかかわらず、やはり認識のずれによるもったいないミスコミュニケーションなども生まれているように見えたため、また、個々人の目線がより開発チーム全体に向いていくように、「良いチームとは何か」を議論するワークショップを開催しました。
正直、ワークショップのアウトプットは、どんなものになっても良いと思っていました。チーム全員に、開発プロセスや体制を変えていこうという意識が芽生えていくことこそが大事だと考えていたためです。
こうして少しづつ共通認識がとりやすくなっていったため、より大きなプロダクトにおける改善施策にも取り組み始めることができました。
例えば、効果に対する不確実性が高く優先度が下がりがちであったWebのスタイル整備も行いました。一つ一つヒューリスティック評価などによる改善案出し、優先度付けを行い、しっかりと小さな開発アイテムごとに切り分けてリリースを進められたことで、CVRの向上や様々な効果につながっています。
このように良い効果が見え始めていたこともあり、さらに強い開発組織を目指しユーザーリサーチをカルチャーとして浸透させていくための動きも始められました。
事業判断にユーザーの声を活かしていくため、エンジニアまでを含めたチーム全体でユーザーへの理解を深め、共通化していくために、ここでもやはり仕組み作りからコミット。常にリサーチやインタビューの内容を速報的にチームに共有し、誰でもアクセスしやすい場所にドキュメントとして整理しておくことなどに取り組みました。
そうしてまた浸透が進んでいった結果、PdMと一緒に定めた事業的な関心ごと (イシュー) に対して、1週間でデザイナーがインタビューをもとにインサイトを抽出してくるサイクルの「リサーチスプリント」という定常的なアクションへつながっています。
開発組織へのコミットを始めてから約1年、リブランディングのプロジェクトの時とは変わり、カナリー全体にデザインの活用が広がり始めています。
今は、toC側だけでなく、toB側にまでデザイナーの影響が及ぶようになっています。例えば以前公開したような、新機能探索の取り組みや、デザインシステムの構築などの開発組織全体を巻き込む取り組みも推進できています。
また、株式会社サイバーエージェントにてソーシャルゲームのUIデザイナーを務め、その後ABEMAに異動し「ABEMA FIFA ワールドカップ カタール 2022」や「ABEMA de DAZN」などのメインUIデザイナーを務めていた寺本さんのようなデザイナーが入社してくれています。
組織全体で、ユーザーの声を活用していくためのリサーチ文化も醸成されてきました。
ここまで来れたのは、一歩目の取り組みで地道に結果を出し続けたことで、組織全体にデザインがどう活用されるのか具体的にイメージが湧くようになり、信頼をつかむことができたからだと思っています。
この2年間の取り組みを踏まえ、カナリーデザイン組織は次のフェーズに進んでいます。新しく入社してくれた寺本さんにマネージャーの引き継ぎが完了し、さらなる拡大に向けて動き出しました。
カナリーでのデザイン組織立ち上げから学んだのは、組織のカルチャーを見極め、溶け込んだ状態でやるのが一番大事ということです。
「この組織では、どういうことが重視されるのか?」「デザインの活用に対して、どのくらいイメージがあるのか?」などの観点を抑えて、それを踏まえたコミュニケーションや、実績の出し方を選ぶ必要があります。
多くの場合、デザインが重要であることは、誰もが分かっています。でも具体的な活用イメージが湧いていないことは多い。であれば、大きな意思決定は行えません。
そのような場合、大きなことにチャレンジしたいなら、まず泥臭く実績を生み、組織のレベルを上げることから始めないといけないのです。
少しずつ、デザインによって課題解決された経験を積み重ねてもらう。泥臭くやっていくと、やがて「デザインを活用して大きな価値を生み出そう」という流れが生まれていきます。
カナリーは、混沌期を抜け、デザインを本格的に活用していくフェーズにあります。これまで試行錯誤を重ねてきたからこそ、今まさにデザインの力でさらなる価値を生み出せるタイミングです。これから入るメンバーとも一緒に価値を創っていきます。