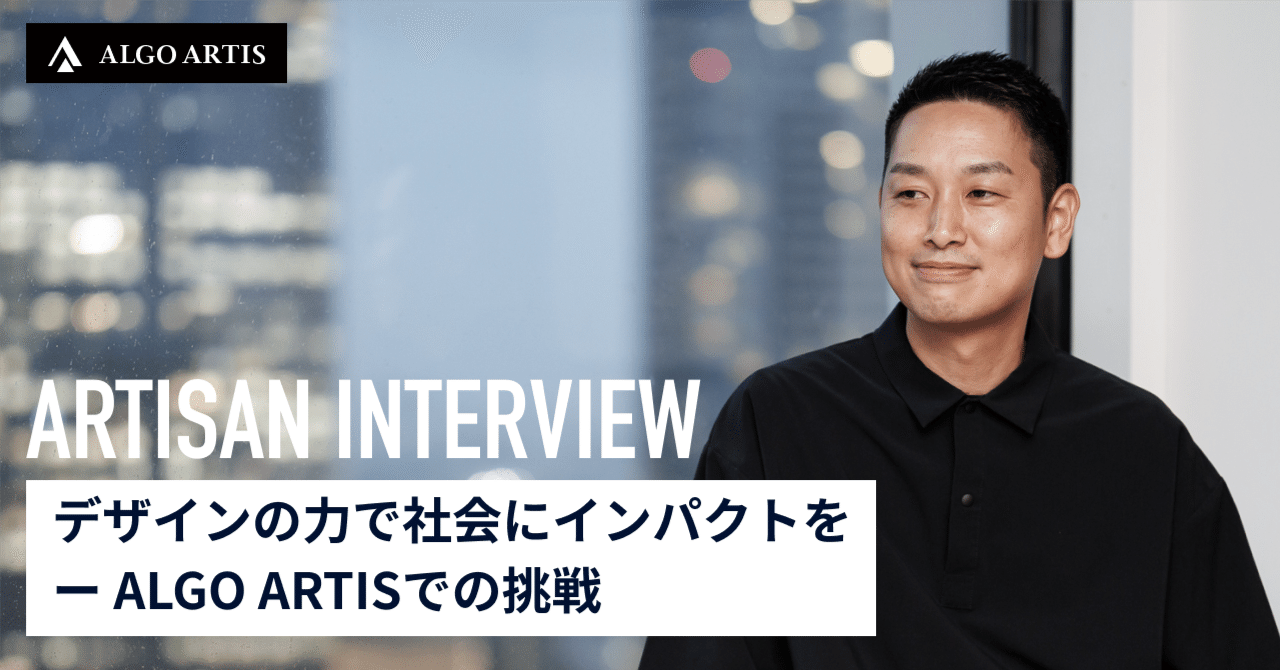高度な最適化AI(アルゴリズム)やソフトウェアを駆使した計画最適化ソリューションを提供するALGO ARTIS(アルゴ・アーティス)のデザインマネージャーとして働く、阪本です。
入社後の1年間で、デザイナーの社員1名、複数の業務委託パートナー (以下: パートナー) という体制から、ALGO ARTISという会社のデザイン活用の期待値を醸成していき、デザイン組織拡大に投資していく意思決定を引き出すまでに至ることができました。
どのように組織からデザインの期待値を醸成し、新たなポジションを確立するまでに至ったのか、その裏側を公開します。
私は、デザイン制作会社でのデザイナー、アートディレクター、スタートアップのデザイン責任者など17年のデザイナーキャリアを経て、2024年にALGO ARTISにジョインしています。
組織には社員デザイナーは1名のみという状況で、2人目の社員デザイナーとして入社しました。一方で、すでにパートナーのデザイナーは多数おり、単純に制作業務を担うだけでは自分に対する期待値は満たせないだろうと考えていました。
そのため、入社時から私のミッションは「デザイン起点でALGO ARTISの事業成長を作る」という広い役割に置いています。
先に結論から述べると、1年間の活動によって「この領域にデザイナーがいなくてはならない」という強い期待値を引き出し、デザイン組織拡大フェーズにまで至ることができています。
以下のような取り組みの順序 (余力づくり→成果を生む→組織構築) で進めてきたこの1年間の活動を、詳細にまとめていこうと思います。
1年間の活動の結果「ALGO ARTISにデザイナーはいなくてはならない」という期待値が引き出せている
デザイン組織立ち上げのプロセスを説明する前に、少しだけALGO ARTISという会社の事業構造や、デザイン活用状況について述べておきます。
ALGO ARTISは、高度な最適化AI(アルゴリズム)やソフトウェアを駆使した計画最適化ソリューションを提供するスタートアップです。
事業としては、AIを活用した運用計画の最適化ソリューションを個社別にフルカスタマイズして提供する「Optium(オプティウム)」と、業界特化型のクラウド型生産スケジューラ「Planium(プラニウム)」の2つを開発・提供しています。
ALGO ARTISの事業運営の特徴としては、複数のプロジェクトが同時並行で動いていることです。特にOptiumでは個社別のソリューションを提供するので、個社ごとにプロジェクトがつくられチームが構成されます。
一方で、当時はデザイナー不在のプロジェクトも多くありました。
私が入社した当時は、デザイナーの社員は1名。あとはパートナーのデザイナーが、必要に応じていくつかのプロジェクトに巻き込まれUI設計を担っているような状態でした。
この状況で、私が入社してまず取り組んだのは「デリバリーのフロー構築」でした。
パートナーのデザイナーは複数いたものの、依頼フローやアサインの基準などは整っておらず、プロジェクトオーナーが個別にパートナーに依頼をして、よしなにアサインされていたような状態となっており、これを改善するところから着手します。
ここに着手したのは、まずそもそも余力を生まなければ、デザインの期待値醸成には入れないだろうと考えたためです。
デリバリーで手一杯になっている状況をすぐさま抜けて、本当に成果を出すべきポイントに余力をぶつけていけるように体制から見直していきます。
功を奏したのは、ALGO ARTISには、レビュー不要で精度の高いUI設計ができるようなミドル〜シニア層のパートナーが揃っていたことでした。
ALGO ARTISがお客さまとしているのは、エネルギー業や製造業など、高度なドメイン理解が必要となる産業の方たちです。なので、ある程度自走できるデザイナーでなければUI設計も難しいので、レベルの高い人を採用すべきということはすでに社内の共通理解となっていました。
そのため、依頼をまずは社員である自分に集約し、各デザイナーのリソース管理をしながらアサインを振り分ける案件マネジメントフローを整えるだけで、かなりデリバリーの安定性が生まれていきました。(レベルの高いパートナーが揃っていたので、レビューの仕組みなどはほとんどテコ入れしていません。)
約2ヶ月ほどで、パートナー中心にうまくデリバリー業務が回るようになってきたため、次のステップへと注力を移していきます。
2〜3ヶ月の取り組みの結果、デリバリーの安定化がされた状況で、すぐさま「デザインがあったからこそ起こった」と言える変化づくりに取り組み始めます。
ここで “体制拡大” ではなく、新しく役割を見つけるための “変化” へと向かっていったのは、組織内でのデザインへの期待値が成り立っていなかったためです。
デリバリーは安定してきたものの、まだまだデザイナーが入ってないプロジェクトも多い。つまり「まだ組織や事業に、当たり前にデザイナーが必要とされている状態ではない。」ということです。そこでデリバリー体制の拡大ではなくて、期待値を生むところからやる必要があると捉えました。
当時はまだ社員デザイナーは2名。
なので、ガチガチに体制仮説を組んだりワークフローから考えるのではなくて、力を求められているところに入っていき自分がまず結果の出し方を示す、というアプローチを取りました。
これは後から振り返ると思うことですが、最初の成果がまだ生まれていない時は、以下の3つの要素を持った場所で、思い切り成果を出しに行くことが大事だと考えています。(と言いつつ、当時はこんな言語化をしていたわけでなく、嗅覚で動いていました。)
デザインの価値を分かっている人がいる
デザインで変化を出しやすい
事業的なインパクトが大きい
これらのポイントを押さえつつ、少ないリソースの中で、デザインの使い所を1点に集中させていきました。
まず一つ目に「デザインの価値を分かっている人がいる」というポイント。組織全体ではデザインへの期待値が醸成されていなかったとしても、人単位で見ると、過去の経験からデザインの重要性に気付いている人が必ずいるはずです。デザイン単体から成果を出すことは難しいので、この期待値がすでに高い人を巻き込んで、一緒に成果を出しに行くことが重要だと思っています。
二つ目の「デザインで変化を出しやすい」とは、デザインを取り入れる前後での変化量の大きい場所を狙うということです。現時点で課題が大きく発生しており、かつ、デザイン的なソリューションを打つことにより課題解決が大きく起こる。このような場所を見極めていくことで、「デザイナーがいてくれて良かった」という状況をつくることができます。
三つ目の「事業的なインパクトが大きい」とは、これらの変化を、事業文脈に載せていくということです。たとえ変化量が大きかったとしても、それが事業的に優先度の低い場所だったとしたら、「事業に必ずデザイナーが必要な状態」とはなりません。事業優先度を捉えて、最も解決されたい課題に取り組み「事業全体で必要とされる結果」をつくることが大切です。
ここで、最初に成果を出そうと選んだのは、Optiumでの「難易度の高い案件受注」と「プロジェクトの要件定義」でした。
OptiumはALGO ARTISにおける収益の柱であり、1社ごとのプロジェクトに深くコミットする高付加価値型の事業モデルです。一方で、複数の業界の企業に対して、各企業ごとの具体的な業務を進めるためのアルゴリズムを組むというプロセスは難易度が高く、プロジェクトを進行するためにいくつもの問題が発生していました。
—
受注前: セールス面
高付加価値なプロジェクトであるため、受注前にも解像度の高い提案が必要となる
個社ごとに毎回異なる業務なのでキャッチアップコストも大きく、一般的なセールスプロセスでは受注に至らない
受注後: システム開発面
個社ごとに全く異なる業務を毎回調査し、アルゴリズムに落とし込む/システムに落とし込む難易度が高い
開発以前に、要件定義が難航し、プロジェクトがうまく進まないことも
アルゴリズムで解決する部分を不必要に大きくしてしまい、開発工数が膨れ上がってしまう
—
つまり、デリバリー以前に、提案フェーズや受注後のシステム設計フェーズで、顧客解像度を高める仕組みがないことがボトルネックになっていると捉えました。
そこで、デザイナーとしてリサーチに注力し、プロジェクトの受注からシステム提供、運用までスムーズに進んでいくように、セールスの提案や、プロジェクトのディレクションに入り込んでいくこととします。
パイロット的に始めようという話を社内で合意しつつ、以下のように事業構造を整理して、入るべきポイントは2つだと特定します。
提案フェーズでの課題整理とデモプロトタイプの作成 (受注率の改善)
プロジェクト開始フェーズの要件定義 (プロジェクト推進への貢献)
■ 提案フェーズでの課題整理とモデル化 (受注率の改善)
まず1つ目が、提案フェーズへの関わりです。
これは、前述したような「毎回異なる業種の複雑なオペレーションを読み解き、提案に落とし込む難易度の高さ」を改善するために行いました。分かりやすい成果としては “受注率” に貢献するということです。
具体的には、セールスのメンバーと一緒に、提案前段階の難易度の高いプロジェクトに入り込みました。
Optiumの提案において大事なのは「アルゴリズムによって業務が大きく改善されそう」と感じてもらうことです。ただ、そのためには非常に複雑なお客さまの業務を読み解き、課題に刺さる形で、AsIsとToBeでどれだけ変化が起こるかを直感的に感じていただく必要があります。
そこで、デザイナーから、提案前のヒアリング情報を整理し、提案資料やプロトタイプの作成を行いました。
入社直後でドメイン理解がない状態だったので、個社のヒアリングをもとに「ここは確かに課題になっている」という部分を丁寧に整理していくような考え方をしました。例えば以下のような観点を提案資料に落とし込んでいます。
受注を決めていただけるようなソリューションコンセプト (解決できることを一言で)
担当者の課題や苦労していること
現状の業務の流れ、どのくらい負荷がかかっているか
システム導入後に現状の運用方法とどう変わっていくのか
このように具体的で解像度の高いアウトプットを示したことで、お客さまからも「業務のことをよく分かってくれている」という安心感を得ていただくことができたのではないかと思います。結果、難易度の高いプロジェクトでしたが、スムーズに受注にまで至ることができました。
■ プロジェクト開始フェーズの要件定義 (プロジェクト推進への貢献)
2つ目に入り込んだのが、プロジェクト開始フェーズです。プロジェクトが開始してからも、複雑な業務ゆえに「どこをアルゴリズムにすると良いか?」「どのようなインターフェースが最適か?」ということを要件に落とし込むのは難易度が高いことでした。
そこで、ここでもデザイナーとして「業務理解」を進めていくことで、要件設計を推進しました。リサーチ項目を設計し、計画業務が行われている現地に足を運んで業務の全体像を整理します。
さらに、顧客中心な発想で、既存の業務からどこをアルゴリズム化するか、どこを人力のままにしておくか、どこをプロダクトのインターフェースで解決するか、という線引きをしてカスタマージャーニーのモデル化を行います。
最終的にステークホルダーともうまく合意をつくることができ、これまでよりもスムーズに開発・実装フェーズに進行していきました。
このような2つの事例を数ヶ月の間につくったことで、結果として「このような探索的なアプローチを、Optiumのすべてのプロジェクトで実施できるようにしていきたい」という期待値を経営・組織全体から引き出すことができました。
逆に、デザイナーのリソースが少ない中で、新規事業であるPlaniumについては意識的に「見守るだけに留める」アプローチを取りました。
Optiumの事業優先度の高さに加えて、Planiumはすでにスキルの高いプロダクトマネージャーを中心にディスカバリーが回っており、デザイナーはデリバリー部分に入れば問題ない状態となっていたからです。
Planiumに対しては、基本は見守りの姿勢を取り続けていましたが、一度だけ「放っておくとユーザー中心な文化が失われてしまいそうなタイミング」でテコ入れをしたことはありました。
Planiumのリリース後に「実際にユーザーが使っているところを見れていない」という課題があがり、私に相談をしてもらいました。そこで私から顧客観察手法を提案し、サポートすることとしました。
すぐさま、実際にPlaniumを利用する方の観察をしにいく見学ツアーを企画し、プロジェクトメンバーみんなでクライアントの工場見学を行いました。この時、どんな項目を聞きたいかは、自分たちで言語化してもらえるように整理を手伝います。
このような動きはチームに定着し、機能リリースをしていくことはもちろん、その裏側で必ずユーザーがどのようなことを重視しているのかを確認するチームの文化ができています。
ここまでに出した成果をもとに、組織構想を進めます。
組織全体に対して「デザイナーはこのポジションを担う」というコミットメントをしていくようなイメージです。
現在もこの組織構想を各関係各所と進めているところですが、基本的には「事業推進のために必要なモデル化」をコアな価値としたデザイン組織設計をしようとしています。
段階としては2段階。今回出した成果を軸足に、徐々に範囲を広げていくような流れで組織設計を行う想定です。
プロジェクトの進め方のモデル化: 複数同時並行で走っているプロジェクトに探索のアプローチを当たり前に
プロジェクトをまたいだモデル化: 産業ごと、案件ごとなど共通する部分を抜き出し、汎用化
探索によって、プロジェクトの進め方のモデル化、プロジェクトをまたいだモデル化、を繰り返していくのがデザイン組織の役割
この組織構想をもとに、すでに体制構築に動き出しています。
社員は、複数のプロジェクトに入り込み、提案からプロジェクト推進まで幅広く探索的なアプローチを取り入れられることに加え、その後プロジェクトをまたいだモデル化にも取り組めるような人材を採用していくことと決めました。
要件は高いですが、前述の通り、すでにパートナーの方を巻き込んだデリバリー体制は構築できており、「社員だからこそできる部分」を突き詰めて妥協しない採用活動に取り組んでいます。
ここまでの流れがALGO ARTISにおける、「最初の結果を出し、新ポジションの採用に至るまで」の全貌でした。
結果として、入社後の1年間で、デザイナーの社員1名、複数のパートナーという体制から、ALGO ARTISという会社のデザイン活用の期待値を醸成していき、デザイン組織拡大に投資していく意思決定を引き出すまでに至ることができました。
まだまだ、リソースの問題で成果を組織全体に普及することはできていませんが、すでに「ここに投資すれば成果を出せる」と言えるレベルには検証を進められたのが良い点でした。
振り返ると今回のようにまとめられたものの、当初からクリアに全てを見通していたわけではもちろんありません。しかし、「今はデザインに期待があるタイミングかどうか?」「どこで力を発揮すればデザインに期待が生まれるか?」という思考は常にしていたように思います。
このような1年間の活動を経て、会社からのデザインへの期待値の変化についても聞いてきたので、こちらにまとめておきます。
私がデザイン組織のマネジメントとして一番意識しているのは「デザイナーがいたから変わったことを増やす」ということです。
デザイン組織の立ち上げ時に特に多いのは「デザインが良いものであることは分かっているけど、具体的な期待が生まれていない」というシチュエーション。このような場合では、変にルールにしたり、体制をガチガチに組まずに、柔軟に動いていくことも必要なのだろうと思います。
ただ、そこで御用聞きになるのではなく、「デザイナーがいたから、これだけ大きく変わった」と言えるような場所を選び、成果を出すと決めたら思い切り成果を出しに行く...と、そのような推進力と戦略の両方が大事です。結果を出せば、組織からの期待が明確になり、また次のフェーズへと進むことができます。
ALGO ARTISは、一つ目の成果を明確にできたので、ここからは組織化のフェーズへと進みつつ、あるタイミングでまた新たな価値貢献領域を見つけ、また組織化へ...というループを回し始めることができています。あとは体制次第なので、魅力的な組織づくりに注力していきます。
次回は、本事例に記載していた「Optiumでの、探索的アプローチによる受注率改善 / 要件定義」という、ALGO ARTISにおける最初の成果の出し方について詳しく深ぼった事例を公開します。こちらもぜひご覧いただければと思います。