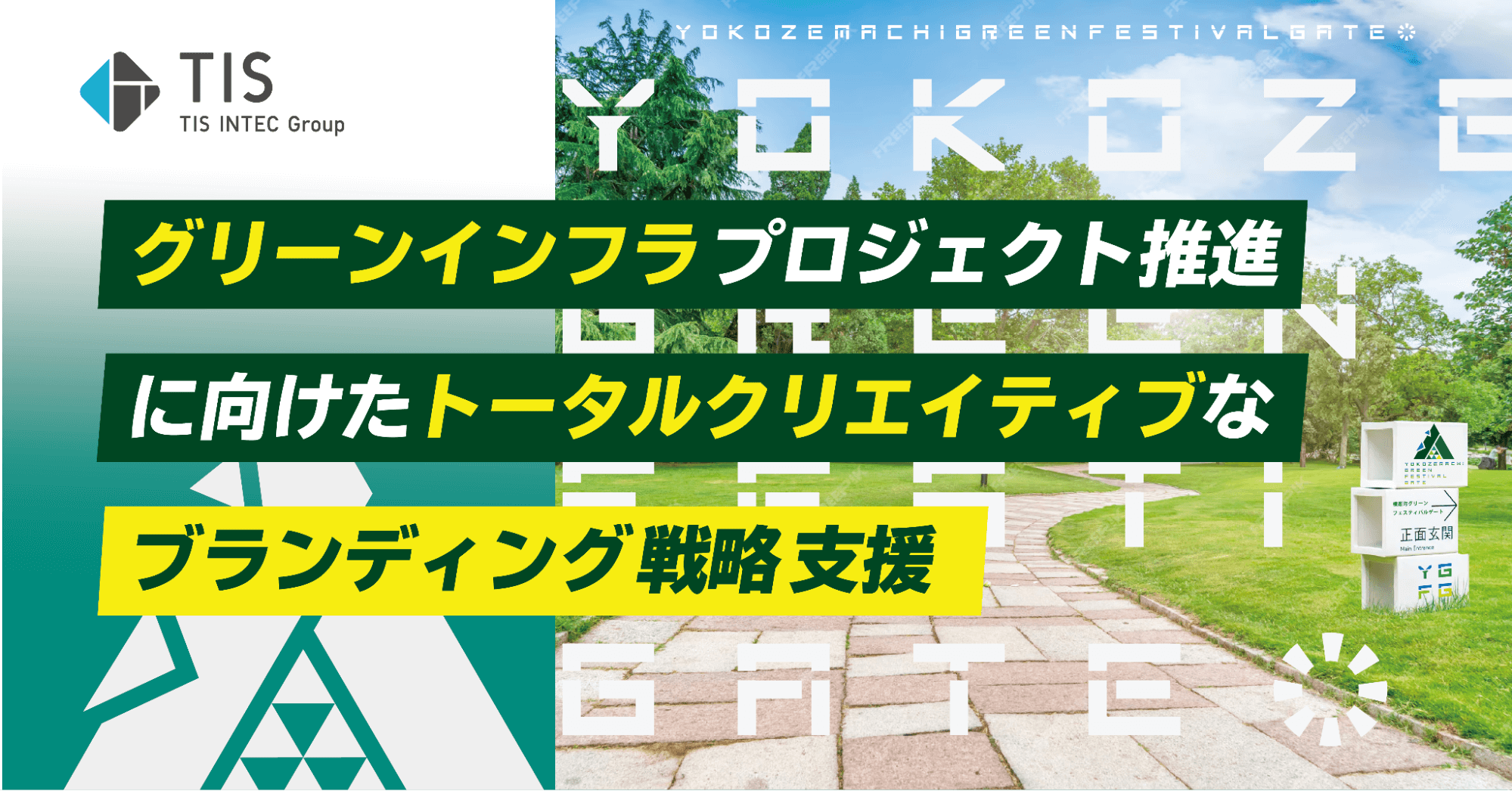TIS XD Studioでは、定量調査からは見えてこない地域の個性を可視化することで、住民参加型のまちづくりを促進するサービス「地域幸福度可視化アプリ」のデザイン支援を行いました。
本プロジェクトでは、サービスビジョンの再構築からユーザーリサーチ、そして継続的な利用を促すUX/UIデザインを一貫して支援しました。今回は、その取り組みの裏側をご紹介します。
「地域幸福度可視化アプリ」は、スマートフォンの位置情報を活用し、地域住民が日常の活動で感じた「ホッとする場所」や「自慢の場所」を記録できるWebアプリです。
記録されたデータは、地域幸福度(Well-Being)指標を補完するデータとして、企業や自治体、地域団体に共有されます。
このアプリは、近年世界的に注目されている「ウェルビーイング(心身ともに健康で、充実した生活を送っている状態)」という概念に基づいて企画されました。
価値観が多様化する現代においては、物質的な豊かさだけでなく、日常の中で感じる幸せや豊かさのあり方も人それぞれです。特に、地域ごとに「豊かさ」や「幸せ」の感じ方は異なります。例えば、多様なモノや文化が集まる都市に魅力を感じる人もいれば、静かな田園風景に安らぎを覚える人もいます。
こうした地域における幸福度をデータとして集約・可視化することで、その地域の個性に応じたまちづくりや地域活性化を促進できるのではないか――。そうした問いから、このアプリは生まれました。
「地域幸福度可視化アプリ」は、TISのデジタル社会サービス企画部が企画・開発を進めているプロジェクトです。同部署は、行政や国との連携を担っています。
2024年11月にはオープンベータ版の提供を開始し、サービスに共感いただいた複数の地域に導入され、PoC(概念実証)を実施してきました。
https://www.tis.co.jp/news/2024/tis_news/20241114_1.html
その後、サービス改善のフェーズへと移行したタイミングで、XD Studioに対してデザイン支援の相談をいただきました。
当初の相談内容は、主に「UIの見づらさ・使いづらさを改善したい」というものでした。
しかし、詳細なヒアリングを重ね、実際のUIを確認していく中で、「このアプリを通じて何を実現したいのか」「どのようなユーザー体験を提供したいのか」といった、本質的なビジョンをもとにした体験設計が不十分であるという課題が浮かび上がってきました。
サービスオーナーは、このアプリに対して強い想いを持ち合わせており、社会的意義が高い取り組みであることは明確でしたが、それらがアプリに十分に反映されておらず、結果としてUIの見づらさ・使いづらさといった表層的な問題として表れていたのです。
このままUIだけを改善しても、本質的なビジョンの実現にはつながらないのではないかと考え、プロジェクトの出発点を「サービスビジョンの再構築」とすることを提案しました。
その過程では、現状の姿とあるべき未来像を構造的に整理し、そこから導き出されるサービスビジョンの必要性について、プロダクトオーナーと丁寧に共有していきました。
その結果、単なるUI改善にとどまらず、サービスビジョンの再構築からUX/UI改善までを一貫して支援する方針が決定されました。
このような背景を踏まえ、実際のプロジェクトは以下の流れで進行しました。
ワークショップによるビジョンの言語化
コンセプト受容性を検証するユーザーリサーチ
ユーザーに使い続けてもらうためのUX/UIデザイン
最初に実施したのは、ワークショップによるサービスビジョンの言語化でした。
「地域幸福度可視化アプリ」の企画・開発を担う主要メンバー4名に参加いただき、サービスビジョンの再定義に加え、「誰に・どのような体験を提供したいのか」といったサービスコンセプトの明確化を目的として実施しました。
ワークショップの進行において意識していたのは、参加者それぞれの経験に紐づくエピソードの共有から始め、徐々に「目指したい姿とは何か」という議論へと展開させていくことです。
テーマである「ウェルビーイング」は抽象的で、人によって捉え方が異なる概念であるため、議論が空中戦になる可能性がありました。そこで、具体的な経験に基づくエピソードから話を始めることで、相互理解が深まり、共通言語が生まれ、より本質的な議論につなげることができました。
また、当時のアプリでは様々なユースケースが想定されていたため、「誰に対して最も価値を提供したいか」という優先順位を明確にすることで、体験をよりシンプルにする必要があると考えていました。
そのため、ワークショップのアジェンダにも、サービスコンセプト(誰にどのような価値を提供するか)の明確化を組み込みました。
事前に準備は十分に行っていましたが、印象的だったのは、私たちが積極的にファシリテーションを行わなくても、全員が自発的に議論を深めていたことです。その姿から、チームの皆さんが強い想いを持って「地域幸福度可視化アプリ」の企画・開発に取り組んでいることを実感しました。
次に、ワークショップで言語化したサービスビジョンやアプリコンセプトを踏まえ、サービスをどのような方向性で改善すれば、より本質的な課題解決につながるのかを把握するために、ユーザーリサーチを実施しました。
リサーチの設計にあたっては、デジタル社会サービス企画部のメンバーに丁寧にヒアリングを行いながら、調査の目的や対象、仮説を以下のように整理しました。
実際のリサーチでは、過去にPoCに参加いただいた民間企業の方々を対象にインタビューを実施。その内容をもとに、本サービスをいつ・どこで・どのように使ってもらうことで、企業と自治体の取り組みを成功につなげられるかといった点について分析を行い、結果をチーム内で共有しました。
本サービスでは、企業や自治体が主催する「まち歩きイベント」を起点として、地域住民やその街に関わる人々とともに街を歩き、地域の魅力を発見・収集していくことを想定しています。そのうえで、イベント後も利用者がアプリを継続的に使い続けることで、地域の魅力が蓄積され、住民の行動変容やまちへの愛着につながるような体験の構築を目指しています。
こうした体験の実現に向けて、ユーザーリサーチの結果をもとに、UX/UIデザインに取り組みました。
主なユーザーは、「利用者=地域住民やその街の関係者」と「管理者=民間企業や自治体」の二者で構成されます。利用者向けのアプリでは、街を歩きながら「いいな」と感じた場所や瞬間をアプリに入力することが主な使い方です。一方、管理者向けのアプリでは、集められたデータを集計・分析し、「自分たちの地域にはこういう個性や魅力がある」と把握するためのツールとして活用されます。
サービスが成立するためには、まず利用者がアプリを継続的に使いたくなる体験を設計することが重要です。そこで、まずは利用者側の体験に焦点を当て、ジャーニーマップを作成しました。まち歩きイベントに参加した方をメインユーザーと想定し、イベント中に街の魅力を記録し、イベント後も継続して利用してもらうためにはどうすればよいかという体験の仮説を整理しました。
特に意識していたのは、自己決定理論(E.デシ&R.ライアン 1985年)に基づいた体験設計です。
地域の隠れた個性を発見していくという体験に対して、内発的動機付けにより行動を促すために、3つの基本的な心理欲求である「自律性」「有能性」「関係性」を満たせる要素をUXに取り入れることを重視しました。
具体的には、ユーザー自身が選んだ特定のミッションをクリアしていくような体験を通じて、自律的かつ意味のある行動につながるよう設計しています。
また、地域の魅力の可視化方法も見直しました。これまでのヒートマップ的な表現に代わり、一般的な地図アプリのように「ピン」で表示する方式に変更することで、より一覧性と操作性の向上を図りました。
サービスビジョンやUX/UIデザインの再構築を経て、現在はより多くの地域での導入を目指し、地域活性化に取り組む企業での展開を進めている段階にあります。
その過程において重要となるのが、「サービスの意義にどれだけ共感してもらえるか」「アプリの活用イメージをどれだけ明確に持ってもらえるか」という点です。こうした背景を踏まえ、XD Studioではサービス紹介資料の作成も担当しました。
プロジェクトを連携しながら推進していた、TISのデジタル社会サービス企画部の方からは、以下のようなコメントをいただいています。
ここまで、「地域幸福度可視化アプリ」のデザインの裏側をご紹介してきました。
近年では、持続可能なまちづくりをはじめ、行政や地域と連携した取り組みに力を入れる企業も増えており、社会的意義のある価値創造に強い想いを持って活動されている方々も多くいらっしゃいます。一方で、そうした取り組みが一過性で終わってしまうケースも少なくありません。
単にサービスを形にするだけでなく、明確なビジョンに基づき、顧客中心の視点で「自然な行動が継続される」サービスへと落とし込むことが重要です。
TIS XD Studioでは、これまでも埼玉県横瀬町と連携したグリーンインフラプロジェクトの推進など、地域の社会課題解決に向けたデザイン支援を行ってきた実績があります。
行政サービスの開発や地域DXの推進などにおいてお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。具体的な支援ができるかどうかに関わらず、これまで培ってきた知見や経験をもとに、少しでも皆さまのお役に立てればと考えています。