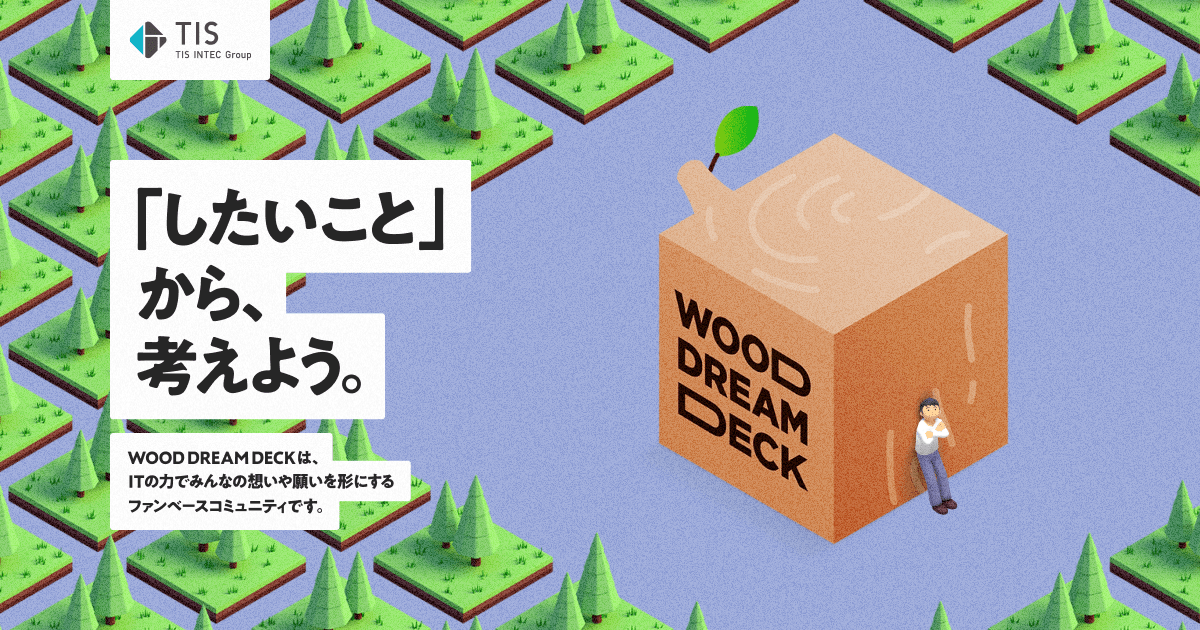TIS クリエイティブデザイン部では、2022年頃から、埼玉県横瀬町における地域の経済循環と森林再生の両立を目指した取り組みを進めてきました。
その一環として、国土交通省と横瀬町が連携して推進するグリーンインフラプロジェクトに協議会メンバーとして参画し、トータルクリエイティブの支援を行っています。
核となるコンセプトは「YOKOZEMACHI GREEN FESTIVAL GATE」。横瀬町ならではのありたい姿を御旗として掲げ、産官学や地域内外の人々が交流しながら、積み木を重ねるように共にまちを創りあげていくという想いが込められており、このコンセプトに基づいたトータルクリエイティブ構想を設計しました。
私たちが提案したこれらの構想は、横瀬町におけるグリーンインフラの計画に組み込まれ、まさにこれから実現に向けて動き出そうとしています。
今回は、TISが横瀬町において行ってきたことや、その背景にある「社会課題をゼロからプラスの視点で解決していく」というアプローチについて紹介します。
WOOD DREAM DECK は、森林資源の循環利用を推進し、社会課題の解決を目指す、横瀬町のファンベースコミュニティです。横瀬町の住民をはじめ、多くの方々が共感し、これまでに横瀬町の森林資源を活用したさまざまなアウトプットが生み出されてきました。
TISも2022年頃から「WOOD DREAM DECK」プロジェクトを通じて、IT技術を活用しながら、横瀬町における地域の経済循環と森林再生の両立を促進することを目指し、活動してきました。
その成果の一つとして、林野庁が運営する 「ウッドデザイン賞」 を、2023年・2024年に2年連続で受賞するなど、社会的にも高く評価されるプロジェクトへと成長しています。
2024年 受賞 : 伝統工法のデジタル化による公共物の創作
WOOD DREAM DECKをはじめ、横瀬町では森林課題の解決に向けた複数のプロジェクトが展開されています。これらの取り組みが評価され、2024年には国土交通省の「先導的グリーンインフラモデル形成支援」の重点支援団体として、横瀬町が選出されました。
横瀬町でのグリーンインフラの実装推進に向けて、TISクリエイティブデザイン部は協議会メンバーとして参画しています。国土交通省や横瀬町をはじめ、複数の団体が参画する本プロジェクトにおいて、グリーンインフラのコンセプトや理想像を描き、提案する役割を担っています。
ここからは、実際にどのような考え方やプロセスで提案を行ってきたのかを紹介します。
グリーンインフラの推進と一口に言っても、その領域は多岐にわたり、明確な定義はありません。そこで、横瀬町の良さを活かした、横瀬町らしいグリーンインフラのあり方を考える必要がありました。
着目したのは、横瀬町における住民と自然との接点です。
自然豊かな地域でありながら、住民が日常的に触れ合うのは整備された公園などの人工的な自然が中心であり、本来の自然に触れる機会が少ない状況にありました。その結果、地域の自然環境への関心も向きづらいという性質が見えてきました。
つまり、「人工的な自然」と「ガチの自然」との中間点があまりないと考えたのです。
そこで構想したのが、「森のInterface」というコンセプトです。
地域内外の人が集まる中心地に、周辺の自然を模した小さな森のような場所をつくり、横瀬町の豊かな自然を身近に感じられる場とすることで、自然への関心を高め、そこから新たなプロジェクトが自律分散的に生まれていく流れを促せないかと考えました。
横瀬町における自然と人との新しい関係性を築き、自然と共存する社会を目指す。このような方向性を基に、横瀬町の中心地におけるトータルクリエイティブを構想しました。
トータルクリエイティブを構想するにあたり、単に施設や景観といったハード面だけ形作るのではなく、横瀬町ならではのグリーンインフラのまちづくりの未来図を「御旗」として可視化することを重視しました。
それによって、共感する人々が集まり、積み木のように積み上がりながらまちづくりが進んでいく——そんなストーリーを実現していくことが必要だと考えたのです。
近年さまざまな地域でまちづくりのプロジェクトが発足していますが、関係者が多い中で、明確な指針がないまま進めてしまうと、全体の方向性がまとまらず、ちぐはぐな状態になってしまいます。そのため、上記のような御旗によって、関係者が同じ目線を持って取り組めるようにすることも重要な視点の一つだと捉えています。
では、どのようなプロセスで、どのような構想を提案していったのか。その詳細をご紹介します。
まずは、横瀬町の住民の方々に参加いただき、コンセプトワークショップを実施しました。それぞれの視点から、横瀬町が目指す未来について意見を出し合い、キーワードを抽出しています。
さらに、キーワードを環境・社会・健康・防災・経済といった領域ごとに分類し、それぞれの未来像を整理します。加えて、異なる視点から横瀬町の価値を見出すためにSWOT分析を行い、それらを掛け合わせながら、検討を進めました。
このような過程を経て、グリーンインフラを軸としたまちづくりの指標を図式化したものが以下です。
産学官民の交流と共創を促すメインエリアを中心に、「体験型スペースエリア」「学びの活動エリア」「ウェルネスエリア」「共創と創作エリア」の4つのエリアを構成し、それぞれが連動しながら、まちづくりが進んでいくような未来像を描きました。
そして、この未来像を実現していくためには、「アイコニックブランディング」というアプローチに沿って進めることが適切だと考えました。
これからの横瀬町の未来像を、ロゴをはじめ、プロダクト、スペース、建築など、あらゆるモノやコトにアイコニックに反映させることで、地域内外の人々の記憶に残り、共創が生まれる場をつくることを目指しました。
この考えを基に、あらゆるコミュニケーションやクリエイティブを構築していきました。
例えば、中心となる場の名称には 「YOKOZEMACHI GREEN FESTIVAL GATE」 を掲げ、ロゴは豊かな自然のイメージと、積み木をみんなでつくりあげる未来をモチーフにしたビジュアルで構成しています。
また、ロゴを起点に、各種コーポレートツールや、プロモーションツール、さらに施設やスペースなど、あらゆる場面に展開することで、横瀬町の理想像に触れる機会が増え、共感してくださる人々が増えていくようなイメージを構築しました。
さらに、前述の 「体験型スペースエリア」「学びの活動エリア」「ウェルネスエリア」「共創と創作エリア」 などのエリア展開と連携しながら設計を進めることで、自然とコミュニティが形成され、共創によってまちづくりが推進されていくことを目指しています。
このような構想をTIS クリエイティブデザイン部として設計し、横瀬町の担当者に提案しました。
この構想は、横瀬町におけるグリーンインフラのアクションプランに組み込まれ、今後、その実現に向けて具体的な取り組みを進めていく予定です。
ここで、TISのこれまでの取り組みに対し、横瀬町役場の田端さまからコメントをいただきましたので、ご紹介します。
今後も、「日本一チャレンジする町」をスローガンに掲げ、先進的な取り組みに挑戦し続ける横瀬町の皆さまとともに、より良い未来の実現に向けて取り組んでいきます。
今回まとめた横瀬町におけるグリーンインフラプロジェクトや、WOOD DREAM DECKという取り組みの背景には、社会課題を“マイナスからゼロ”ではなく、“ゼロからプラス”の視点で解決しながらマイナスの課題を解決していくという私たちの考えがあります。
顕在化した課題を解決するアプローチには多くのプレイヤーが挑戦していますが、それでも解決されず、いまだに社会課題として残り続けているものも少なくありません。
こうした状況において重要なのは、単に課題の解決を目指すのではなく、思い描く“より良い未来”を広く発信し、そのビジョンに共感する人々を増やし、共創の輪を広げていくことです。その結果として、社会課題が解決されていく。このように、“ペイン”ではなく“ゲイン”を示しながら、ゼロからプラスへと社会を前向きに変えていくことが重要だと考えています。そして、ゼロからプラスを実現することで社会に浸透させて、マイナスからプラスにつながっていくクリエイティブな社会課題解決を目指しています。
今回実践した、横瀬町ならではの未来を御旗として掲げてブランディングしていくというアプローチは、まさにその考えを体現したプロジェクトの一例です。
TISでは、地域社会に寄り添い、その地域ならではの未来を描き、地域内外の人々を巻き込んでいくサポートを行うことができます。私たちの取り組みに興味を持ち、一緒に挑戦してみたいと思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください。