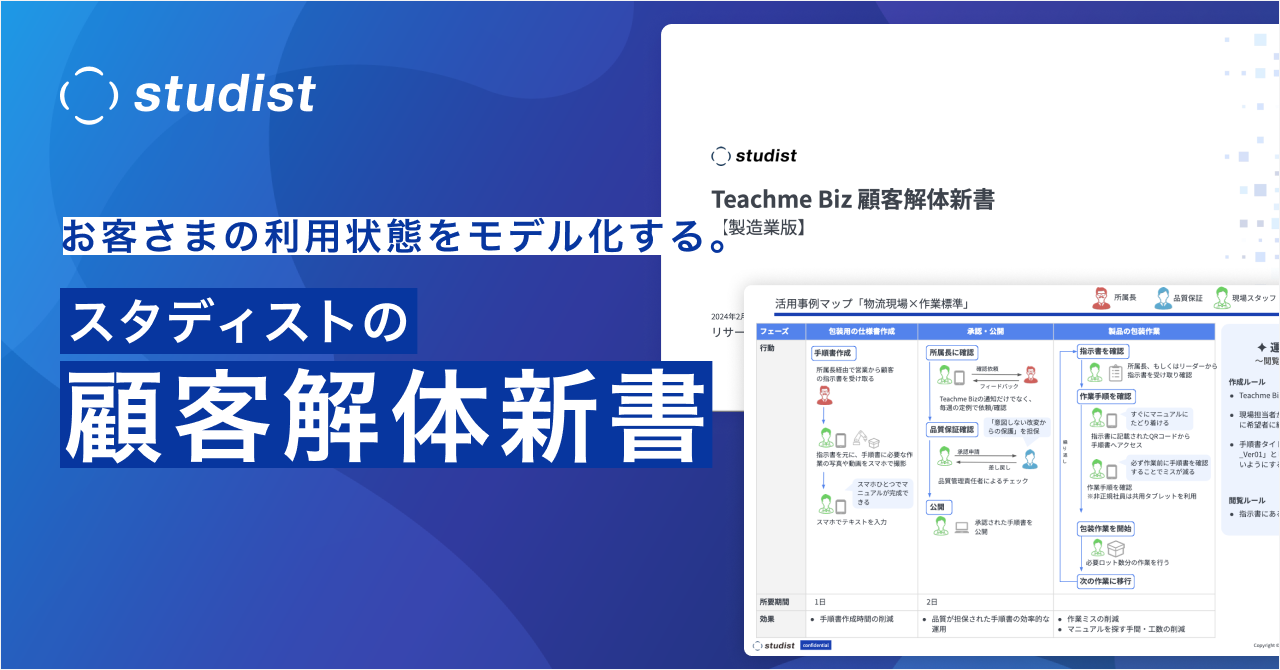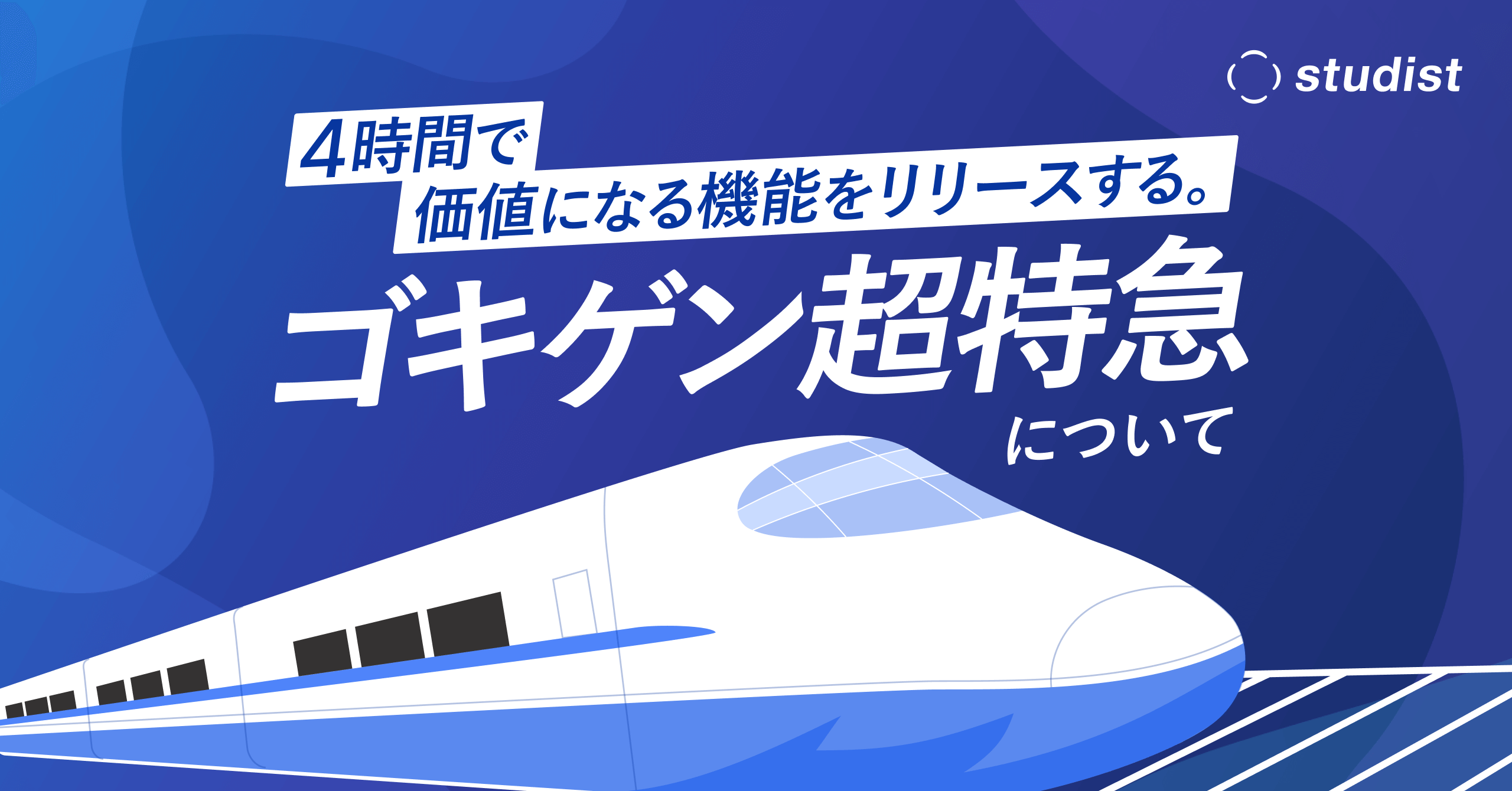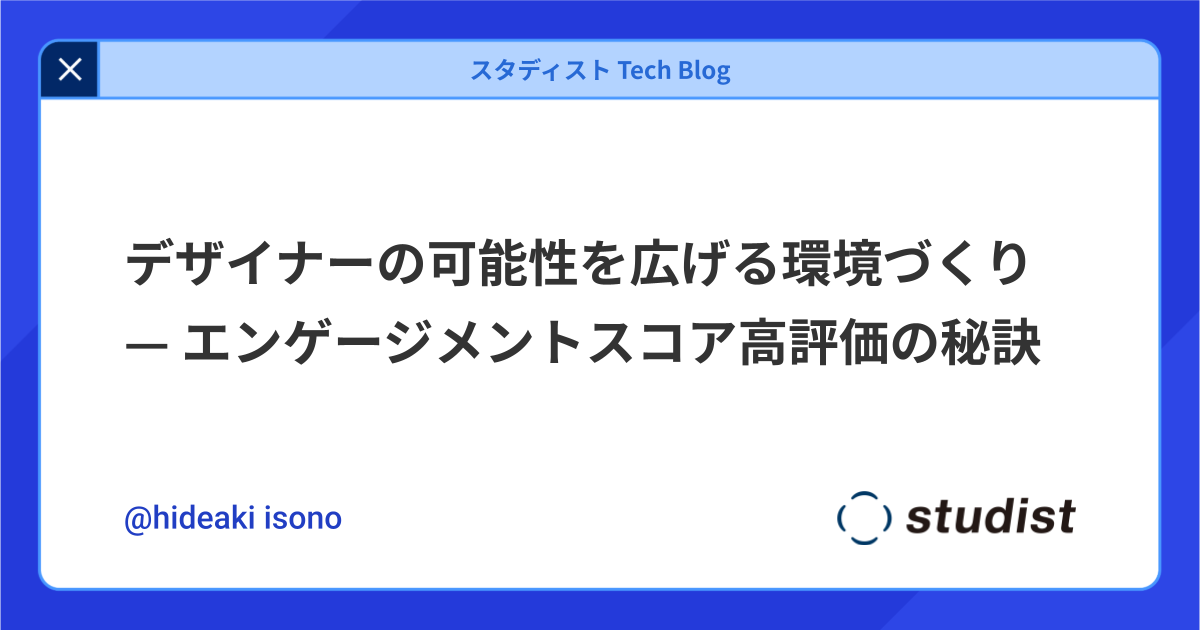スタディストのリサーチ&デザイン室のマネジメントをしている磯野です。
現在は5名が所属するリサーチ&デザイン室。2019年まではデザイン専任のマネージャーはいませんでしたが、2020年にプロダクトデザイングループを設立し私が専任のマネージャーに就任、2024年にグループから室に格上げし、リサーチ&デザイン室と改称してきた歴史があります。
自分は2020年のマネージャー就任からデザイン組織のマネジメントとして、スタディストにおけるプロダクトデザインが効果的に機能する体制を構築することに尽力してきました。
この事例では、スタディストデザイン組織の変遷と、基盤となる戦略「デザインブースト」の考え方について解説し、デザイン組織のマネジメントに携わるみなさまに少しでも知見を共有できればと思っています。
スタディストには、2019年までは専任のデザインマネージャーがおらずデザイン組織といえる形にはなっていませんでした。デザイナーは開発本部に所属しながら主にUI設計を役割とし、その他社内のデザイン業務も依頼ベースで対応していました。
当時、UXデザインはプロダクトマネージャーが行う形になっており、デザイナーの役割は狭い範囲にとどまっている状態でした。一部のデザイナーは体験設計や、新規事業のリサーチなどにも関わっていましたが、全体としては限定的な役割にとどまっていました。
私は、当時、開発部の中で副部長とPdMを兼務し、組織のマネジメントとプロダクトマネージャーの支援に取り組んでいました。
組織のマネジメントやプロダクトマネージャーの支援を行う中でUXデザインの支援も行っていました。しかし、プロダクトマネージャーがUXデザインまで担当する形は限界があると感じてきていました。
その現状に対して、今後を見据えUXデザインを担う組織を作ることが必要と考え、組織の再編に取り組みました。
立ち上げ時点では組織の規模やメンバーの経験も限られていたため、全部を一気に変えることは現実的ではありませんでした。
デザインの専門性を扱う組織をマネジメントするときに難しいのは、影響を与えられそうな範囲が広く、いろいろ半端に手を出してしまいやすいことです。例えば、マーケティングデザイン面や、ブランドデザイン面など、デザインが貢献できることは多岐にわたりますが、どれもこれもやれるほどのリソースも専門性もありませんでした。
当時、スタディストにはデザイナーは3名しかいませんでした。 新たにUXデザインに取り組んでいくならば、全部取りをするのではなく、思い切ってプロダクトのデザインに注力を絞っていくべきだと考えました。
デザイン組織に限らず、組織の役割を設計するときのポイントは3つあります。それぞれ、踏むべきではないアンチパターンもあり、以下のように整理できます。
スタンス
🙆… 出したい結果を役割にする(会社や事業が主語)
❌… 手段が先行する (デザインを主語にしてしまう)
解くべき課題
🙆… 事業や組織のフェーズが変わる課題に集中する
❌… 闇雲に幅広く手を出してしまう
取り組む範囲
🙆… 等身大に、一歩先の範囲に取り組む
❌… 身の丈に合わない役割を掲げる (遠すぎるゴール / 広すぎる領域)
デザイン組織立ち上げにおいて最も避けるべきは、「デザインはこうあるべき」という過剰な期待を自分たちが持ってしまい、あれもこれも手を出してしまい、結果として何も達成できないことです。
あくまで少し背伸びすれば達成できる範囲から。そして、取り組めば組織や事業のフェーズが変わるような一点に集中すること。これがマネジメントにとって不可欠な視点だと思います。
これまで述べてきた組織の役割を設計するポイントをスタディストに当てはめて、組織の役割をいくつかの段階に分けてに落とし込んだのが、スタディストデザイン組織のロードマップ「デザインブースト」です。
この「デザインブースト」では、組織が立ち上がってから、どのように役割を拡張していくのかを段階的に定義しています。
最終的なゴールとして「デザインが経営に貢献できている状態」という指針は持ちつつも、そこに至るまでにデザイン組織としてどのように役割を拡張していくのかを段階的に表したロードマップです。
この段階定義は、事業・組織・デザイン組織の状況によって異なります。あくまで「スタディストにおいては、この登り方がベストだと捉えて進めてきた」と読んでもらえると嬉しいです。根本的な設計思想は、どの組織でも参考にできるだろうと思います。
スタディストのデザイン組織は、このデザインブーストの考え方に基づき、以下のような変遷を辿っています。
まずは「プロダクト開発への貢献」から
その後「ビジネスプロセスの支援」へ
このようにデザイン組織の貢献範囲と専門性を少しずつ広げていくように進めてきました。
ここからは、デザインブーストの考え方に基づいた、スタディストのデザイン組織変遷を実例とともに紹介します。
2020年、スタディストで初めての専任のマネージャーがいるデザイン組織である「プロダクトデザイングループ」が設立されました。
前述の通り、その時点のスタディストでは、デザイナーが担当している範囲は機能案が固まった上でのUI制作が中心でした。プロダクトデザイングループでは「顧客の課題定義まで入りこみ、コンセプトを決めて一貫した解決策の作成を行う」という役割を担うことを目指しました。
具体的には、顧客の課題定義から入り込み、コンセプトを決定し、一貫した解決策の作成を行うために、以下のような新しい取り組みにチャレンジすることから始めました。
ユーザビリティテスト:UIデザインの意思決定をユーザー中心で行うため
ステークホルダーインタビュー:開発テーマのゴールイメージの共通認識を作り、検討を主導するため
ユーザーインタビューとプロトタイプ検証:顧客中心で検討、検証を進めるため
デザインスプリント:開発チーム全員の共通認識づくりと迅速にアイデアを出し検証するため
もちろん、新しいことに取り組むにあたっては組織として社内勉強会などで学習時間を確保することや、マネージャーが新しいチャレンジを全力でサポートするといったことも非常に大事にしていました。
デザイナーの専門性を高めていく活動と同時並行で、デザインをデザイナーだけが担う状態を解決することにも取り組みます。
プロダクトデザイナーの人数が増えてくると、分業化が進むことで、コミュニケーション不足や連携不足といった問題が発生する可能性があります。
例えば、エンジニアがUI設計の段階では関わって良いものか分からず、実装段階になってから「このUIはどうなってるんですか?」とデザイナーに問いかけることが増えるなど、開発プロセス全体でコミュニケーションコストが大きくなってしまうリスクが生まれます。
このようなコミュニケーション不足や連携不足といった問題が発生するリスクを回避するため、「デザインはデザイナーだけが担うものではない」という意識を開発組織の中で根付かせていくことが必要です。
スタディストの場合、プロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニアの垣根を無くし、誰もが初期段階から課題解決に貢献できるように、プロジェクトの序盤でステークホルダーへのヒアリングや、デザインスプリントをメンバー全員で行うことを推奨しました。
このような活動を続けていくことで、デザインプロセスを開発組織全体で扱えるようになってきています。そしてそれをデザイナーが推進するための経験やスキルが磨かれてきました。
ここまでは積み上げ的な思考でデザイン組織の役割を考えることができたので、ある意味貢献範囲を決めることは容易でした。「まずは自分たちが成長する。そして、開発組織全体も良くしていく。」という方向で、2年間はまっすぐ進んできました。
一方で、それが当たり前にできるようになっていく中で、次に何を行うべきかが少し見えなくなってきます。
何に貢献できるのかを検証するために、デザイナーとしての影響範囲を少しずつ広げてみようと試行錯誤を始めますが、範囲が広く、一貫した活動になりません。
そこで、改めて組織としての貢献範囲を見直すことに取り組みました。ここまで積み上げてきた専門性を踏まえて、自分たちが貢献できそうで、かつ事業や組織のフェーズを一段上げられる部分がどこなのか?を見直します。
ここで、現在のロードマップ「デザインブースト」が生まれます。すでに存在していたデザイン組織としてのミッションに向けて、どのようなステップで登っていくのか?という形で言語化を行いました。
「デザインブースト」を改めて定義したことで、今自分たちは「Lv1: デザインチームをブースト」「Lv2: プロダクト開発をブースト」まではうまく実行できるようになってきていることがわかりました。
逆に、これからは「Lv3: 価値提供までのプロセスをブースト」することに取り組むことが必要なのだとわかったので、このような動きを実験的に増やしてみます。
この検証期間を経て、確信を得たため、プロダクトデザイングループを室に昇格し、本格的に全社のビジネスプロセスへの貢献を開始していきます。
価値提供までのプロセスをブーストするため、まずは組織体制を見直し「プロダクトデザイングループ」を「リサーチ&デザイン室」へと変更しました。
グループから、室へと昇格させて、より会社全体に影響しやすくしました。プロダクトデザイングループの時点では単一のプロダクトに紐づいていたので、管掌範囲も変わっています。
また、貢献すべき範囲がプロダクト開発がメインであることは変わりませんが、さらにビジネスプロセスへも広げています。
例えば、リサーチを通した課題の発見や、開発ロードマップ案件の優先度検討への情報提供、マーケから営業・CS活動におけるCXの改善のための情報提供やコンテンツ作りなど、プロダクトの機能開発に止まらない顧客への価値提供全体をリードしていけるように位置付けを見直しています。
貢献範囲はプロダクトだけではなく、顧客理解をもとにビジネスを推進していく役割です。なのでリサーチ&デザイン室という名称に変更しています。
また、このタイミングで私は、開発部の副部長の兼務を外れ、リサーチ&デザイン室の室長に専念することにしています。ここまでの活動を通して「デザインの領域に力を入れることでスタディストの成長を生むことができるだろう」という確信が得られていたので、さらに注力することにしました。
現在も「Lv3. 価値提供までのプロセスをブースト」に取り組んでいる最中ですが、案件に止まらず、ビジネスプロセス全体に価値を出す動きをいくつも行ってきました。
いくつかの事例はCocodaにもすでに掲載しています。 例えば、個社ごとのプロダクト活用例を資料化し、セールスの提案や、インサイドセールスの架電ヒアリング時に活用できるようにした「顧客解体新書」を作成しました。
また、CSが集めてきた要望の中で、開発ロードマップに乗っていないものもすぐに実装に繋げていく「ゴキゲン超特急」の仕組みを運用開始しました。このように、顧客理解からビジネスと開発を繋げていき、価値提供までのプロセスごと改善していく動きを増やしています。
ここまでの活動を通して、スタディストのデザイン組織に対して、会社全体から大きな信頼と期待を得られるようになってきました。
デザイン組織の役割は順調に拡大しています。プロダクトの機能開発の案件は当たり前に回すことができ、その上でビジネスプロセス改善にまで入っていける貢献範囲の広がりが実現できました。
つくった仕組みによるビジネス成果も多く生まれています。例えば、顧客解体新書は、フィールドセールスの提案時や顧客向けのセミナーやCS活動における資料として活用されています。またゴキゲン超特急では、1年で20個以上の改善をリリースすることが出来ています。
このような活動を通して、デザイン組織に所属するデザイナー各人としても、非常に働きがいを感じているようです。
例えば、毎月取っているWevoxのエンゲージメントスコアは3ヶ月連続Aランク(90点以上)ととても高く、これは深ぼると「デザインスキルにとどまらないチャレンジをできる環境」ということが影響しているようでした。
こうしてこの数年間を振り返ってみると、自分たちの状況は特別なものではなく、多くの組織に共通する要素が多いのではないでしょうか。
初めはケイパビリティも無いので、それを身につけるところから始める。その上で一定の成果が約束できるようになった時に、その役割を広げていけないかと模索していく。この登り方は多くのデザイン組織に転用可能なパターンだろうと思います。
一貫して、組織全体に対する貢献を増やすことを意識し続けてきたことで、等身大に、でも確実に、貢献範囲を広げていくことができています。「あのチームに人を増やすと、きっと良いことが起こる」という期待感を持ってもらうことができ、組織に対して投資が生まれ、実際に組織への所属人数も増えて行く予定です。
スタディストのリサーチ&デザイン室は、自分たちのミッションを「組織としての顧客理解を高めることでビジネス全体をブーストする」としていますが、もちろんこれ以外にも貢献可能な範囲があります。例えばマーケティングデザインや、ブランドデザインなどには意図的にまだ入り込んでいません。(ここにも将来的には、入っていくだろうと思っています)
組織や事業の注力によっては、コミュニケーションデザイン領域からアクションを始めることもあり得るだろうと思います。
スタディストでは、多様な顧客を含む複雑なドメインゆえに顧客理解が最も重要だと捉えていて、私自身が開発のバックグラウンドを強く持っていたからこそ「プロダクトデザイングループ」から始め、「リサーチ&デザイン室」へとつなげているのであり、これは我々だからこその意思決定でした。
私自身、6番目の社員ということや、開発組織全体をマネジメントしていたこともある立場ということもあって「デザインがこうあるべき」というスタンスではなく、「事業活動のボトルネックはどこか。」「課題を構造化したときに根本課題となっていることはなにか」」をはじめに考え、そのためにデザイン組織のあり方を定義していく思考を自然に行えているように思います。
狙う成果と、自分たちが持つケイパビリティを合わせてコントロールし、事業成長を生んで行く、このようなデザイン組織のマネジメントを引き続き進めていければと思います。