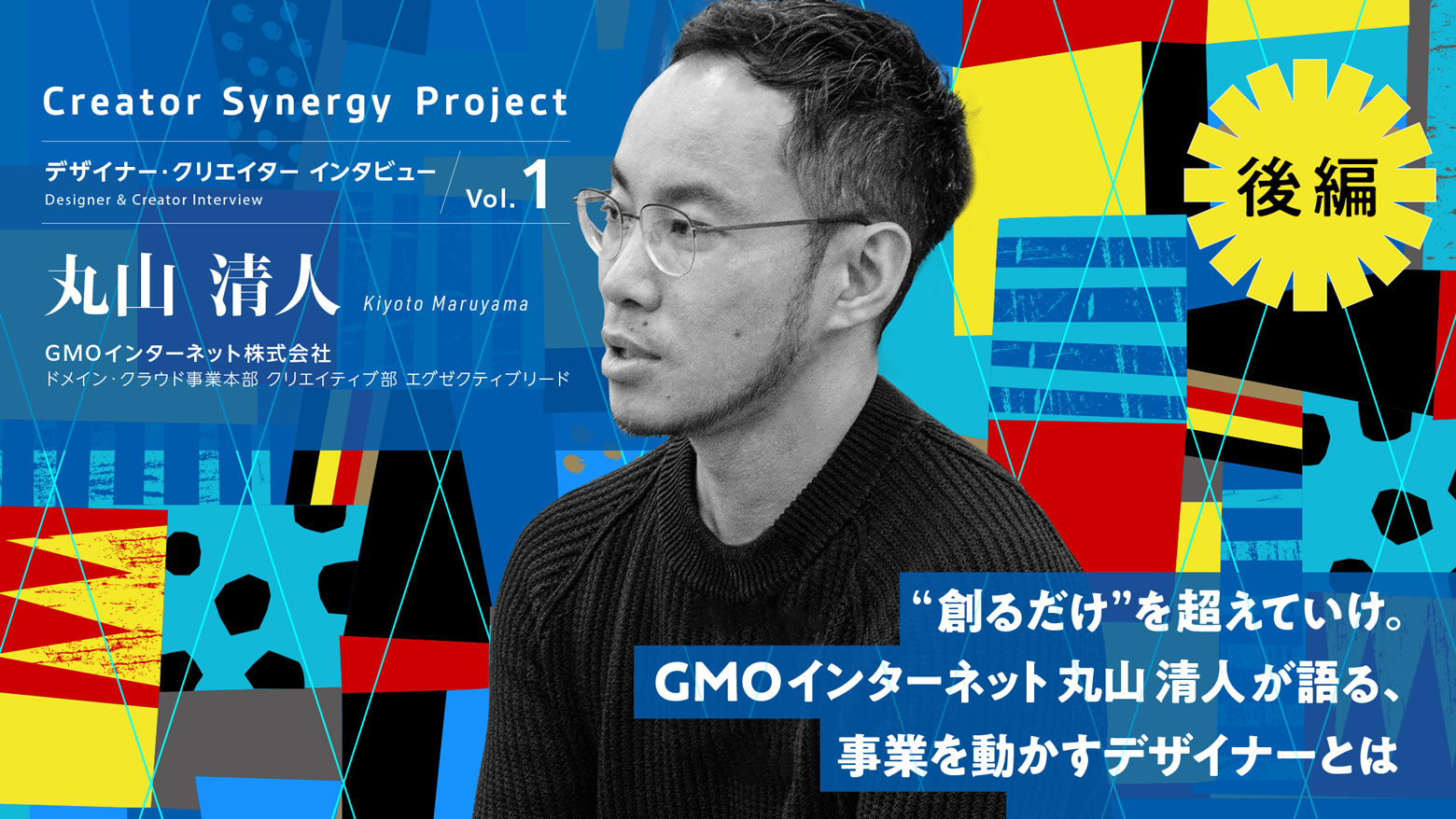社員700名のうち、約50名以上のクリエイターがいるGMOインターネット株式会社。
私は、クリエイターをまとめたクリエイティブ組織を束ねるエグゼクティブリードという立場で、社内のクリエイターの位置付けを変えていくために、この数年マネジメントの試行錯誤をしてきました。
私が入社した2013年当初は10名ほどだったクリエイターも、2025年4月現在では、50名を超える規模になりました。
このように大所帯になってきた組織のマネジメントで何より意識しているのは「組織の共通言語をつくり、まずは姿勢から変えていくこと」です。
拡大する組織で、どうすればクリエイターの貢献範囲を増やし、ビジネスを拡大していけるか。2017年ごろから少しずつ取り組んできた歩みを、等身大にまとめてみます。
私がGMOインターネットに入社した2013年当時から、クリエイティブ組織内の、特にデザイナーの立ち位置に問題意識を持っていました。
当時のGMOインターネットのクリエイターは、極端に言うと、エクセルでガチガチに固められた仕様書を渡され、それを絵にすることが役割になってしまっていました。私は、そこからの転換が必要と考え、2017年には初めてメンバー向けの勉強会を実施し、デザイン確認のフロー(承認フローと呼んでいます)を導入するなど、小さな変化を積み重ねてきました。
そして2018年にアシスタントマネージャーに就任してからは、部内全体のデザイン組織がどうあるべきかを形にする取り組みを、本格的に開始しました。さらに2020年には「クリエイター指標」を提言するなど、個人のスキルだけでなく組織としての成果を高める仕組みづくりに注力していきました。
そのような流れの中で2022年11月、部全体を変えるチャンスがやってきます。私がエグゼクティブリードに就任し、グループ全体の注力としても「クリエイティブNo.1」という方針が掲げられました。一方で、そのような追い風に対して、自分たちのデザイン組織はまだ追いついていないと感じることも増えてきました。
GMOインターネットグループ全体としての露出も増えていく中で、「自分たちGMOインターネットのクリエイティブ組織は、本当に実態が伴っているのだろうか」ということを考えるようになります。
真にクリエイティブNo.1を掲げるのならば、外向けのキラキラした取り組みだけでなく、実態を伴わせることが必要なはず。
2022年頃から企画段階から積極的に入り込み、事業やプロダクトの成長をリードしているクリエイターが増えているのも事実で、彼らの頑張りには大いに感謝しています。ただ一方で、クリエイターを「デザインツールが使える人」として捉える風土が残っているのも現状でした。GMOインターネットのクリエイティブ組織では、依然として、事業部から渡された依頼を請け負うだけの行動も多く見られていました。
本来あるべき姿は、クリエイターが企画から推進し、クリエイティブによって事業やビジネスを成長させていくことです。そうした理想像を組織全体で実現するため、マネジメントの立場から、数十名に拡大したクリエイティブ組織をさらに変えていこうと、試行錯誤を始めました。
私がこの数年間で最も意識したのは、「共通言語」をつくることでした。
管理職になる前は、自分自身が実行する中で影響を及ぼすようなプレースタイルが多かったのですが、50名を超える組織を動かすには、それだけでは足りません。
何が良いとされ、何を良しとしないのか。目指すべき方向に向けてクリエイター全員を動かしていくために、組織における共通言語をつくり基準値を引き上げることをマネジメントとして実行してきました。
大きく分けると、4つのアプローチで、GMOインターネットのクリエイティブ組織における共通言語を浸透させていきました。
1. 承認フローの設計
2. クリエイティブビジョン & ガイドラインの設定
3. スキルマップと、目標設定の仕組み化
4. 1on1やキープアップミーティングを通した地道な浸透
まず取り組んだのが、制作における承認フローの設計です。デザインや映像の制作物の部内確認を行う仕組みを、承認フローと呼んでいます。
それまでは、事業部などが「これでOK」と判断したものを、そのまま納品、公開をしていました。ところが、このやり方だと、クリエイター視点での品質基準が十分に担保されないまま進行してしまうリスクがあります。
そこで、デザインや動画のクオリティが一定以上であると部内で確認したうえで事業サイドへ提出するフローに切り替えることで、クリエイターが積極的に品質をコントロールし、他部署からの信頼度を高めることを狙いました。
また、現在では組織が大きくなったこともあり、私自身は新規サービスやリニューアル案件を中心に承認フローに関わっています。メンバーそれぞれが自分の担当領域でこの承認フローを回しているおかげで、組織全体として共通の品質基準を保ちつつ、スピード感のある制作を実現できるようになってきました。
2つ目に、クリエイティブ組織としての注力を毎年更新しながら設定する「クリエイティブビジョン & ガイドライン」という仕組みの運用をはじめました。
当時のGMOインターネットのクリエイティブ組織では、それぞれのクリエイターに向けて組織からの指針も示せておらず、個々人が何に注力すれば良いか分かっていない状態になっていました。
そこで、「クリエイティブビジョン & ガイドライン」という資料を作成し、全てのクリエイターの指針として共有しました。
この資料は、数年先に向けたクリエイティブ組織のロードマップとしての位置付けでつくっています。
構成としては、前年の振り返り、WHERE(目指す像)、WHY(存在理由)、HOW(実現方法)、WHAT(今年の行動目標)、WHO(スキルマップ)の6項目でつくられており、特に、WHATの項目は毎年内容を更新しながら運用しています。
毎年更新しているWHAT (その年の行動目標) については、全クリエイターがその年に行うべきスキルアップの行動を、具体的な指標も含めて明示しています。
これは要するに「ここに注力していれば、クリエイターとして事業に貢献できる」という指針であり、このように指針を示すことで、メンバーは迷いなく行動することができるようになります。
クリエイティブビジョン & ガイドラインで、目指すべき指針を示すだけでは、ただ言葉が一人歩きしているだけの状態になってしまいます。最も重要で、難しいのは、これを徹底的に浸透していくことです。
GMOインターネットのクリエイティブ組織の場合、「スキルマップ」と「目標設定」の連動によって、メンバーがクリエイティブビジョンを踏まえて行動できるように工夫しています。
まず、スキルマップについて。これは、クリエイティブビジョン&ガイドラインの中にも明示しており、GMOインターネットの一員としての「GMOイズム」の徹底から、クリエイターとして成長するための汎用的なスキル、それをさらに昇華させるスキル項目までを並べたものになっています。
このようなスキルマップはさまざまな組織で作成されているかと思いますが、私たちが工夫しているのは、これを目標設定に紐づけているところです。
具体的には、クリエイティブビジョン&ガイドラインの中で、WHAT (その年の行動目標) とつながるスキル項目を明示したKPIツリーを用意しています。
これにより、汎用的なスキルの中で、どこを今年特に伸ばすべきなのかをクリエイター全員が考えやすくなり、組織として一貫したスキル成熟を促すことができるようになります。
個々人の具体的な目標については割愛しますが、このような仕組みを運用し続けてきた結果、うまく組織の行動目標につながる個人目標を設定できている方が増えています。
これまでにまとめた仕組みを運用していれば、自然とクリエイターの姿勢が変わっていくかというと、そんな訳ではありません。
結局、地道な浸透を繰り返していくこと、語りかけていくことが徹底されなければ、文化が変わることはないだろうと思います。
私たちは1on1やキープアップミーティングを通して、日常的に何度も行動目標や、クリエイティブビジョン&ガイドラインを浸透させていくことを徹底してきました。
部長を含めた週次のキープアップミーティング(Mキープ)や、各チームのマネージャーやリーダーとはFriday Feed Forward(FFF)と称した時間を設けて隔週金曜で対話を重ねており、その中でクリエイティブビジョン&ガイドラインを踏まえた組織状況の共有やレビューも行っています。
さらにマネジメント陣から、各チームのメンバーに対してレビューが行われていき、その繰り返しによって地道に浸透が起こっているように思います。
このような、共通言語の定義と、地道な浸透を繰り返してきた結果として、今のGMOインターネットのクリエイティブ組織は少しずつ変化してきています。
例えば、冒頭にも記載したように、クリエイティブ組織に所属する方は50名を超え、大規模な組織となっています。
他にも、依頼を受けるだけでなく、企画の検討段階にクリエイターが参加するケースが見られるようになりました。
まだ一部のプロジェクトに限られますが、そういった案件ではスムーズに成果物を仕上げられたり、よりユーザビリティを重視できたりと、ポジティブな効果が実感され始めています。
また、スキルマップや目標設定を使うことで、メンバー各自が「自分の伸ばすべき領域」を以前より明確に認識できるようになりました。まだ全員が十分に活用できているわけではありませんが、積極的に取り組むメンバーからは「自分の目標をクリアに描けるようになり、成長しやすくなった」という声も出ています。
GMOインターネットという大きなインターネットインフラを提供する会社で、私たちクリエイターは、「依頼を待つだけ」の存在ではなく、「課題を解決できるクリエイター」に変わっていかなければ価値を発揮できません。
そのように考え、ここまでの取り組みで、少しずつクリエイティブ組織に「実態」を持たせ始められているように感じています。
とはいえ、実態として、GMOインターネットグループ全体で目指している「クリエイティブNo.1」という状態を満たせているかというと、もちろんまだまだ道半ばです。
例えば、サービスの一つひとつの体験が、本当にお客さまに求められるものになっているのか。クリエイティブの一つひとつが、本当に高品質なものになっているか。
大きな責任のある領域で、お客さまを含む皆さまから「GMOと言えば、クリエイティブ」と言ってもらえるように、地道な試行錯誤をこれからも続けていきます。
長い道のりですが、少しずつ変わっていく「GMOインターネットグループ」の歩みを、今後も等身大に公開していきます。
本事例の公開と同時に、GMOインターネットグループのテック・デザインブログでも私のインタビューが公開されています。ぜひこちらも合わせてご覧いただければ嬉しいです。