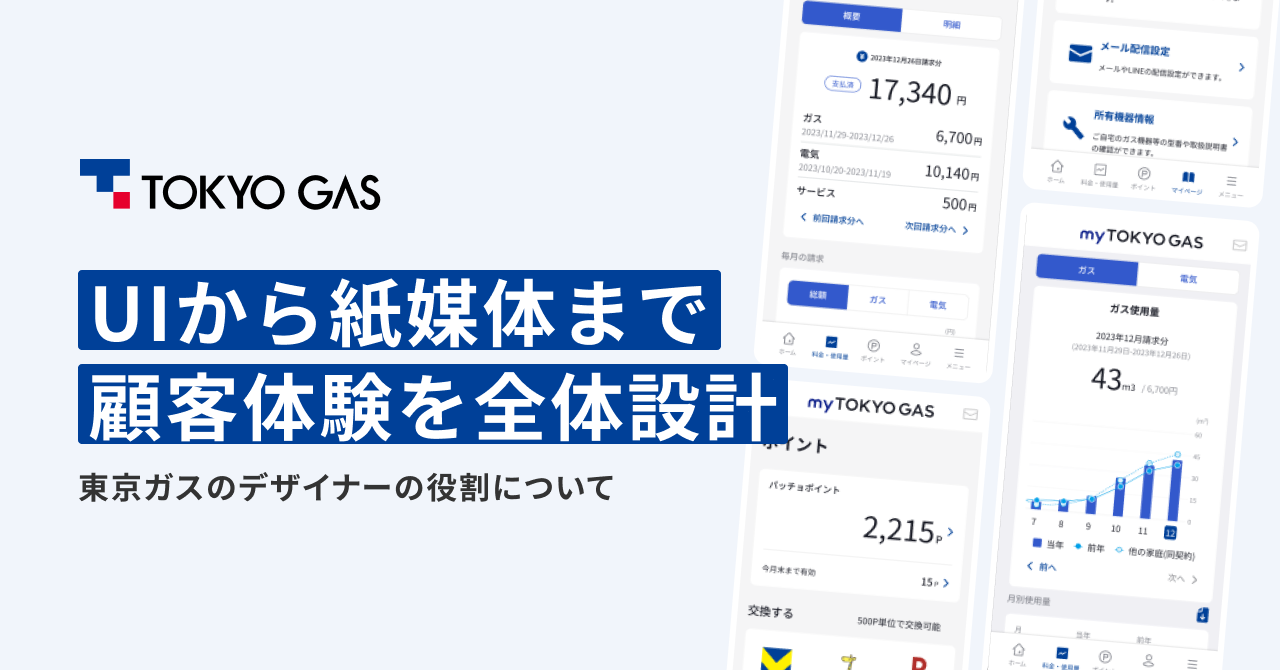東京ガス株式会社でUIUXデザインチームのリーダーをしている檜垣です。
東京ガスでは、2022年にWebプロダクト開発の内製化を目指して、インハウスの開発組織が立ち上がりました。同年、デザインチームも立ち上がり、現在は兼務者も含めて8名が所属しています。
東京ガスは現在3000名以上が所属する大規模な組織です。私は2022年3月に、東京ガスで初めてとなる、デザイナー経験者採用枠で入社しています。
今回は、なぜ東京ガスに内製のデザイナーが必要だと考えているのか、1人目デザイナー社員として取り組んできたか、を振り返りながらまとめてみます。
東京ガスは、前述の通り、3000名を超える大規模な企業です。(連結では約15000名) 2024年3月末時点で、提供しているガス・電気・サービスの延べ契約件数は1300万件を超えており、非常に多くのお客さまに価値をお届けしています。
現在、エネルギーの分散化・自由化などの市場の変化や、環境問題を受けた脱炭素化という大きな潮流など、世界全体でエネルギーの課題に向き合うことは必須項目となってきています。
1969年に日本で初めてLNG (液化天然ガス) の導入を行った東京ガスは、天然ガスを扱うリーディングカンパニーとして、2030年に向けた経営ビジョンの中で、「次世代のエネルギーシステムをリードする」ことを目指しています。
そのために、これまで培ってきた事業を活かしつつ、さらに新たな価値の創出に取り組むことは必要不可欠と考え、2021年のmyTOKYOGASのリニューアルをきっかけにデザイン内製について本格的に検討が始まっていきました。
その中で「やはり、事業と一体となって、中から推進する社員が必要だろう」とグループマネージャーの及川が考え、デザイナーやエンジニアの経験者採用を開始します。
私は、1人目のデザイナー社員として入社した後は、「myTOKYOGASの内製化」「受付フォームのリニューアル」「検針票ペーパーレス化」など既存東京ガス社員(東京ガスに新卒入社した、総合職出身の社員)のデザイン業務の支援なども行いながら、チーム化を推進してきました。
この数年間は、いわば「東京ガスの事業特性を踏まえたデザイナーの役割を見つける」ための期間でもあったと思います。
ここからは、実際の流れに沿って、入社以降の具体的に行ってきたことをまとめてみます。
まず、1人目のデザイナー社員として入社した1年目は、既存メンバーと協働して、社内にデザインの大切さを浸透することに重きをおきました。
ここで地道に1人でデザイン業務を頑張るのではなく、元々東京ガスの総合職出身の既存メンバーと一緒に、さまざまなプロジェクトに関わりながら、デザインの価値を社内に浸透していくように動いていきました。
地道に自分1人でデザイン業務を行うというよりも、社内の既存メンバーのデザイン業務を私がサポートしたり、協業のパートナーの方との関わり方をインプットしていくなど、社内のデザイン伴走パートナーとして関わっていきました。
デザインの活用方法が社内でも分かっていないタイミングなので、影響が大きそうで、新しい価値を生めそうなものには既存メンバーと一緒に入れるだけ入り込んでいきます。またデザイナーがいる方がプロジェクトがスムーズに進むなど、継続して一緒に業務したいと思われることを大事にしていました。
やることは無数にあり、1つのプロジェクトをやるだけでは内製化の学習を得るには足りません。
myTOKYOGASの内製化
受付フォームのリニューアル
検針票ペーパーレス化
省エネ行動を促す新規コンテンツの、企画検討とコンテンツ運用
などを同時並行で取り組んでいきつつそれぞれのプロジェクトで必要なデザインプロセスをチームで学習していくように進めました。
2年目は、チームの成熟を促しながらも、デザインチームから実績を出せるようなプロジェクトへの注力を強めていきます。
具体的には、前回もCocodaで事例を公開した「検針票のペーパーレス化・myTOKYOGASのリニューアル」のプロジェクトに2023年は注力。
検針票のペーパーレス化、myTOKYOGASのリニューアルにおいては、UIUXデザインチームから既存メンバーがデザイナー兼プロダクトオーナーとして入りプロジェクトを推進しつつ、私もデザイナーとして入りプロジェクトを進めます。
ペーパーレス化プロジェクトの全体的な顧客体験整理や、お客さまに対する周知物の検証・デザイン、myTOKYOGASのUI設計・テストなど、幅広く関わり、無事プロジェクトを完遂することができました。
エネルギーを扱う東京ガスの事業特性として、プロダクト開発だけに注力するのでは顧客価値を届けることはできず、業務オペレーションの把握や考慮、お客さまへのアナウンスなど、サービス全体を俯瞰し体験をデザインすることが求められます。
このプロジェクトを経て、東京ガスのデザイナーの役割も、UI設計などにとどまらない範囲を受け持つことが必要であることに確信を持ち始めます。
2023年秋ごろ、検針票のペーパーレス化プロジェクトがひと段落したタイミングで、東京ガス社内での専門人材計画にあわせて必要なデザイン人材の検討を開始します。
ここまでで分かっていた「UI設計に留まらない、サービス体験全体のデザイン」の必要性や、「2030年に向けた新しい価値の創造」というビジョンを踏まえて、「UXUIデザイナー」と「サービスデザイナー」という2つのロールを定義しました。
この2つのロールは、未来のエネルギーを扱うインフラ企業としてのより良いサービスの仕組みを描き、実現するための、具体のUI/UXをデザインしていく人材として期待されています。
職種としてはこの2ロールで定義していますが、関連するサービスのグラフィックデザインやインタビューの実施、UXリサーチ、ワークショップの設計など業務内容は多岐にわたります。
また2024年からは、myTOKYOGAS以外のUI/UXデザイン伴走支援も始め、東京ガスの機器交換や新事業ブランドでのデザイン支援も行っていきました。
現在も、事業の中心であるガス・電気事業と、周辺事業の両方に入り込んでいます。
ガス・電気事業では、会員登録時のUI改善、関連する設備ソリューション事業では、「東京ガスの機器交換」の立ち上げなどに取り組みました。
新規事業では、ソリューションブランド「IGNITURE」のデザインシステム検討、関連サービスのUXリサーチ支援も行いました。
このような組織構築のプロセスを経て、2025年9月時点では、リビング戦略部のデザイナーは、兼務も含めて8名が所属しています。
私が2022年に入社した時から比べると、デザインの重要性は少しずつ浸透してきたように思います。一方で、顧客体験向上と事業フェーズでのデザイン課題はまだまだ多くあります。
今回触れたプロジェクト以外にも、いくつものプロジェクトや、新規事業ブランドのデザイン伴走支援にも関わり出せています。
個人向け領域を貫くデザインシステム構築なども取り組んでおり、新しい顧客体験を考える課題も出てきました。
顧客体験を扱うサービスデザイン領域では、2月に水野さん、4月に片山さんが続けて入社し体制が強化され、サービスデザイン領域の期待も高まっています。
既存メンバーも成長し、そこに中途入社の社員が加わり、組織拡大に向けて動いていくフェーズ
冒頭にも述べた通り、東京ガスにおいて2030年に向けて「次世代のエネルギーシステム」をリードできる存在を目指しています。
そのためには、お客さまに最適な顧客体験やサービスを提供し続けることが大切だと考えています。
検針票のペーパーレス化や、myTOKYOGASのリニューアルなどに留まらず、デザイナーが顧客体験やサービスをデザインしていくためには、まだまだチームとしての拡大・成熟の余地は大きくあります。
プロダクトデザインも含めて、サービスデザインを牽引できる東京ガスのデザイン組織を、理想に向けて今後も推し進めていければと思います。