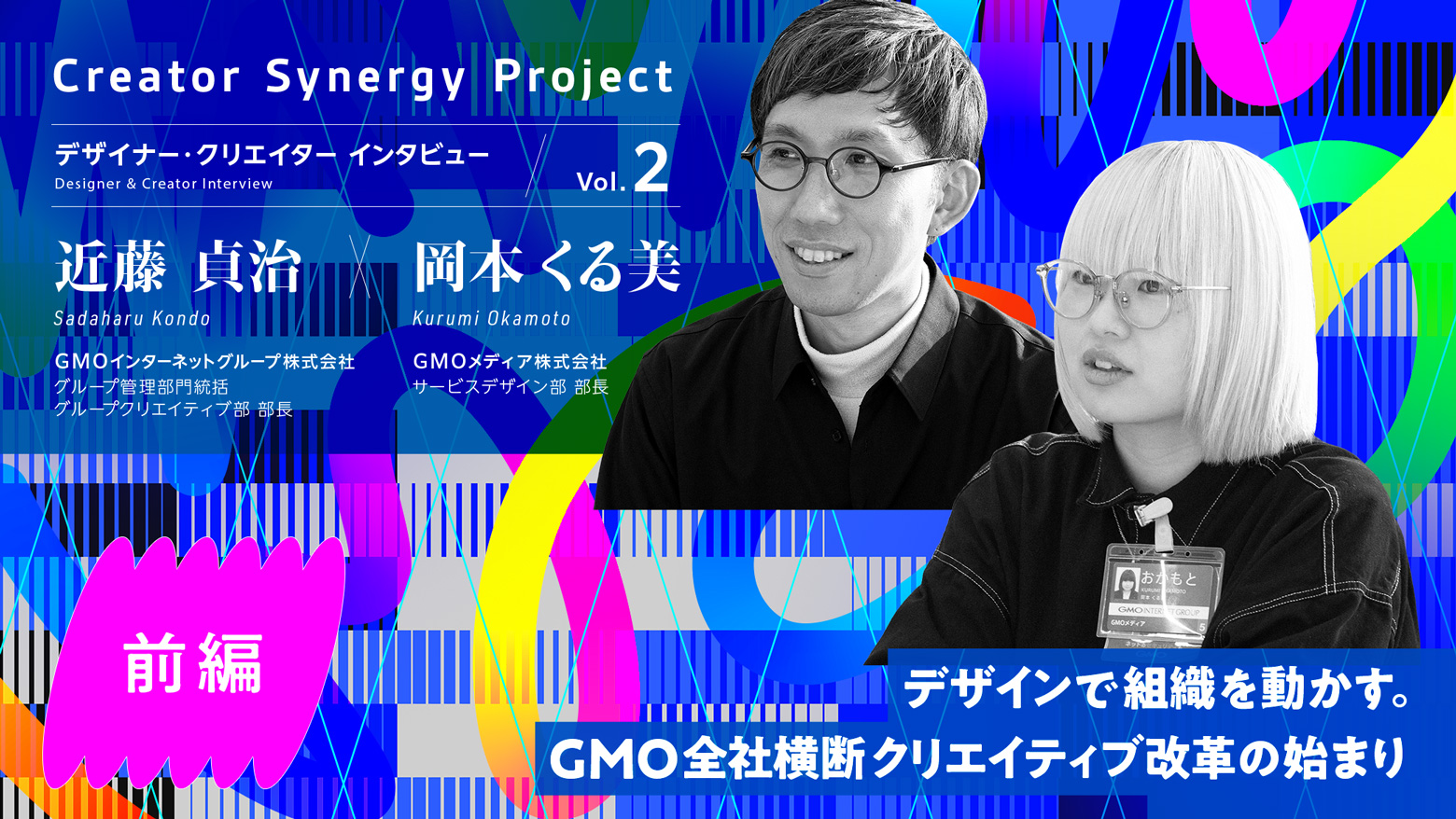GMOインターネットグループには、114社のグループ企業に多数のクリエイターが所属しています。
2023年にはグループ全体の社内スローガンとして「すべてのサービス・マーケティングを、圧倒的No.1クリエイティブ & UI/UXデザインに」という指針が掲げられ、これまでビジネスやエンジニアリングに注力してきたGMOインターネットグループとして、より一層デザインへの注力を強め始めています。
そして、実はこのようなスローガンを支えるグループ横断のデザイン活用推進の取り組みとして「クリエイターシナジー会議」という組織が、2022年から立ち上げられています。
「GMOインターネットグループ」は巨大な組織で、グループ企業ごとのデザイン活用度合いも、デザインに対する理解度も異なります。グループによっては、デザイナーがいなかったり、1名しかいないような組織もあります。このような環境で、いかにデザイン活用のファーストステップを踏んでいけば良いか。横断的な組織として取り組んできたデザイン活用推進のプロセスをまとめてみます。
“クリエイターシナジー会議” は、GMOインターネットグループのグループ企業から、各社のデザイン責任者たちが集まって組成された、横断組織です。
この取り組みのはじまりとしては、2022年後半に有志メンバーで「GMO全体のデザイン活用を何とか変えていけないか」と話し始めたのがきっかけでした。
そもそもGMOインターネットグループとは、多数のグループ会社が連なってできている巨大な企業グループです。
ただ、これらのグループ全体を統括するCDOのような存在がいるわけでもなく、デザイン活用度合いはグループ会社によってさまざまでした。CDOやデザイン責任者がいるグループ会社もあれば、デザイナーは不在、または1名のみで組織化されていない、といったグループ会社もありました。
このような状況を改善するために、当時GMOインターネットグループのグループ専務執行役員・CBOとしてグループ全体のブランド戦略を統括していた橋口が、デザイン活用が進んでいる数社のデザイン責任者に、「グループ全体としてデザイン活用を進めるために、何かできることはないか」と相談を持ちかけます。
それを受けて、GMOペパボの当時のデザイン責任者、GMOインサイトの執行役員が中心になり「クリエイターシナジー会議」を立ち上げました。
そこにGMOメディアのサービスデザイン部部長の岡本をはじめ、グループ各社のメンバーが有志として集まり、GMOインターネットグループ全体のデザイン活用の3カ年ロードマップを引いてみたりと、試行錯誤するところから活動は始まっています。
実験的な活動を続けていく中で、少しずつ体勢も拡大し、現在ではクリエイターシナジー会議には約30名の各グループ会社に所属しているデザイナーが参加しています。GMOインターネットグループ本体に所属し、代表の熊谷とも連携しやすい近藤が議長を務めています。
「会議」というと非公式なプロジェクトと思われるかもしれませんが、「クリエイターシナジー会議」は正式にGMOインターネットグループの組織図にも組み込まれている組織となっています。管掌役員として橋口が関わっており、GMOインターネットグループ全体に広げる活動を行いやすい土壌が整っています。
私たちが意識し続けているのは、グループ各社のそれぞれのデザイン活用度合いが違う中で、どんな状況であってもデザイン活用を推し進めやすくしていく「基準の底上げ」に取り組むことでした。
クリエイターシナジー会議発足時から組織を推進している岡本自身も、GMOメディア社でサービスデザイン部の部長を務めていますが、グループ企業内だけでデザイナーが動くのではなかなか全社を巻き込みづらい課題感を持っています。
グループを横断してつくられた組織である「クリエイターシナジー会議」が、各グループ内のデザイナー単体では行いづらいことを代わりに行うことで、各社のデザイナーがより社内で動きやすくなることを目指して活動してきました。つまり、トップダウンな組織というよりも、ボトムアップな活動をより行いやすくするためのサポートに徹しているのが「クリエイターシナジー会議」です。
具体的には、この数年間で、以下のような取り組みを行っています。
UXチェックリストのグループ全社浸透
デザイナーのプレゼンス向上施策
GMOインターネットグループ全体としてのデザイン発信強化
グループ企業単体では取りづらい大きな予算の獲得
特に効果的だった、目ぼしい取り組みについて今回は詳しくまとめてみます。
クリエイターシナジー会議のアウトプットの一つが「UXチェックリスト」です。
これは、グループ各社が、一つのサービスを対象にして、どの程度ユーザー体験を支える仕組みが整えられているかを測定することができるチェック項目をまとめた仕組みです。
クリエイターシナジー会議発足後、そもそも、「デザインを活用できているかどうか」という観点すら持てていないグループ企業も多くあるだろうと考えていました。
そこで、なかば強制的に自社のサービスと、競合サービスを比較してもらいつつ、具体的にどのくらいユーザー体験を踏まえたサービス設計が行われているのかを確かめてもらうことで、まずは問題意識を持ってもらいたいと考えてこの仕組みをつくっています。
具体的には、7つの観点を用意。それぞれ具体的に「できている/できていない」をジャッジしてもらい、結果として得点が出てくる仕様となっています。これを、各社の担当 (多くはデザイナー、いない場合は別の方) が社内の役員と一緒にチェックしてもらうような運用を指定しました。
このような取り組みは、実際に運用されることが重要ですが、GMOインターネットグループではグループ全体の社長や役員メンバーが集まるグループ幹部合同会というものがあり、ここでグループ本体として「これをやってください」と伝えることで、協力体制を強めるようにしました。
この取り組みで、サービスの品質が実際に上がるかどうかは遅効的なものなのですが、「うちもデザインに取り組まないと」という雰囲気をつくることに成功したように思います。
実際に「うちは大丈夫か?」と問題意識を代表や役員から投げかけられるデザイナーが生まれたり、UXチェックリストの項目をよくしていくためのチームを組成したグループ会社が出てきたりと、少しずつグループ各社でデザインに注力しなければという雰囲気が出てきました。
UXチェックリストの取り組みについては、GMO Developers Day 2023のセッションでも詳しく触れているので、そちらのアーカイブ動画もぜひ合わせてご覧ください。
(デザイナーからすると基本的な項目も多く、少し不安ではある内容だったのですが、グループ企業ごとに状況が違うため、そもそもデザインに目を向けてもらうための一歩目として、ここから始めたのは良かったのではないかと思います。)
UXチェックリストの取り組みを終えて、次は「グループ各社のデザイナー採用」の課題を解決しにいくこととします。
当時は、グループの中で、デザイン組織拡大に向けた採用の取り組みは、各社のデザイン責任者たちが自分で設計して、できる限りで行っていたような現状でした。
「もっとグループとしての強みを活かせないか」と考え、GMOインターネットグループ全体としてのデザイン面の発信を、クリエイターシナジー会議が働きかけ、予算を獲得し行っていくこととしました。
例えば
「Designship 2024」「Spectrum Tokyo Festival 2024」などにトップスポンサーとして参加
AI活用デザインコンテスト「GMO DESIGN AWARD」の開催
エンジニア向けカンファレンスとして開催していた「GMO Developers Day」に、クリエイター枠としてセッションを追加し、クリエイティブ制作にも関わっていく
など、グループ全体的な露出を強める活動を推進しています。
グループ全体的な露出を強めるためのイベント協賛・開催
「Designship 2024」のスポンサー時には、イベントに合わせて、グループ全体のデザイナーを押し出すCMも作成しました。
グループ単位ではどうしても大きな露出のための予算獲得などは難しくなりがちですが、グループ横断機能である「クリエイターシナジー会議」から、グループ本体の予算を捻出するよう働きかけることで、各社に負担をかけず露出機会を用意することができます。
このような機会を増加していくと、グループ各社の採用も行いやすくなっていくはず。「GMO=デザイン」という印象づくりは、横断機能として「クリエイターシナジー会議」が力をかけるべきポイントだと捉えています。
クリエイターシナジー会議発足から、約2年半が経過し、GMOインターネットグループとしてのクリエイティブ活用は少しずつ前進している現状です。
例えば、UXチェックリストの項目をすでにほとんどチェックできている企業が生まれていたり、GMOインターネットグループとしてクリエイターの活動を認知してもらえたりと、試行錯誤の結果が出始めているように思います。
「クリエイターシナジー会議」に発足から参加している、GMOメディア岡本の目線でも、GMOインターネットグループ全体に対しての貢献をしていくことで、グループ企業の一員としても非常に活動しやすくなったように思います。
例えばGMOメディアのデザイナーは、積極的に全社的な発信 (ex. Designshipのブース設計、GMO DESIGN AWARDのクリエイティブ設計) に関わるようにしています。
グループ内の活動に閉じないことで、幅広い経験を得ることができたり、「GMOメディアのデザイナーは、グループ全体に貢献できるほど力が育ってきている」というGMOメディア社内の雰囲気も醸成することができているように思います。
2年半前の立ち上げ時よりも、状況は改善されてきているように思いますが、逆にデザイン活用度合いが引き上げられたことで、新たな課題も生まれています。
例えば、UXチェックリストの基礎的な項目は満たせている企業の方からは「もっと発展的な取り組みはないか」「次は何をすれば良いか」などの声をいただいており、活用レベルが高まってきたグループ企業向けのアクション提示も行っていく必要が出てきています。
また、グループとしてのブランドづくり、デザインガイドラインのアップデートなど、少しずつ取り組んでいるもののまだまだ行い切れていない部分を、今後はよりクリエイターシナジー会議として推進していくことが必要だろうと考えています。
それぞれ異なるデザイン活用度合いのグループ企業にクリエイターの重要性を浸透していくことは、非常に骨の折れる取り組みです。ただ、誰かがやらなければこの状況は変わっていきません。
グループ企業に所属しているデザイナー・クリエイターの活動がとにかく風通しが良くなるように、ボトムアップな取り組みを支える横断組織として、今後もクリエイターシナジー会議から各社のデザイン活用をサポートしていきます。
本事例の公開と同時に、GMOインターネットグループのテック・デザインブログで、本事例の執筆者である岡本・近藤のインタビューが公開されています。ぜひこちらも合わせてご覧いただければ嬉しいです。