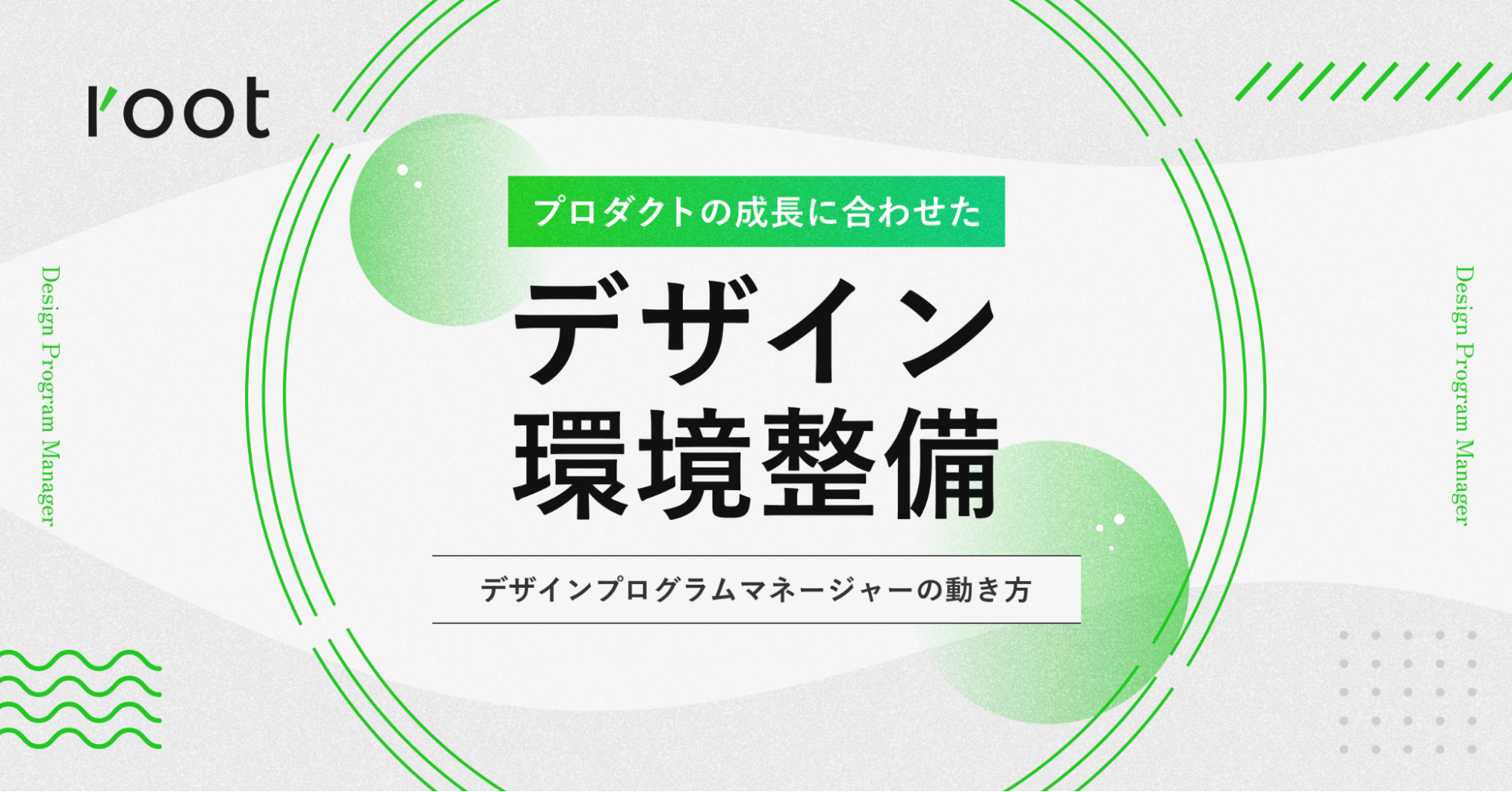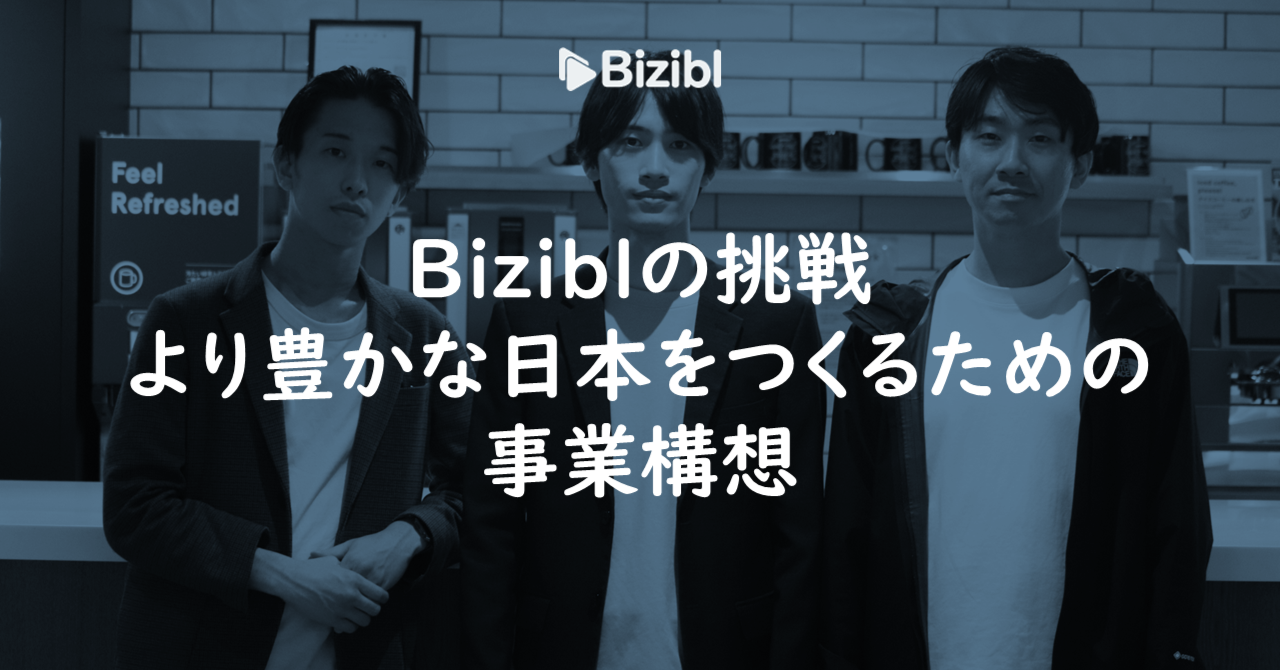rootは、事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。主に新規事業開発やスタートアップの成長支援をしています。私は、ルートでデザインプログラムマネージャー(以下DPM)として働いています。
rootでプロダクト開発を支援している「Bizibl (ビジブル)」のプロジェクトの中で、DPMとして、プロダクトデザイナーが十全に能力を発揮できるようにするための、デザイン環境の整備を行いました。
- なんでもやる期:負債の解消と、コミュニケーションの改善
- 生産性向上期:増えていく要望に答えられる体制に
- 計画期:より長いスパンの計画を担えるように
と進めていった
プロダクト開発の初期段階から、少しずつデザイン環境の整備に時間をかけていたことで、うまくプロジェクトを進行できるようになっています。どのように進めていったかまとめていきます。
私が参画した段階では、すでに主要な機能は作られてはいたものの、まだまだ出来ることが少ない状況。とにかく早く進めることが重要だったため、週ごとにやることを決めて開発を進めていました。
そこから、少しずつプロダクトの方向性が絞られ始め、その分つくりたい機能の複雑さも高まっていたため、1〜2週間スパンで開発の計画が必要になっていきます。
そんな中で、デザイン環境が少しずつボトルネックとなっていることを感じていました。
初期の開発の負債が溜まっており、開発の生産性が低い
複雑な要件が増えてきて、読み解きが難しい
仕様が複雑になってきたことで、コミュニケーションが取りづらくなっていた
そこで、DPMとして、今後の体制も見越したプロセスの整備を少しずつ行い始めることとします。
プロダクトの方向性が見えてきて、1〜2週間の計画を立てられるようになり、案件が複雑になってきたタイミングから、デザイン環境の整備に力を入れ始めます。
まずは、DPMといいつつ「必要なことはなんでもやる」意識で、問題になっていることを一つずつ解決していきました。
ユーザビリティの負債が溜まっていたため、ヒューリスティック評価を行い、最低限の課題を取り除いていきました。
要求がどんどん複雑になっていくタイミングだったので、これまでの負債は早めに解消しておくべきだと考えていました。
また、デザイナーのリソースは、より複雑な機能開発に割きたかったので、自分も手を動かしてユーザビリティの改善を行っていきます。
同時に、デザインプロセスでのコミュニケーションが課題になってきていました。
そこで、まずは問題意識を揃えるために、チームで何が問題になっているかを確認するワークショップを行いました。
ファウンダー・開発者らが集まって課題感を共有しあい、何がボトルネックになっているのかをすり合わせました。その結果、コミュニケーションの中で成果だけではなくプロセスの課題についても扱い始める空気感が生まれました。
徐々に目先の開発に対応できるようになってきて、さらにプロダクトが成長してきたことで、1ヶ月ごとに開発計画を引くような開発状況になってきました。
顧客からのフィードバックが多くなり、開発優先度の決定や、役割分担、依頼フローの整備など、生産性が課題となっていきます。
そこで、全体としてデザインがどう行われるかを整理するために、開発プロセス全体でどのように役割分担をするべきか、デザイナーはどこに注力するべきか、を図解して認識をすり合わせました。
営業やBizDevが探索やアイディエーションは担っていたため、それ以降のプロトタイピングやUI設計にデザイナーは注力することに
root側で整理をした上で、Biziblのメンバーにも見せたところ、「そうだよね」とすぐ合意することができました。
さらに、アジェンダレベルでの位置づけ確認もデザイナーと行っていきます。不要なコミュニケーションは削いでいき、生産性を高めていけるようにしています。
デザイナーは探索やアイディエーションのプロセスには関わらないと決めた上で「全部つくる」とはならないよう、要望回収フローを整理しました。
書き込む難易度を少しあげたことで、フィードバックへの解像度が高まった。また「どれもこれも開発しよう」とならないように。
また、複雑で大きめのチケットが切られることが増えてきたので、チケット全体を俯瞰できるようにして、管理体制をしっかりつくっていきました。
複雑な案件が増えてきたので、管理にも力を入れる
さらにプロダクトの成長が起こっていったことで、これまでプロダクトオーナーとして関わっていたファウンダーがプロダクトから離れていくことになり、権限移譲が必要となっていきました。
開発的にも、目先の開発については生産性高く安定して行えるようになっていたので、デザイナーからより主体的に「何をつくるのか」を計画することから関わっていけるようにしていくことを目指していきます。
プロダクトオーナーとして関わっていたファウンダーがプロダクトから離れることになったため、ファウンダーがいなくても全員がプロダクトの方向を考えられるようにする必要がありました。
なので、プロダクトをどうしていきたいのかを解像度高く認識するために、ファウンダーの花谷さんにヒアリングして共感マップを作成しました。
このワークには開発者も参加しました。同時にこのワーク全体を録画し、Biziblの営業・CSメンバーに向けても共有されました。
すでに作成されていたロードマップに対して、デザイナー目線でわからないことや、定義が曖昧に感じるところを経営陣にぶつけつつ、理解を改めて図解して目線を合わせていきました。
経営目線と合わせて、長いスパンでプロダクトの開発計画を担えるようにするために、このような経営目線とのsyncをかなり重視しています。
今回のプロセス改善を受けて、rootのデザイナーからもよりデザインしやすくなったという感想をもらっています。
チームでデザインの議論をする上で、成果だけではなく、プロセスなどのメタな領域や、未来を見据えてどうしていくべきかという話をするのが当たり前となってきました。
コミュニケーションの質も頻度も高まり、ブロッカーは即排除の姿勢が保たれています。わからないことも、共に悩むことが出来ています。
何を作るかだけではなく、どうあるべきかに対してチームが期待と責任を持ちながら協業できています。
rootでのDPMとしての関わり方をまとめてみました。
rootでは、プロダクトの成長のためにサービス開発にデザイナーとして入り込むことはもちろん、デザインプロセスの整備など、チームの成長につなげることを両輪で支援しています。
プロダクトだけにデザインスキルを使うのではなく、より良いデザイン環境を整備していくことで、プロダクトの成長を早めていくことができます。そして、そのような組織のスキルやワークフローを束ねていくのが、デザインプログラムマネージャー(DPM)という役割なのではないかと考えています。
今後も、rootらしく、プロダクトの成長に関わりながら、ボトムアップにプロセスも育てていくプロセスを磨いていきます。