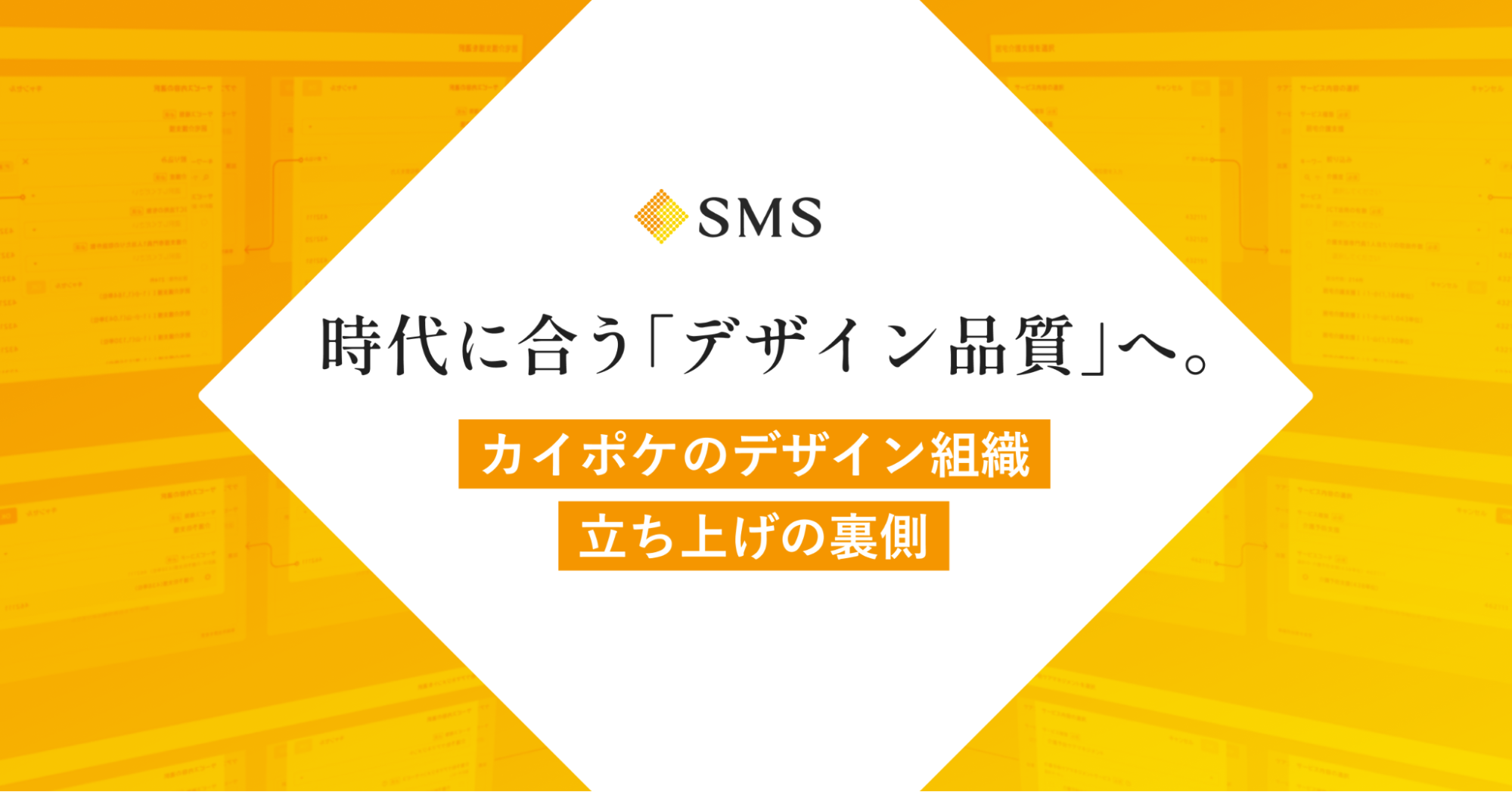エス・エム・エスのコミュニケーションデザインチームは、「ユーザーエクスペリエンスとクリエイティブなデザインでビジネス価値を高め、カイポケの成長をサポートする」ことをミッションに、「カイポケ」における広範なコミュニケーションデザイン業務を担っています。
以前、エス・エム・エスにおけるプロダクトデザイン領域を含むデザイン組織の立ち上げについての事例を公開しましたが、今回はコミュニケーションデザイン領域に焦点を当て、どのような変遷を経て役割を進化させてきたかをまとめたいと思います。
立ち上げから現在に至るまでは、大きく以下のような変遷を辿ってきました。3つのフェーズに整理していますが、必ずしも当初からこのように明確な道筋を描けていたわけではありません。
しかし、エス・エム・エスにおけるコミュニケーションデザインチームを、単なる制作部門にとどまらず、より上流の戦略部分に深く関与し、事業貢献できる組織へと進化させることを目指し、柔軟に変化を続けてきました。
ここからは、各フェーズで取り組んできた内容や、その際に意識していた点についてまとめていきます。
内製化を進めるにあたり、初期段階で特に重視したのは「実績をつくること」でした。
それまで、多くのデザインは外注で賄われていましたが、単にそれが社内のデザイナーに置き換わっただけでは、本質的な変化とは言えません。
当時は、各事業グループが施策ごとにバラバラにデザインを発注する状況で、内製でデザインの品質を統制できる体制が整っていませんでした。また、デザインの品質に対する要求にもばらつきがあり、納期や制作量が優先される場面も多くありました。
そのため、納期を守りながら、担当者の期待以上のアウトプットを提供し、事業部からの信頼を獲得すること。それによって、デザインの価値を示していくことが第一歩になると考えました。
その一例が「総合カタログの刷新」です。総合カタログは、カイポケというサービスの全体像を象徴的に伝える紙媒体の資料です。当時の刷新は、単なる資料の更新にとどまらず、カイポケのブランディングに関わる重要なプロジェクトでした。
従来のカタログでは、介護保険請求業務の効率化ソフトとしての側面が打ち出されていました。しかしその一方で、介護業界向けのコンサルティング支援や、現場で使用する備品の購買支援など、顧客のニーズに応じてサービスの支援領域が大きく広がっていました。
つまり、カイポケのサービスが「介護保険請求業務の効率化ソフト」から「介護/障害福祉の経営支援プラットフォーム」へと進化していました。こうしたサービスの実態に即して、総合カタログをはじめとするタッチポイントでの見せ方もアップデートしていく必要があったのです。
総合カタログの刷新は、カイポケ全体のブランディングに関わるため、事業責任者やPMをはじめ、多くのステークホルダーを巻き込む必要がありました。そうした中で、コンセプト設計からビジュアルデザインに至るまでを一貫して内製で推進し、当時のカイポケのコンセプトを的確に伝える総合カタログを完成させることができました。
また、LPやバナー、チラシといったプロモーション系の制作物についても、内製化を進める中で制作フローや品質維持に関するナレッジが着実に蓄積されていきました。
それに伴い、社内向けにデザインチームの認知を高めていくための取り組みも開始しました。その一つが、デザインチームの社内向けポートフォリオサイトの運用です。(※現在は、デザインチームの認知が広がったことにより、運用を終了しています)
携わった案件を随時登録していくことで、チームとしての実績を示すだけでなく、部門を横断して「どのような施策が行われてきたのか」を共有するための仕組みとしても機能していました。
事業の成長に伴い、マーケティンググループの人員が増えるにつれて、施策の数や規模も拡大していきました。そうした中でデザインチームは、課題発見から案件を推進していったり、制作フローの整備に注力していきました。
その一例が、「カイポケのサービスサイトリニューアル」です。
当時のサービスサイトは、SEO強化を重視することでサービスの認知拡大やリード獲得において大きな役割を果たしていました。一方で、コンテンツの拡充を優先してきた結果、サイト構造の複雑化や更新のしづらさ、ビジュアルトンマナのばらつき、UIデザインとコードの不整合といった課題が顕在化してきていました。
しかし、サイト構造の変更は数値面でネガティブな影響が出るリスクを伴うため、必要性を感じながらも、抜本的なリニューアルに踏み出しづらい状況が長く続いていたのです。
その状況の中で、「どうすれば改善できるか」をデザインチームが主体となって模索し始めました。
たとえば「この範囲であればデザインを変更してもSEOには影響しない」といったラインを、マーケチームと一緒に探りながら、少しずつ更新を重ねていきました。変更可能な範囲への理解が深まってからは、サイト構造の再整理、デザインやコーディングルールの整備といった、より根本的な改善にも踏み込んでいきました。
結果として、リニューアルを通じて数値面でも改善傾向が見られ、この実績を受けて他チームから「カイポケのようにサービスサイトもリニューアルしたい」といった相談も増えました。
社内での案件依頼が増加していくに伴って、制作フローを整備していきました。
具体的には、Slack上で依頼を起票するとスプレッドシートに自動連携され、そこからバックログ化するという仕組みを導入。これにより、案件量の可視化やリソース調整がしやすくなり、制作を進める上での連携もスムーズになりました。
施策単位で安定的に制作を担える状態となり、デザインチームへの信頼が高まるにつれて、マーケティング戦略への関与を強めていきました。これにより、企画段階からアウトプットの品質をさらに高めることにコミットできる状態を目指しました。
その象徴的な例が、カイポケにおける「バリュープロポジションの分析」の推進です。
プロジェクトの背景には、カイポケの大規模リニューアルに伴い、UIやビジュアルの方向性を定義するためのブランド基盤が必要であったことがあります。
従来、カイポケ全体のブランド定義は存在していなかったため、開発スケジュールとの兼ね合いから、UIデザインに直結するVI開発(プロダクト側)と、サービス全体を俯瞰するブランディング定義(コミュニケーションデザイン側)に分けて進行しました。今回の取り組みは後者にあたります。
ワークショップでは、介護・訪問看護・障害児支援といった事業部の各領域の識者と、以下のような議論を行い、ブランドターゲットのニーズとサービスの強みがどのように一致しているかを分析しました。
ブランドターゲットとセールスターゲットの明確化
ブランドターゲットのインサイト整理
提供できている・できていないベネフィットの抽出
顧客課題やジョブタスクの分解
サービスのコアバリューの言語化
その結果、サービスのコアバリューが社内で共有され、ブランドガイドラインやVIガイドラインが未整備の段階でも、部門横断で一貫した訴求や共通のイメージを持つことが可能となり、マーケティング施策の整合性向上にも寄与することができました。
立ち上げから数年で上記のような変遷を経ることで、コミュニケーションデザインチームとして成長を続けられてきました。
マーケティンググループのプロジェクト数が約4倍に増加
デザインチームの人員数が2倍以上へと拡大
また、さまざまなプロジェクトに携わる中で、定量・定性 両面から成果を上げることができるようになってきています。
このような組織としての成長を経て、今後さらに事業成長を支援するため、ケイパビリティの拡張を進めていきます。具体的には、以下のような項目を強化していこうと考えています。
- マーケティングデザインのさらなる進化
- 施策の効果測定を強化し、デザインの成果を定量的に示す仕組みを拡充
- ブランディングデザインへの拡張
- 「カイポケコネクト」のリブランディングに向けたデザイン戦略の確立
- プロダクトのUX/UIだけでなく、コミュニケーション設計を含めたブランド体験をデザイン
- デザイン組織のさらなる拡大
- 現在のマーケティングデザインの枠を超え、事業開発や新規事業のサービス設計に深く関与できるデザイン組織を目指す
- デザイナーの役割拡張
- デザイナー × ビジネス視点の強化
- 事業戦略と連携し、ビジネス視点でのデザイン提案を行うチームへ
改めて、エス・エム・エスのコミュニケーションデザインチームは、事業の成長とともにデザインの役割を進化させながら成長を続けてきました。
これからは、「デザインの力で事業成長を支援する」ことをより明確にし、マーケティングデザインからブランディングデザインへとケイパビリティを拡張していきたいと思っています。
試行錯誤の過程ではありますが、今後の活動にご期待ください。また、私たちのチャレンジにご興味を持たれた方は、ぜひ気軽にお声がけください。