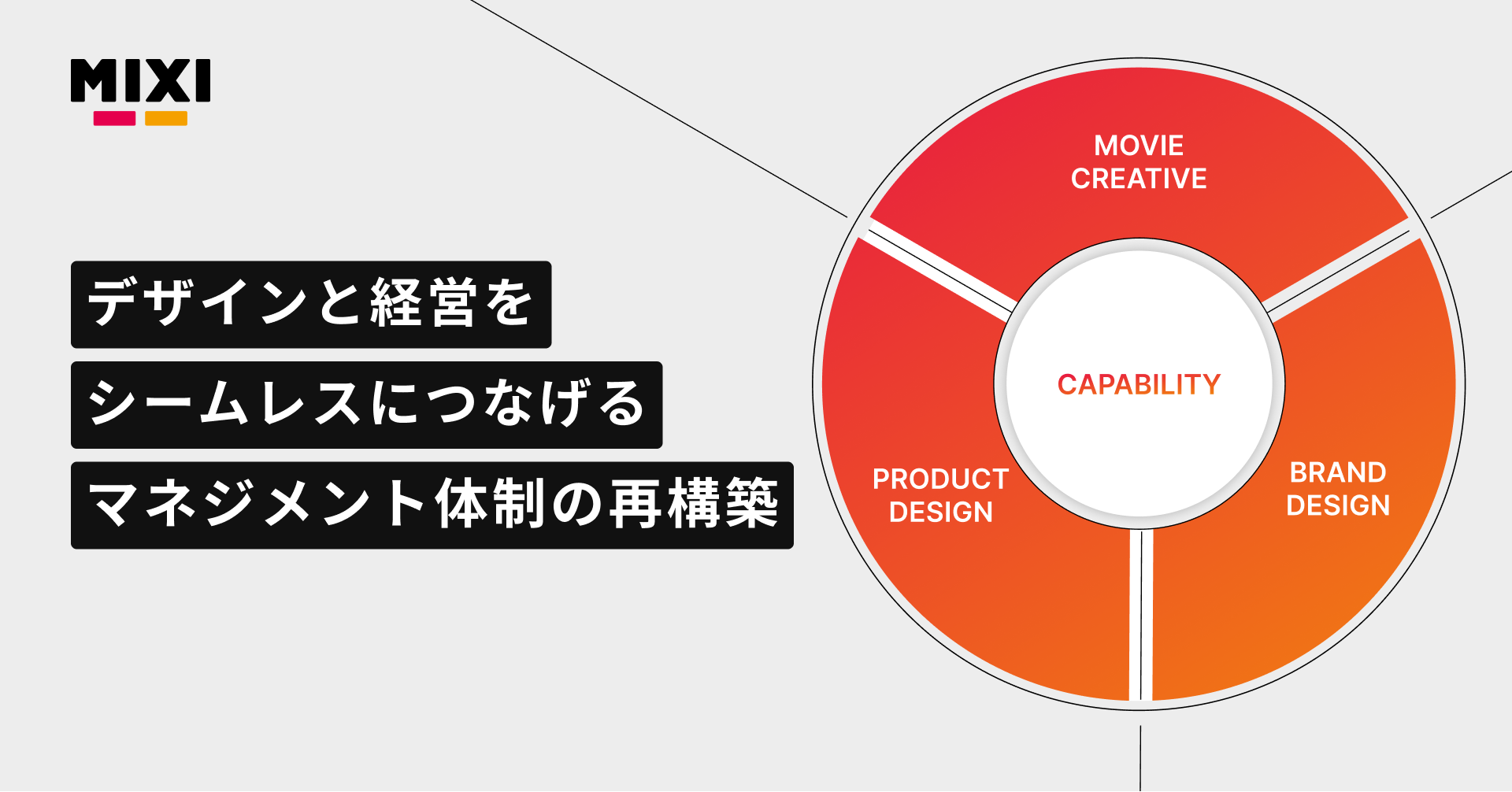2022年4月、MIXIデザイン本部に「プロダクトデザイン室」が設立されました。(部室立ち上げの背景については以下の事例をご覧ください。)
プロダクトデザイン室は、プロダクトの立ち上げから運用など、プロダクトデザインに関わる幅広い範囲を支援しているのが特徴で、さまざまな職域のメンバーが集まっています。
今回は、その中のグループである「エクスペリエンスデザイングループ(以下、EXD)」が担う役割やミッションについてまとめてみます。
EXDには、現在20〜30名のデザイン職が所属。「TIPSTAR」「家族アルバム みてね(以下、みてね)」「FC東京公式アプリ」「千葉ジェッツ公式アプリ」「Fansta」など、MIXIのさまざまなサービスに横断的に関わり、UI/UXの知見を活用してプロダクトづくりを推進しています。
さまざまな職域のメンバーが所属し、各事業と連携しながら、体験全体に幅広く関わっているのが特徴です。
あるべき理想の整理から、アプリのUI作成、サービスロゴやキービジュアル、LPの作成に至るまで、プロダクト立ち上げから運用までの体験設計 (UX) から一気通貫で支援しています。
デザイン本部がEXDを設立し、“体験設計 (=UX) ” をケイパビリティ(競争優位になる固有の強み) として確立しようとしているのには、大きく2つの背景があります。
MIXIはさまざまなプロダクト・事業を展開していますが、UI/UXの浸透についてはまだまだ伸びしろがあると認識しています。
各事業ではUXの重要性は感じられてはいるものの「具体的にどのようにUXを構築すれば良いのか」は整理されておらず、デザイン本部からのコミュニケーションも不足していたので「UXに対してデザイナーがどのように貢献してくれるのか」も明らかになっていませんでした。
EXDという組織をつくり、“UX” を軸にサービスの立ち上げから運用までを支援して実績をつくっていくことで、MIXI全体にUXの重要性が伝わり、各サービスがより良いユーザー体験を提供できるようになることを実現しようとしています。
もう一つの狙いは、複数の事業をまたぐ “UX” の知見を活用できるようにすることです。
MIXIの事業は、それぞれ事業フェーズや形態が異なります。ただ逆に、知見やプロセスは共通化できる部分もあります。
これまでは、デザイン本部の各デザイン職が事業に入り込んでいても、その中で知見の共有が行われているかどうかは、現場によってまちまちとなっていました。
EXDという組織があることで、これらの各事業の支援から得られた知見を、UXというケイパビリティに特化して集約・アセット化し、また他の事業へと展開していくことができるようになることを狙っています。
個々人の属人的な強さではなく、EXDというグループの強みに昇華・体系化していくことが、私たちが “組織” として存在する理由だと考えています。
このような目線を持つEXDは、2022年4月から現在までの3年間で、大きく2つのフェーズを経て立ち上がってきました。
・フェーズ1: 個人から、チームへ
・フェーズ2: UXによる実績を増やし、“存在感” を生む
2022年4月1日、プロダクト推進グループ (*EXDの旧称) が立ち上がりました。
グループはできたものの、初期はこれまでと変わらず「ソロプレーヤーの集まり」という雰囲気が残っていました。それぞれのメンバーは各自で事業に入り込む以外の活動はほとんど行っておらず、横断組織として何ができるのかは探り探りという状況です。
この段階で、まず組織としては「個人から、チームへ」というテーマに注力していきます。
始めに、前任のマネージャーによって、プロダクト推進グループ全体としてのロードマップが定義されました。
ここで、大きな仕事をしていくためにも、まずは個々人が小さく現場で信頼を積み重ねることに注力することを明示しています。
ただ「UXをケイパビリティとしたグループができました」と言うだけでは、特に信頼が生まれるわけもなく、事業の根幹となるようなコアな体験設計にまで入り込めるわけはありません。
「小さな案件から期待を超える」「そこで生まれた信頼から、他の案件も任せられる」「その積み上げで、プロダクト全体、事業全体...と期待が大きくなっていく」という流れをイメージして、まずは個々人が現場で期待をつくってくることを重視していました。
もう一つ、私たちが組織としてUXの機能を発揮していくためには、そもそもチームとしての繋がりをつくるところから強化する必要がありました。
日常的には、それぞれの担当プロダクト内で業務を進めているため、同じプロダクト推進グループに所属しているのに話したことがないような人も当時は多くいました。
その状況に対して、「メンバーが抱えているUX的な課題もしくは組織課題を話せるまでに関係値を上げる」ことを目標として「わくわくデザインセンター」というコミュニケーション施策を実施します。
まずはお互いを知ることが目的だったので、初期は直接的に案件に関わらないアジェンダも多く扱われています。
初期のアジェンダの例
404ページについて
女性専用車両について
カードゲームパック開封のワクワク感のUXについて
リファラルってほんとに起こるの?
ガチャの確定演出はなぜ虹色なのか?
etc…
お互いの人となりを知っていき、少しずつコミュニケーションが取りやすくなっていくにつれ、徐々に具体的な案件の相談など、実務に活きる知見交換のアジェンダが増えていきます。
後期のアジェンダの例
仕様書、ギリギリまで把握しない・しづらい問題
デザイナーがディレクターに求める期待を認識したい
業務の効率化ってみんな何してる?
デザイン修正指示、デザイン確認フロー、みんなどうしてますか?
プロジェクトへ早いタイミングでデザイナーがジョインするためにできることは?
etc…
このような動きを繰り返していったことで、個別に動いていたメンバーのスキルセットを、少しずつグループ全体で認識できるようになっていきました。
フェーズ1で、日々の案件支援を行いつつ、ロードマップで定義したように「個人としての信頼を積み上げてきたこと」、わくわくデザインセンターで「チームとしての連携を強めていったこと」によって、初めてチームとして大きな案件を進めていくことができるようになりました。
それが、以前Cocodaにも事例を掲載した「FANUP」のサービス設計です。
これまで個人として案件を推進することが多かったのですが、理想としていた「コア体験の設計から入り込む」ことができる大きな案件を相談され、リリースまで3ヶ月という短い期間ではありましたが、プロダクト推進グループが主体となって、全力で推進していきました。
「個人から、チームへ」というフェーズ1のテーマが実現でき、組織としてもこの案件が転機となりました。ここから、組織は次のフェーズへと移行していきます。
2024年10月、マネージャーの交代と同時に、組織の名称をExperience Design Group (EXD) と名称を改めます。
組織全体の所属人数も増えてきていたことから2つのグループに分割し、これまでもチームリーダーだった橋本、尾崎がそれぞれのグループのマネージャーとなります。
組織全体としては、さらにフェーズが進み「UXによる実績を増やす」ことが注力となっています。
UI制作のみ支援するような小さな関わりではなく、サービスのUX全体に影響した実績の増加にコミットしていくことで、会社全体で存在感のあるグループになっていくことを目指しています。
まず、組織としてのフェーズが変わったことを自覚できるよう、EXDへの名称変更と同時に、目標の再設定を行いました。
ここで重視したのは、抽象的なスローガンではなく、アクショナブルな目標になるようにすることです。ようやく「個人→チーム」への変化が実現できてきたこのタイミングで、「FANUP」の時のように「体験設計まで入り込み実績を出せたプロジェクト」を増やしていくことを目標にしました。
さらに、目標だけでは、どのようにそこまで登っていくのかが分かりづらいので、現在の状態と今期の目標、その後の「究極目標」がどう繋がっているのかを、グループメンバーと話し合いながら設定してみました。
(究極目標、という単語も、メンバーが取っ付きやすいようにあえてこのような言い方にしています。)
目標に掲げたように「FANUP」に加えて、全体の体験設計から大きく入れている案件を増やしていくことに取り組んでいます。
例えば、先日Cocodaに公開した「FC東京公式アプリ」の事例もその一つです。
EXDが体験設計から関わっている「FC東京公式アプリ」では、ファン・サポーターが必要な情報に円滑にアクセスできる情報設計や、ニーズに寄り添ったUXデザインをゼロから構築し、より便利で楽しいものに進化させることを目指しています。
例えば、スタジアムマップのリニューアルのプロジェクトでは、自分たちが理想とするマップ体験が実装されている事例が他にない中で、体験の構想を素早く可視化し、ユーザーごとの理想体験の流れを可視化するところからリードしました。
また、幅広い職能を持つEXDの特徴を活かして、アプリ内のUIだけでなく、スタジアムマップリニューアルをお知らせするLPも作成しました。
このように、体験に対して必要なものを幅広くつくっていく関わり方ができるのもEXDとして目指す像の一つです。
さらに、FC東京公式アプリでのスタジアムマップリニューアルの知見は、千葉ジェッツ公式アプリの設計にも活用しています。
事業をまたがるグループである強みをうまく活かすことができました。このような事例を今後も多く増やしていこうとしています。
案件の進め方だけでなく、組織づくりの施策についても、次のフェーズに入っています。
わくわくデザインセンターなど、これまでの組織的な取り組みは「まずは、チームの繋がりを強化する」という文脈が強くなっていました。
一方で、フェーズ2では「組織として “UX” の知見を資産化」し、再現性を生んでいくことを強く意識しています。
例えば、毎週の定例ではプロジェクトの進め方についての振り返りを実施しています。
進捗管理をする目的ではなく、プロセスを転用できる部分を組織全体で探り、学びを残していくような会話になるようにアジェンダを工夫しています。
また、各プロジェクトを進める上で有効な知見やフレームワークを「EXD_Storage」というナレッジデータベースにアセット化していくようにしています。
EXD_Storageには、これまでのプロジェクトで使われた提案資料や、合意形成のために有効なフレームワーク、知見など、いくつものアセットが集約されています。EXDのメンバーは、このアセットを使えばプロジェクトを進行しやすくなるように設計されています。
また、ワークフローから根本的に見直していく検証としてAI活用にも積極的に取り組んでいます。(メンバーによっては、業務の1/3の時間を割くくらいに重視)
プロセスを標準化・体系化することは、短期的な効率化だけでなく、長期的なスキルの向上、事業部との信頼構築、そしてビジネスの成長にも寄与すると考えます。
単なる作業の効率化ではなく、企業文化の形成やブランド価値の向上にもつながる重要なステップだと捉えて、このような領域にもEXDとして注力して取り組んでいます。
3年間の立ち上げ期間を経て、EXDのグループは3つに増え、所属するデザイン職の人数は20〜30名の規模になりました。スキルも多様な人が集まっていて、「FANUP」や「FC東京公式アプリ」の事例で述べたように、幅広い支援が可能になっています。
また、冒頭に記載したように「TIPSTAR」「みてね」「FC東京公式アプリ」「千葉ジェッツ公式アプリ」「Fansta」など、MIXIのさまざまなサービスに横断的に関わることができています。
実績を通して「MIXI全社にUXを浸透すること」も、少しずつ実現できてきました。例えば、FANUPや、FC東京公式アプリなど、EXDとして理想的な案件の推進を経て事業部からも期待が高まってきています。
まだまだ道半ばですが、EXDの現在地をまとめてみました。
EXDのマネージャーとしてこれから、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というMIXIのパーパスを各プロダクトに浸透していくことを実現していきたく思っています。
さまざまな形態や事業フェーズのサービスがある中で、「MIXIらしい体験づくり」を実現するのは非常に難しいことです。豊かなコミュニケーションをどのように体験設計に組み込んでいくのか、試行錯誤していく必要があります。
そのために、自分たちだけで知見を留めず、MIXIという組織全体に、EXDとして培っていく “UX” の知見を還元していくことが必要だと考えます。
最終的には、MIXIのすべてのサービスで「幸せな驚き」が実現されている状態を目掛け、EXDが先陣を切って、より良い体験づくりを実践していきます。