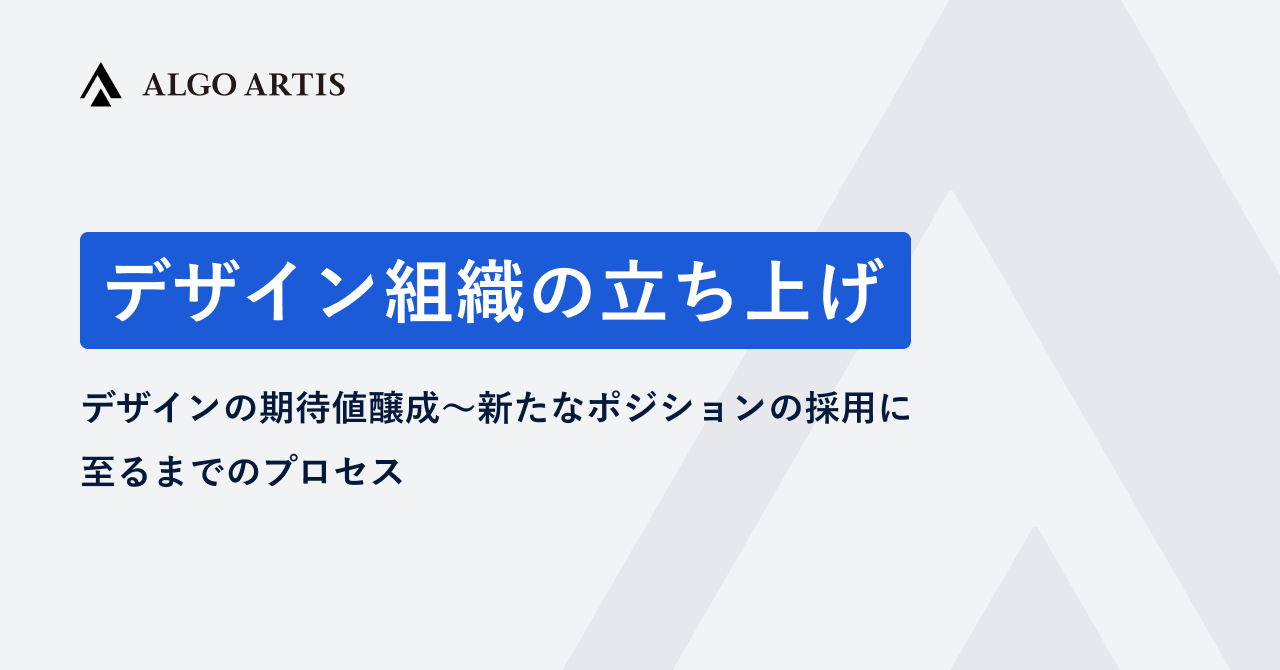ALGO ARTIS(アルゴ・アーティス)は、高度な最適化AI(アルゴリズム)を駆使した計画最適化ソリューション「Optium (オプティウム) 」を提供しています。
Optiumでは、電力会社の配船計画、化学メーカーの生産計画など、非常に複雑な業務に対してアルゴリズムを活用したシステムを提供することで業務の最適化を実現しています。
個社ごとに異なる複雑な業務を、解像度高く、いくつも理解していく必要があるため、事業運営難易度は非常に高いのがOptiumの特徴です。
ALGO ARTISのデザイン組織では、この難易度の高い事業運営を、ディスカバリー (リサーチ / 探索) の力で解決することに挑戦しています。これまでの1年間で、すでに以下のような成果をディスカバリーの力で生むことができました。
提案段階:難易度の高いプロジェクトの受注が決定
要件定義段階:プロジェクトのスコープを明確に定義し、顧客とスムーズに合意
今回はOptiumにおけるディスカバリーを通した事業成果のつくり方を、事例としてまとめてみようと思います。
「Optium」は、AIを活用した運用計画の最適化ソリューションを個社別にフルカスタマイズして提供する事業です。
非常に幅広い業種や業務に対してソリューションを提供しており、導入によって大きく生産性が高まるなど、計画業務の最適化に貢献できています。
「Optium」では、個社ごとに最適なアルゴリズム・UX・UIをフルカスタマイズしています。
例えば、一つの輸送という業務を取っても、どんな頻度で計画する必要があるか、対象業務の特性によって異なるので、この個社に必要な業務の理解から、UX設計までを一貫して提供します。さらに、体制としては、これら複数のプロジェクトを並行で進行させています。
「多様な業種」×「複雑な業務」×「同時進行するプロジェクト」という、難易度の高い事業です。
私が入社したタイミングで事業的な課題となっていたのは、個社ごとに違う「複雑な業務」を読み解く難易度が非常に高いことでした。
Optiumは、導入時にも業務理解を深めた上で提案を行い、導入していただき、導入後にもお客さまの業務を細かく理解した上で、必要なアルゴリズムを設計していきます。
つまり、業務理解を進めなければ、受注もできず、システム導入から結果に繋げるところまでを支援することもできないということ。Optiumにとって業務理解の仕組みは必要不可欠でした。
一方で、私が入社した当時は、この探索部分のアプローチは固まり切っていない状態でした。その結果として、システムの要件定義の難易度が高くなってしまっていました。
ここでALGO ARTISのデザイン組織として、ディスカバリーを活用した事業成果を段階的に生んでいくことに取り組み始めます。
プロダクトデザインという範囲に限定させず、力を発揮できそうな部分に実験的に入り込み、一つひとつ確実に最初の事業成果をつくっていきました、
具体的には「提案段階」と「要件定義段階」の2つのポイントで、ディスカバリーのアプローチからこれまでにはない変化を起こすことができました。
・ディスカバリー×提案フェーズ:難易度の高いプロジェクトを受注
・ディスカバリー×要件定義フェーズ:プロジェクトのスコープを絞り効率化 & 合意までの速度が向上
まず、受注前の提案段階での最初の成果の出し方についてです。Optiumにおいてこのプロセスが必要だったのは
複雑な業務であるため、受注前にも解像度の高いゴールイメージを持ってもらう必要がある
個社ごとに毎回異なる業務なのでキャッチアップコストも大きく、一般的なセールスプロセスでは受注に至らない
という課題が発生していたからです。
ここで起こすべきアウトカムは「難易度の高いプロジェクトを受注」することでした。
私が参画した当時のプロジェクトの状況は以下のようなものでした。これは多くのOptiumの提案段階のプロジェクトとも共通します。
どのような計画業務が実際に行われているのかが分かっておらず、提案の質を高められない
複雑な業務であるため、具体的なイメージが湧かないと相手も意思決定しづらい
ここで、ディスカバリーを活用して「業務理解を進めながら、見えるモノで提案できるように」することを試みました。
受注前のプロジェクトがまだ始まっていない段階では、システム設計に必要な情報をすべて集めることは難しい場合が多いと思います。それでも、ヒアリングした内容から「相手の業務を深く理解していること」「アルゴリズムによって何を改善できると嬉しいのか」を丁寧に整理することで、信頼をつくることはできます。
ここで大事なのは、相手の具体的な業務のシチュエーションに沿った提案をすることです。例えば、計画業務の頻度は年間なのか、毎日なのか。どのような部分に苦労しているのか。具体的にどのくらい負荷・コストがかかっているのか。読み取れる部分から、提案に必要な情報を整理します。
さらに、出来るだけ具体的に「これができると嬉しい」と感じてもらえるように、提案資料とモックアップに落とし込んでいきます。ここは「絶対にこれをつくる」ということではなく、「自分たちのことを理解してくれている信頼できるパートナー」という信頼をつくることを目的としています。
例えば以下のような観点を提案資料に落とし込んでいます。
受注を決めていただけるようなソリューションコンセプト (解決できることを一言で)
担当者の課題や苦労していること
現状の業務の流れ、どのくらい負荷がかかっているか
システム導入後に現状の運用方法とどう変わっていくのか
このように具体的で解像度の高いアウトプットを示したことで、お客さまからも「業務のことをよく分かってくれている」という安心感を得ていただくことができたのではないかと思います。結果、難易度の高いプロジェクトでしたが、スムーズに受注にまで至ることができました。
さらに、セールスメンバーからも「このように具体的な提案資料・モックアップがあったから受注がスムーズになった」と伝えてもらうことができました。
同時並行で、ディスカバリー×要件定義フェーズでの成果も狙いにいきました。Optiumにおいてこのプロセスが必要だったのは
個社ごとに全く異なる業務を毎回調査し、アルゴリズムに落とし込む/システムに落とし込む難易度が高い
開発以前に、要件定義が難航し、プロジェクトがうまく進まないことも
アルゴリズムで解決する難易度が高く、開発工数が膨れ上がってしまう
という課題が発生していたからです。
ここではリサーチと業務モデル化によって、プロジェクトスコープを明確に定義し、顧客との合意をスムーズに進めることに貢献しました。
対象としたプロジェクトでは、すでに提案・アルゴリズムの設計の段階は終わっており、個社の業務に最適なUI設計に進むタイミングでした。
一方で、状況として以下のような問題が発生していました。
ユーザー主語のドキュメントを用意できておらず、インターフェースの設計が難しい
実業務を行っている現場の画面を見たことがなかったため、システムが業務にフィットするかが検証しづらい
そこで「リサーチを通して、ユーザー主語の要件をまとめる」ことを試みました。
まず、より確実に業務で使われるシステムの要件がつくりやすくなるように、ユーザー主語のドキュメントを作成するプロセスをワークフローに組み込みました。
このドキュメントの項目を集めるために、カスタマージャーニーで業務の流れの仮説をまとめた上で、直接現地に訪問しました。実際に現場の担当の方に話を聞いたり、観察する中で業務理解を深めていくことで、想像ではなく実際に使われる確信を持ちたかったためです。
ここで得られたリアルなユーザーの声・情報をもとにして、ユーザーの業務に寄り添った画面設計を行います。
このようなアプローチを取った結果として、他プロジェクトと比べて、システムの要件が先方と合意するまでのスピードが格段に速くなりました。
また、プロジェクトのスコープを明確に定義し、アルゴリズムでつくるべき範囲を明確にしたことで、アルゴリズムエンジニアの生産性も向上し、システム納品までの期間も短縮することにつながる見込みです。
ALGO ARTISのデザイン組織では、このように難易度の高い事業運営を、ディスカバリー (リサーチ / 探索) の力で解決することに挑戦しています。改めて、この1年間で出せた成果は以下の2つです。
提案段階:難易度の高いプロジェクトの受注に貢献
要件定義段階:プロジェクトのスコープを明確に定義し、顧客とスムーズに合意
このような成果を受けて、全社的に「すべてのプロジェクトに探索アプローチを組み込めるようにしたい」という要望が起こっており、現在デザイン組織としてこの組織化を進めています。
私はディスカバリー (リサーチ・探索) の活用ポイントは幅広くあると思っています。
今回まとめたように、つくるものに合意する提案段階にも入れますし、要件定義段階にも入れます。プロダクトデザインにおいて重視されることが多いように思いますが、その他の事業領域にも積極的に入っていくべきです。
このように活用を広げていくポイントとしては、組織としてデザインの期待が具体的に醸成されていない時は、断らずに各所に入り込むことです。結果として、デザイナーと働くイメージもつけてもらえるし、期待も明確になります。
ALGO ARTISでは、このようなディスカバリーの文化をさらに多くのプロジェクトに取り入れていき、提案から要件定義、インターフェース設計と、全ての領域でユーザーのインサイトが活用されているような状況をつくっていくことを目指しています。
すでにALGO ARTISは、最初の成果を踏まえた組織化の段階へと進んでおり、これからの取り組みについても事例にまとめたので、こちらもぜひ合わせてご覧ください。