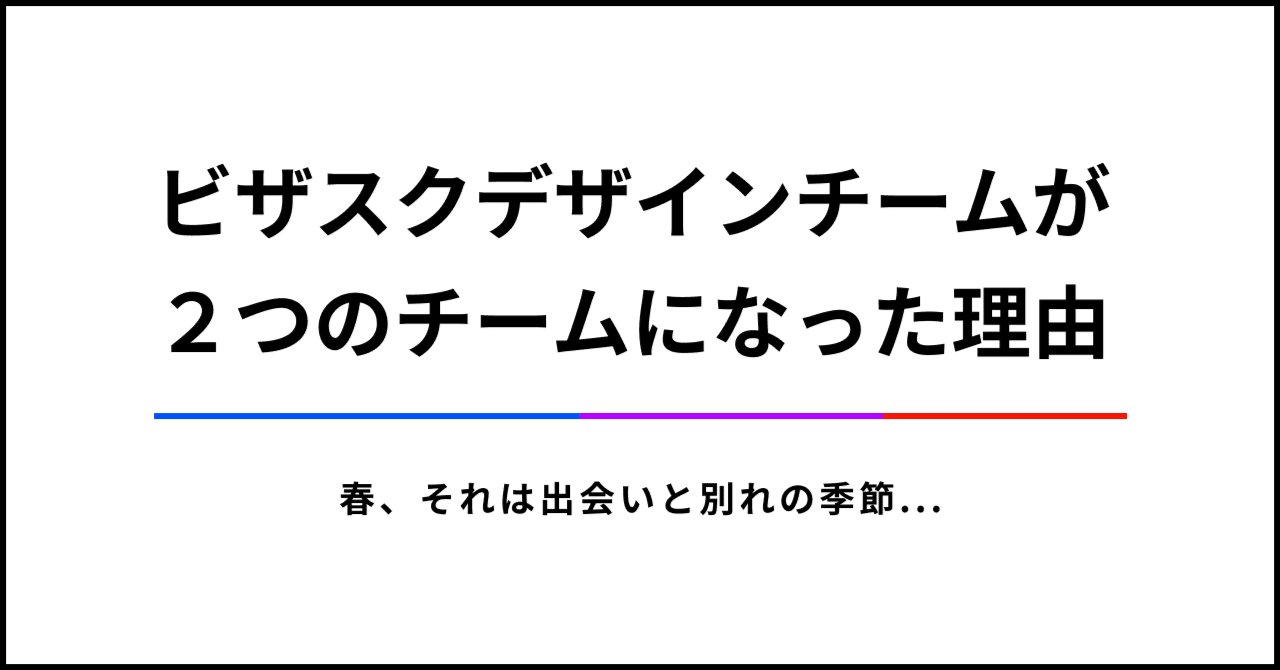ビザスクのコミュニケーションデザインチーム (以下、コムデチーム) は、現在3名のメンバーが在籍しています。
実は、コムデチームのリーダーは2024年1月から産育休中(おめでとうございます!)で、当初は同じCEO室で関わることも多かったPRチームリーダーがコムデチームリーダーを兼任、PRが事業部直下に移動後はCEO室長(金融/M&A畑)がコムデチームリーダーを兼任しており、デザイナー出身のリーダーがいない状況です。
メンター的役割、ピープルマネジメントの役割は、各兼任リーダーが果たしてくださってきたものの、デザイナーとしては「自分で判断し、自分で管理すること」が求められてきました。いわば「偶発的なティール組織」という感じでしょうか。
もちろん大変な面もありましたが、一方で、メンバー全員が「どうやったらリーダー不在でも回していけるのか」と考える良い作用も働き、この一年をなんとか乗り越えることができました。
この事例では、コムデチームが、どのように今までのやり方を工夫し、揺れ動く組織に最適化してきたかを、等身大に振り返っていきたいと思います。
2023年のブランドリニューアルをきっかけに、一つの組織であったデザインチームを、プロダクトデザインチームとコムデチームに分けることとしました。コムデチームとして「ブランド価値の向上と認知拡大を推し進めていく」という役割が明確化したためです。
他の企業でのコミュニケーションデザイナーの所属は独立した形を取るか、マーケティング部の中に置くことが多いと思いますが、ビザスクのコムデチームは、「企業価値の向上に資するあらゆる業務」をミッションとするCEO室に所属しています。
CEOの端羽さんとも近い距離で仕事をしているため、以下のような特徴を持っています。
機密性の高い情報を扱う
社外に情報を伝えるための手段(コーポレートサイトやIR資料)は、コムデチームが担当しているので、機密性の高い情報や新しい情報(ビジネスの方針など、新規や変更・改変)にアクセスの上、業務を行うこともあります。
迷いがあった時、代表に直接質問できる環境がある
週に一度のコムデチームのミーティングでは、1週間の進捗と共に、ブランド表現に関する迷いがある場合、代表である端羽さんに共有します。
制作物の中でビザスクのシンボルやブランドカラーの3色を使用する重要性について、端羽さんが熱く語ってくださったこともありました。端羽さんの想いのこめられたVisual Identityについて、改めて大切に考える機会となり、身が引き締まりました。
ビザスクのコムデチームは、ブランド価値の向上と認知拡大を目的に、各種プロモーションからイベント、採用、営業、IR領域と、社内外を対象とした幅広い制作に携わっています。
私たちは単に見た目を整える制作だけでなく、ディレクターやアートディレクターとしての役割も担い、時にはコピーライターやカメラマンとしての役割も求められます。
あらゆる媒体において、事業部担当者などの依頼者からヒアリングを行い、スケジュールや見積りから、課題や目的に合わせた最適なアウトプットまで提案、実現しています。
冒頭にも記載した通り育休中のリーダーが不在で相談できないので、他のデザイナーとの対話を増やしバランスよく進めることで、より良いアウトプットを目指しています。
各プロジェクトは、国内・海外拠点の事業部の担当者とデザイナーがチームを組んで進めています。
キックオフ時にクリエイティブブリーフを作成し、プロジェクトにおける課題や事業部の要望、制作目的、ターゲットに求める行動などを確認し、プロジェクトの方向性をすり合わせます。
担当デザイナーは、ヒアリングを通じて必要な情報を集め、支給された原稿や資料を元に構成や仕様を策定。その後、デザインの初稿を作成してプロジェクトチームに共有します。デザインに迷いがある場合は、他のデザイナーに相談したり、壁打ちをしてクオリティを上げていきます。
CEO室やコムデチームにはエンジニアがいないため、Web制作や運用においては、プロジェクトに関連するインフラやリリース体制、アカウント整備などについて、必要に応じて基盤チームやエンジニアリーダー、ITチームと連携して進めています。
また、印刷会社やWeb制作会社、展示会ブース装飾会社、オフィス設計デザイン会社など、さまざまなパートナー企業に対しても、依頼準備から検収、契約にまつわる稟議などの事務手続きまで自分たちで担当しています。
このような状況下で、ビザスクのコムデチームが工夫したことの一つが「品質管理」でした。
リーダーが産育休に入る前に残してくれた仕組み。それがビザスクの「クリエイティブブリーフ」と「クリエイティブチェック」の仕組みです。これまで、これらのチェックはリーダーが主に行っていました。リーダーが不在となってからは、プロジェクトメンバー間での相互レビューによって品質管理を行えるように体制を変更しています。
まず、クリエイティブブリーフを引き続き活用し、誰にでもプロジェクトの目的や内容が伝わるよう、より一層徹底しました。クリエイティブブリーフとは、目的やターゲットなどを整理した仕様書のことです。
クリエイティブブリーフを作成する目的は以下のように言語化しています。
プロジェクトに関わる全てのメンバーと目線・認識を合わせる
プロジェクトにおける課題や訴求を明確にする
メッセージの品質を上げる (コピーライティングや、デザイン)
優先順位を明確にした上で情報整理を行う
意図した通りにメッセージが伝わったり、課題の解決に寄与することができるか
制作の背景や目的などの必要な情報がブリーフにまとめられていることで、スムースなレビュー依頼に繋がっています。
クリエイティブブリーフでは、項目ごとに押さえるべき観点についても言語化しています。
例えば、制作物の目的である「新規リード獲得」や「サービスやブランドの認知向上」を実現するために、どのような方々に、どのようなメッセージを届けるか、その根拠は何かについて詳しく記載しています。
また、対象者の抱える課題感についても想定しています。
ビザスクのコムデチームにおけるクリエイティブブリーフは「事業部とともにつくるもの」として位置付けられています。
まず、事業部のプロジェクト担当者にすべての項目を記入してもらい、その後、キックオフミーティングでデザイナー側の視点を共有し、要件を整理していきます。
クリエイティブブリーフを使い始めた当初は、最初から必要な情報をすべて記入してもらうのが難しいこともありました。しかし、何度か繰り返すうちに、こちらからの質問も減り、目線合わせも容易になりました。
クリエイティブブリーフに基づいて制作を行った後の品質管理の仕組みが、クリエイティブチェック (承認) です。
ビザスクでは各制作物の品質管理を、各プロジェクトの担当デザイナーが担っています。この体制を維持するには「品質管理の基準が一定であること」が大切です。
このクリエイティブチェックはコムデリーダーとPRリーダーが行うことになっていましたが、リーダー育休中はデザイナーではないPRリーダー及びCEOの端羽さんが代行することになったため、重要になったのが、クリエイティブチェック前に担当外のデザイナーとデザイン面の目線合わせをする「デザインレビュー」です。
これは、コムデチーム内に出しているレビュー依頼です。コンテキストも確認しますが、見た目に気になる点がないか、ブランドパーソナリティに沿っているかを確認しています。デザイナーにしかできない品質管理は、このプロセスで自分たちで行うんだ、という一人一人の自覚が最大限発揮されます。
デザインレビューを経たものを次のクリエイティブチェックに回します。
その後、見た目、PR目線、ブランド目線で、社外に出して問題ない内容になっているか確認するための最終承認過程として、「クリエイティブチェック」を行います。(テンプレートに沿ったものや、既存のデザインを流用したものについては、クリエイティブチェックは不要と考えています。)
クリエイティブチェックでは、制作物を見ながら、必要な基準・品質を満たしているか、複数の項目に対してチェックリストを用いて確認していきます。
「ブランド維持」「デザイン」「目的達成」に大別され、この「目的達成」の項目で、先程説明したクリエイティブブリーフを参照し、目的と一貫した制作物になっているかどうかを見定めていきます。
チェック項目を満たしていないものがあれば、指摘と修正を行い、承認を得るまでこのサイクルを繰り返します。
直近では、デザインレビューは迷いがあった場合などの任意チェックとし、クリエイティブチェックについても、既存デザインの展開ではなく新規にデザインする制作物や、かなりチャレンジしたデザインなど、担当者自身がリーダーによるクリエイティブチェックが必要と思ったもの以外は、担当デザイナーと事業部責任者の両軸で最終承認を行う体制に変わりました。
担当デザイナーがそのままクリエイティブの最終リリースにも責任を持つ体制にすることで、品質に対するこだわりと責任感を、各自がより一層大切にするようになったと思います。
リーダー不在の中で、急遽必要となったのが「チームのあり方」を考えることでした。
例えば、業務委託や正社員の新規採用、会議でのファシリテーションの持ち回りなどにメンバー全員で取り組みました。
これまではリーダーが採用を統括しており、メンバーは必要に応じて面接に参加する形を取っていました。対して、リーダー不在中の新規採用の機会では、コムデチームのメンバー全員がどんな人と一緒に働きたいかを改めて考える必要が生まれます。
そこで、書類選考や面接なども自分たちで対応するために「一緒に働きたい人の人物像」「今後のチームの将来像」について、チーム内で議論の上、言語化・ドキュメント化をしています。
さらに、採用フローの見直しや、選考時に取り組んでもらう課題の設定なども行いました。
リーダーがいない状況だからこそ、メンバー全員がチームに対して責任を持つ意識が育てられたように思います。
ここまで、リーダー不在の状況で頑張ってきた、業務の進め方やチームづくりの工夫をまとめてきました。
もちろん、「リーダーの支えが欲しかったこと」も多々ありました。メンバー目線で、この1年間感じていたことを記しておきます。
==
CEO室の室長は制作に関与していないため、デザインやデザインチームに関するトピックの軽い相談などは、デザイナー間でのすり合わせを行い、その上で多忙な代表に相談することになります。デザイナー同士であれば話が早く進むこともあり、気軽に相談できるリーダーが身近にいることのありがたみを実感しました。
==
==
プロジェクトを俯瞰して見る人がいないので、プロジェクトの進行状況について相談したり、自分の取り組もうとしていることに問題ないのかを確認する術がありませんでした。だからこそ各々の判断力はついたのかもしれませんが、それを支持したり見守ってくれる存在がないことは不安でもありました。
==
リーダーが無事、育休から復帰してくれることを、チーム一同、心から待っています!
ビザスクの従業員数は、国内・海外の拠点をあわせて613名。(2025年1月現在)
上場、2021年の買収を期に、さらなる事業拡大に合わせて組織も大きく成長しています。プロジェクトが大きくなるにつれて、新しいメンバーや施策が増え、コミュニケーションデザイナーへの依頼や相談も多く寄せられるようになりました。
私たちのサービスはBtoBの無形商材です。このサービスを広めるためには、メッセージやデザイン手法を考える際に、言葉選びやデザインの難しさがあります。しかし、クライアントや事業部のエキスパート、経営者との綿密なコミュニケーションを通じて、デザイナーとしても事業への理解が日々深まっています。
これからも最適化を続け、より良いアウトプットを迅速にリリースしていけるよう努めたいと考えています。