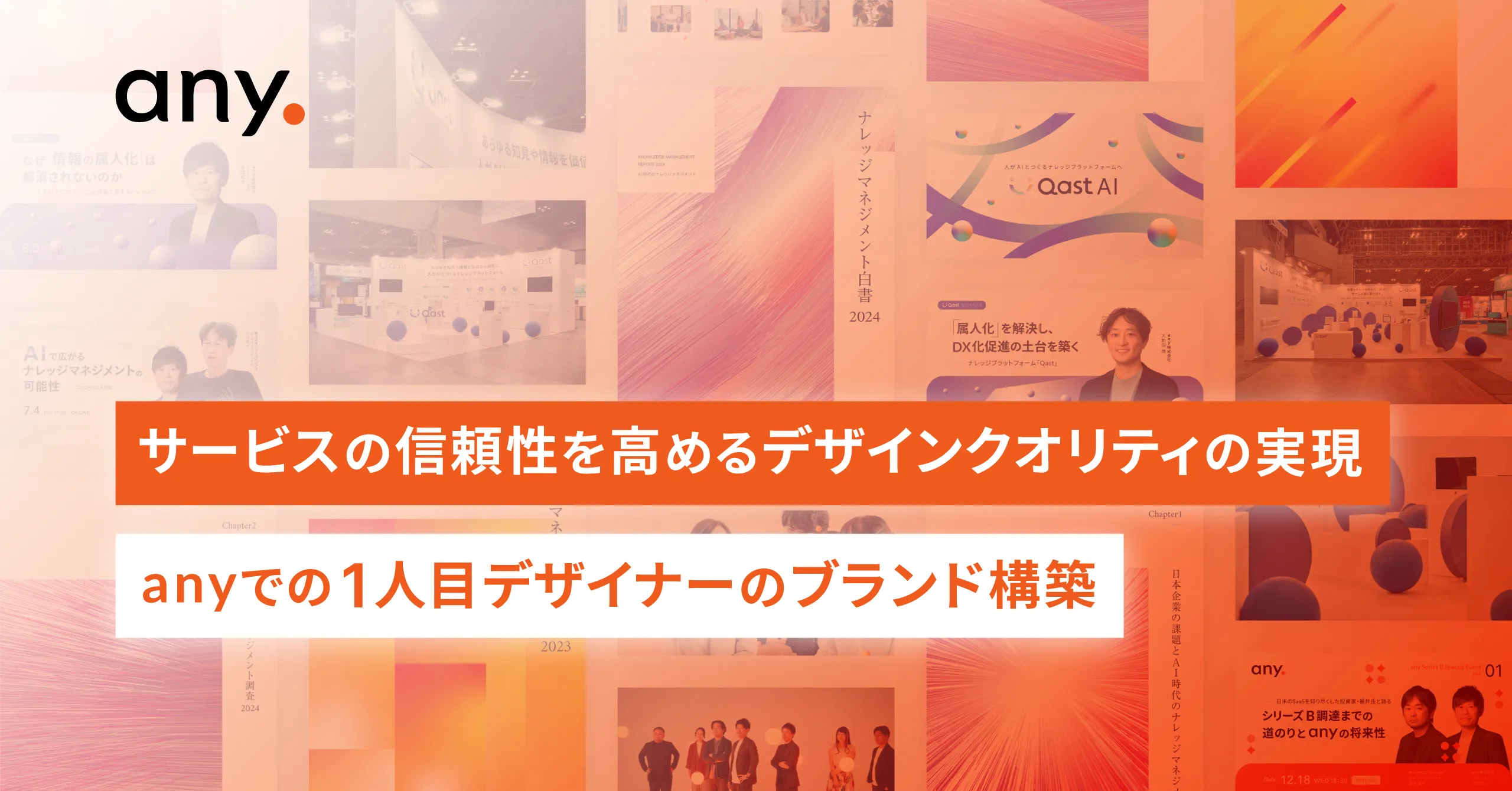ナレッジプラットフォーム「Qast」を運営するany株式会社で、デザインマネージャーを務めている三宅です。
私は、入社から現在までの約2年間で、サービスのリブランディング、レベニュー活動に必要な各種マテリアルのデザイン、プロダクトの新機能 / 既存機能のデザイン、プロダクトのUIリニューアルに向けた会議体の立ち上げと運営、コーポレートのリブランディングなど、様々な活動を展開してきました。(詳細な流れは、前回まとめた事例をご覧ください。)
今回はその中でも特に力を入れて取り組んでいる「展示会のブースデザイン」について詳しくまとめてみたいと思います。
一般的に、展示会ブースは専門の制作会社さんにプランを提案いただくケースがほとんどだと思いますが、弊社では基本的な平面図の制作、素材選定、寸法の検証、壁面グラフィックの制作などは社内でおこなっています。
(※詳細図面の制作や施工会社さんとの連携はパートナー企業さんにサポートいただいています。)
今年、2025年中には展示会戦略の大きなアップデートが予定されていることもあり、これまでの経験で蓄積してきたブースデザインのナレッジを一度まとめておければと思い、事例にしました。
【完全版】と銘打っている通り、出来る限り詳細にプロセスを公開しています。ぜひ、ブースデザインに取り組まれる際の参考にしていただけたらと思います。
まず前提になりますが、anyでは展示会をマーケティング戦略上の非常に重要な施策として位置付けています。
その背景として、施策を通しての受注数の多さ、そして数が多いだけでなく、最初の接点を作ってから受注に至るまでのスピードの早さ(リードタイムの短さ)という点でも他の施策に比べて際立った成果を挙げている、という分析結果があります。リードタイムについては、Webの資料請求などのインバウンド経由と比べ、展示会経由は約半分の期間という驚異的な短さで受注に至っています。
こうした理由から、anyでは会社全体で展示会に大きく力を注いでおり、その流れから、デザインにおいてもブースやノベルティ、各種配布資料といった展示会まわりのデザインに注力しています。
私は、展示会の成果に対してブースデザインが果たす役割・期待される効果は非常に大きいと考えています。具体的には、以下の8つが挙げられます。
「いかに多くの来場者を接客できるか」「通りやすい動線になっているか」といった機能的価値はもちろん、「ブースのしつらえで信頼性を感じさせることで、最初から安心感や説得力を持ってお話を聞いていただける」といった情緒的価値、その中間の「ブースの独自性によって印象に強く残り、後日連絡した際に思い出していただきやすくなる」といった効果が挙げられます。
特にQastの場合、社内情報を蓄積するサービスであること、全社や大規模な利用人数での導入を検討されるお客様を注力ターゲットとしていることから、「信頼性」を感じていただけるかどうかは非常に重要です。展示会においても、ブースに入る前から一定の信頼感を感じていただける状態を目指しており、その点でブースデザインが果たす役割は大きいと考えています。
SaaS企業では多くの場合、展示会ブースのデザインに取り組む際、社内でゼロからプランを設計するのではなく、制作会社さんなどのパートナー企業にデザインを依頼し、インハウスの立場からブランドのトンマナに沿ったディレクションを行っていく、という進め方をとる会社がほとんどではないかと思います。
ただ、anyの場合は、前述のように展示会が戦略上非常に重要な位置付けであることと、私自身が空間デザイン(建築・インテリアデザイン)を学んでいたというバックグラウンドがあることから、今のところ、基本的な空間プランについて社内で設計を行う体制をとっています。
このあたりは各社の戦略に応じて最適な体制があると思うので、「これが正解」というものは無いと思います。
社内で基本的なプランを設計することのメリットとしては、ブランドのトンマナを深く理解した上で、他の制作物との連動性まで意識してデザインができること、会社の事業計画や戦略、展示会の戦術をめぐる社内の会話といった大量の背景情報を踏まえた上で、それらを加味したデザインが初手からできること、などが挙げられます。最初のデザイン工数は膨らみますが、フォーマットが一度出来てしまったあとは、実はさほどデザイン工数をかけずに回すことも可能だったりします。
ではここからは実際のブースデザイン実務の流れをご紹介していきます。
まず、全体のフローとしてはこのような流れをたどります。
こうして書くと膨大なステップがあるように見えますが、一度型ができてしまえばあとは前回ベースで比較的スムーズに進められるところが多かったり、素材選定や服装のデザインなどは一度決めれば一定期間は変えないものなので、ステップを飛ばすことになります。
展示会ブースデザインの考え方については、各社が展開している製品の特性やターゲット層に応じて、独自の考え方や成功フレームがあると思うので、「これが正解」という意味でご紹介するわけではないことをご理解ください。また、主にSaaS企業のケースを想定して書いていることを前提にお読みいただければと思います。
まず出展を検討するにあたって、小間*位置を決定する議論に参加し、デザイン観点からコメントします。もちろん主体となるのはマーケティングチームですが、「この小間位置なら壁はどの面に立てることになりそうか」「この2つの候補なら、こちらの方がこういう理由でブースは作りやすい」といったように、造作・デザイン面での考慮ポイントを共有し、小間位置決定の判断材料の1つとします。
また、東京ビッグサイトや幕張メッセ、インテックス大阪など、これまでに何度も足を運んでいる会場では、実際に会場内を歩き回った経験から、「このあたりは奥まで進まずにお客様はこの角のところで曲がってしまうから、ここに出すと費用対効果が悪いのでは」「この会場だと、会場中央のこのあたりは人通りが多いが、会場の端の方は来場者の数がぐっと減ってしまう」といった、造作にとどまらない観点での意見を述べることもあります。
小間位置が決定し、いよいよブースデザインに入るというタイミングになったら、最初に正確な小間サイズ(縦何m x 横何mか)と、ブースを取り囲む通路の幅が何mかを確認します。可能であれば周辺の出展企業名も確認しますが、会期が近づいてこないと分からないことも多いです。
通路の幅の確認は非常に重要で、出展検討用の会場マップは紙面の都合もあって通路幅が正確に反映されていないことも多いので、マップで見ると広く見えたが現場に行ってみると思ったよりも狭かった、といったことがよく起こります。そのため、マップから通路幅を推測するよりも、正確な寸法を事務局に確認した方が安全と言えます。
特に通路幅が狭い場合、通路上でお客様と長い時間お話すると、他のお客様への声かけがしづらくなり、獲得リード数の低下につながってしまうため、そうしたことが起こらないような動線・空間設計を心がける必要があります。
小間の環境が確認できたら、いよいよ平面プランの作成に入ります。展示会ブースデザインの全フローの中でも、ここが一番重要なステップと言えると思います。
平面プランをいくつかの構成要素に分解し、それぞれにおける考慮ポイントをご紹介します。
体験 展示会を多数経験して、自社のブース内のオペレーションがしっかりと固まるまでは、空間としての動線設計などの前に、お客様にどんな気持ちになってほしいか、何をゴールにするか、最初に誰が声をかけ、そのあとお客様はどこに移動するか、といった全体的な「体験」の整理をすると良いと思います。
動線 会場全体の動線を意識し、どの方向からいらっしゃるお客様が多いかを考えてメインとなるコーナー(角)を定めたり(展示台の配置や壁の向きに影響します)、セミナースペースを設ける場合はブースのどのあたりに設けるか、セミナーが終わった後のお客様とメンバーの動きはどうなるか、バックルームの扉をどの通路側につけ、メンバーがどういう動きをたどってブースとバックルームを行き来するとよいか、などを考えたりします。
壁の配置 これはよく言われることでもありますが、壁は来場者の流れを考え、基本的に来場者が多くいらっしゃる方向に向くように壁を立てる、ということを意識して設計しています。
3分の1開放ルール 通路側に壁を立てる場合、最大でも小間と当該通路の接する長さの3分の1は開放しなければいけない(色々細かいルールはありますが、基本的には「壁」と見なされる構造物を立てることができない)、というルールを設定している展示会が多いです。壁を立てる場合には出展マニュアルでこの点を確認する必要があります。
セミナースペース ブース内でセミナーを行う会社も多いと思います。セミナースペースを設ける場合、そこで使用するモニターをどう設置するか、スピーカーはどこに取り付けるかといった造作観点、セミナーが終わった時にお客様にメンバーがどう話しかけ、お客様をどう誘導するかといったオペレーション・動線の観点での考慮ポイントが発生します。
バックルーム バックルームの広さは、同時に休憩に入るメンバーが一番多い時で何人いるか、から割り出すことが多いです。その他にも、例えば冬の展示会であればハンガーラックの台数をいつもより多めに見積もったり、参加メンバーが多いときは最終日にみんなの荷物を収納できるかどうかなどを考慮しながら最終的な広さを決めます。(展示会によっては会場の外に荷物置き専用のスペースをお借りできることもあります。)
展示台(デモ台)の配置 動線や壁の配置、声かけをするメンバーの配置を考えながら、デモ機を置く展示台の配置を決めていきます。この配置の仕方については各社の成功法則があるかと思いますが、個人的には「デモ機が通路から離れすぎていると少し入りにくいブースになるな」ということを感じています。ただ、オペレーションの狙い上、あえて通路から離すという設計をする場合もあると思うので、どれが正解、ということではないです。
自分の経験上の感覚ですが、デモ機を横並びに並べる場合、デモ機どうしの間隔は最低でも1100mmはあけないとお客様どうしがぶつかる可能性があり、できれば1500mmはあけておくと安心だと考えています。
また、ブース内で2人の人が無理なく自然にすれ違えるようにするには、できれば1800mmあけられると最適で、少なくとも1600mmくらいの幅が必要になります。ある程度小間サイズが大きくないと、すべての動線でここまでの幅を確保するのは難しいので、そういった時は1人ずつ通るのに必要な幅として800〜900mm、そこに展示台の前に立つお客様がいる場合は、1200mmあると1人が無理なく通れる幅になると思います。
図面で考えていたときの広さと実際会場で見た広さは全く違う(大抵、実際の方が狭く感じる)ので、図面では「ちょっと空きすぎでスペースがもったいないかな」と感じるくらいで実際はちょうど良い広さになっていることが多いです。
配線 意外と考慮から漏れがちなのが、デモ機やセミナースペースのモニターまで電源やLANケーブルをどう通すか、という観点です。床上げをしない限り、基本的に壁から離れたデモ機やモニターまではカーペット下に電源ケーブルやLANケーブルを這わせることになります。弊社でも会期途中で集客状況に応じて可動式のモニターを通路際に出そう、といった設計を考えたことがありましたが、その際に電源ケーブルはどうするか、という観点は結構見落としてしまいがちなので、留意する必要があります。
平面プランができた後、立面プランを作成します。立面では特に壁面グラフィックが什器などでどれくらい隠れそうかや、モニターや什器の高さと人の目線・手にとりやすい高さとのバランスなどを確認します。平面同様、人の添景イラストを入れることでよりイメージが湧きやすくなります。
弊社では、最近はブースのフォーマットが決まってきており、立面を書かなくてもおおよその空間イメージが想像できるため、このステップを省略することも多いです。
平面と同じく、立面プランを作成する際の考慮ポイントを簡単にご紹介します。
壁の高さ 上限3600mmの展示会が多いです(必ず出展マニュアルで確認が必要)。最近はあまりやっていませんが、以前は造作予算が大きくオーバーしている時などに、壁の高さを2700mmに下げるということをやっていた時期もあります(そうすることで壁をつくるための木工パネルの費用を圧縮)。会場の壁を背にする外周側の小間位置で8〜9小間くらいの広さがある場合、壁の高さを多少下げても、ブースの存在感がそこまで大きく薄れるということがないため、壁を下げるという選択肢をとることも可能になります。ただしすぐ真横に高さ3600mmの他社ブースが隣接するとやはり存在感は弱くなるのと、壁面グラフィックが什器に重なる割合が大きくなるというデメリットもあります。
展示台の高さ 各社好みがあると思いますが、QastのブースではH1000mmにしています。前かがみにならずに無理のない体勢でデモ画面を眺められる、ちょうど良い高さだと感じています。
モニターサイズ モニターサイズは空間の大きさ(小間サイズ)とのバランスで考えます。弊社では小間サイズに応じて55〜65inchの間で決めており、最近は60inchを使用することが多いです。モニターは壁にそのまま備え付ける(壁からはみ出す)取り付け方と壁の中に埋め込む方法の2つのやり方があります。埋め込みの方が開口部の木枠を作る必要があり、その分やや高額になります。
展示台(デモ台)
デモ機を置く台は木工で作ったオリジナルの什器を使用しています。丸テーブルなどのレンタル備品を使用するケースも多いかと思いますが、展示台をオリジナルにすることで空間の質が一気に高まるので、予算的に可能であればオリジナルで制作する方が良いと考えています。
今後仕様を変更する予定ですが、現在の展示台では、お客様に渡すためのパンフレットを収納したり、デモの後にお渡しするノベルティを入れておくための開口部が側面に設けられています。
横長什器(パンフレット台)
長手の通路際に設置する台。特に正確な呼び方はなく、「横長什器」と呼んでいます。以前はパンフレットやノベルティを天板(天井を向いた面の板のこと)の上に飾るように置いていました。最近はデモ機を1台置いています。主にメンバーやコンパニオンさんが来場者に配布するパンフレットのストック場所としての機能を果たしています。
電源を接続したりするときに台の中に入るための扉を「ケンドン扉」と呼び、この扉を開けて中に荷物を収納することも可能です。ケンドン扉は什器の側面から出っ張るように取り付けられることが一般的ですが、希望があれば側面から出っ張らないように作ることも可能です(「面(つら)合わせ」といいます)。
カタログラック(パンフレットラック)
カタログラックはレンタル備品やアクリルケースを使うことが一般的だと思いますが、空間のオリジナリティを高めるため、また動線設計の都合上、弊社では壁にオリジナルの棚を備えつけています。
受け棚は木工、押さえ棒は金物で制作。押さえ棒の高さはどのくらいがバランスが良いか、などを検証しながら制作しました。パンフレット表紙のメインコピーがギリギリ見える高さに設定しています。
モニュメント
Qastのブースの場合、丸を基調としたデザインであること、世界観的に圧迫感を感じるような構造物を置くのがそぐわないこと、メンバー間のアイコンタクトがオペレーション上重要であること、などの理由から、各社がコーナー部分によく置いているような背の高い構造物を置きづらいという事情があります。
そんな中でもブースをより印象づけるために、コーナー部分に独自にデザインしたモニュメントを置いています。透明のアクリルパネルを使うことでブースの中を見通すことができると同時に、圧迫感も軽減。厚さ10mmのしっかりとしたアクリルを使うことで質の高さを印象づけることもでき、全体で1250mmと背は低めですが、十分に存在感を発揮しています。
素材は毎回展示会のたびに考えるということはなく、デザイントンマナをリニューアルするタイミングで見直しを行っています。
Web上でカタログを確認することができるケースも多いですが、モニターで見る色と現物の色は多くの場合かなり異なるため、必ず現物サンプルを取り寄せて実際の色を確認したほうが安全かなと思います。
一般的に展示会でよく使われる素材をいくつかご紹介します。
「展示会でよく使われる素材」というのはだいたい各社共通しており、特殊な素材を使う場合は通常よりも実現方法の検証や現場での施工に時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで進める必要があります。
デモ機
弊社では2023年4月までは27inchのiMac、それ以降は21.5inchのiMacをデモ機として使用しています。2021年に発売が開始された24inchのiMacはそれまでと大きく筐体のデザインが変わり、角ばった印象が強くなったため、Qastの丸みのある空間とあまりマッチしないという理由で今のところは使用を避けています。ただ、新しいOSを使用する必要もあるため、切り替えの可能性も模索中です。
toB SaaSの場合、Windowsを使用されているお客様が多いのでデモ機はWindowsにすべきではという議論もあります。それも一理あるとは思うものの、空間の印象に与える影響を凌駕するほどのメリットがあるとは考えにくいと考え、今のところはMacを利用しています。
備品 バックルーム(休憩や荷物を置くためのスペース)で使用する長机やパイプ椅子、ハンガーラック等の備品類については一般的なレンタル備品を活用しています。このあたりは現場オペレーションと深く関わる部分であることや、お客様から直接見える場所ではないことから、基本的にはレベニューチームのメンバーに必要な備品の数などを見積もってもらっています。
ロゴサイン 文字の形に金属製のボックスを作りその中に照明を仕込むチャンネル文字、骨白アクリル(真っ白で透けないアクリル)などのアクリルの背面に照明を仕込んで壁を照らすことで浮かび上がらせる方法、壁のベニヤ板自体に直接ロゴの形をくりぬき乳半アクリルを通して照明を光らせる「抜き行灯(あんどん)」、スタイロフォームやカルプなどの素材でロゴを切り抜くスタイロ文字・カルプ文字などの形式があります。特にチャンネル文字やアクリル文字はかなり高価なので、基本的には使い回しを想定して作る必要があります。
LED投光器などの照明 壁上から照らす照明の適切な台数や配置の計画についてはパートナー企業さんの方で立案いただいています。あらかじめロゴや壁のグラフィックがちょうどよく照らされるように設計いただいていますが、影の落ち方や明るさが気になった際は現場で位置を調整いただくこともあります。
弊社の場合は社内で平面・立面(前述の通り最近は省略することも多いです)の基本プランを作成した後、それをもとに施工や部材の都合等を踏まえた詳細図面をパートナー企業さんに作成いただいています。
詳細図面をお送りいただいたら、当初の設計意図とずれてしまっている部分がないかなどを確認し、必要に応じて調整のやりとりをさせていただきます。
詳細図面と同時並行、または図面の後にお見積をいただき、予算と照らし合わせてデザイン調整の必要有無を判断します。展示会ごとに見積のデータを蓄積していき、経年で比較することで、壁面や出力グラフィックの面積と費用の関係についての感覚を掴んだり、各項目の費用がだいたいどれくらいかかるものなのかといった知識を蓄積していきます。
詳細図面と見積は1〜2回くらいの調整を経てFIXすることが多いです。
壁面コピー 一言でサービスの特徴を伝える、展示会ブースにおいて最も重要なグラフィック要素です。通路を歩いている来場者がぱっと見た瞬間のコンマ何秒で「どんなサービスか」を伝えなければならず、毎回頭を悩ませます。
マーケティングチームが主体となって考えますが、自分もディスカッションに参加し、主に文字数や改行、壁に入れたときのバランスといったデザイン観点、Qastの世界観や他の制作物との一貫性といったブランディング観点でコメントしています。
また、壁面コピーを考えるときは壁の立面の中に入れ込むと実際の見え方のイメージが湧きやすいため、立面の白紙の画像を用意して、そこに出てきた案をどんどん書き入れていくことで議論を活性化する、という役割も率先して担うようにしています。
導入企業ロゴ 展示会壁面グラフィックにおける鉄板の要素で、やはり強い訴求力を持ちます。ブース内に人が溢れていても通路から見えるよう、なるべく高い位置に掲示するのがベターと言えます。
図などのグラフィック要素 図や数字といったグラフィック要素はサービスの特徴を伝える情報であることはもちろんですが、アイキャッチとして見る人の足を止める効果も期待できます。
グラフィック出力かカッティングシートか 広範囲に細かい文字や図形が広がる部分はグラフィック出力、狭い範囲に一定の太さのある文字を入れたり、正確な色を出したいロゴなどの部分はカッティングシートで施工することが多いです。どちらも面積に対して費用が算出されます。
ノベルティ
ノベルティは大きく2つの役割を担うものと考えています。
- ブース誘引
- お客様をブースに誘引する際のフックの1つとして活用する。この用途の場合、「もらいたい・欲しい」と思うものであること、「それが何なのか」がぱっと見てわかること、の2つの要件を満たす必要があります。
- 検索誘引
- お客様にご自宅やオフィスまで持ち帰っていただき、そこで改めて見て気になって検索する、という行動に繋げる。この場合、「すぐに捨てられない」「しばらく手元に置いておきたくなる」ことが要件となります。
「重くないこと」は意外と重要な要件で、お客様に配布する際に何個も束にして抱えたり、補充する際に大量の数を運んだりするので、「重い」というのは致命的なマイナス要素になります(弊社も失敗したことがあります)。
モノや作り方にもよりますが、「基本的にノベルティの納期は長いものが多い」と考えていた方が安全です。2週間だと間に合わないものが多く、少なくとも3週間は見ておいた方がよいでしょう。
パンフレット・チラシ
パンフレットは既存のものをベースに、毎回の展示会ごとに情報の更新の必要性についてマーケティングチームと会話し、必要があれば更新作業を行います。残部数の管理などは展示会のプロジェクトマネジメントを行うメンバーが担ってくれており、新たに発注すべき部数が決まったらデザイン側で入稿を行います。
また、業界特化型の展示会に参加するときなどは、パンフレットがホリゾンタルな(業界を絞らない)内容になっているため、より対象の業界に刺さる内容で構成したA4両面のチラシを制作し、パンフレットと一緒に配布しています。
商談資料
ブース内商談でお見せする資料スライドのデザインも、毎回ではないですが、展示会向けに新たに作られたスライドがあった場合や、セミナーブース(会場の一角に設けられ、招待されたゲストが登壇したり、出展企業がセミナーを開催したりする)でセミナーを開催する際は手がけることがあります。
メンバーの役割によって3種類の服装を設定しています。
最初に通路上でお客様にお声がけするメンバーは白Tシャツ(秋冬はその上に白パーカー)、立ち止まってくださったお客様に話しかけ、Qastの具体的な説明と課題をヒアリングするメンバーは黒ポロシャツ(秋冬はその上にグレーパーカー)、より深くQastに興味を持ってくださったお客様に対してデモやユースケースのご紹介をして、後日商談のお約束をするメンバーは白Tシャツの上にジャケット、といった具合です。
最初の接点は明るい印象から入れるように白く、最後はしっかりとした信頼を感じていただけるように黒く、その間はグレーと、お客様の体験の流れに応じて色を設計しています。
一般的には施工が終わるタイミングの会期前日の夕方に現場確認に行く出展企業が多いと聞いていますが、弊社ではもう少し早く、昼過ぎ頃に現場に向かい、図面と異なる部分や汚れなどが目立つ箇所がないかを確認したり、照明や展示台の位置などで調整できる部分については最終調整を行ったりしています。
職人の方々は1つの展示会で複数社のブースを並行して施工されているので、限られた時間の中でご協力いただく必要があり、調整にご協力いただけた際にしっかりと感謝を伝えるなど、良いブースを作るためにはコミュニケーションが重要になります。また、調整が実現可能かどうかを相談する時にいただく専門的な見地からの意見やアドバイスは、その後ブースを設計する際の貴重な知識・情報になります。
毎回ではないですが、IT WEEKやDX EXPOなどの大型展示会ではフォトグラファーの方に竣工写真を撮影いただくこともあります。自分たちがスマホで撮影するのとは全く違うクオリティの写真が残せるので、会社紹介資料をはじめ様々な媒体で活用することができ、とても重宝しています。
会期が始まると、来場数やお客様対応の結果を踏まえてブースに変更が加わることがあるため、撮影は会期初日の朝に行っています。壁や什器の垂直に合わせ、デモPCの画面の角度を90度に揃えて撮影しています。
自社ブース
遠方開催の展示会以外はなるべく会期中も会場に足を運び、実際にお客様が入ってメンバーが応対している様子を見ることで、意図した通りの動線になっているか、使いにくそうにしているところがないかなどを確認します。また、実際に接客をしているメンバーの声を聞き、出てきた感想や改善アイデアなどを次回以降の設計の参考にします。また、口頭での会話だけでなく、Slackでも気づきをポストする専用のスレッドを立て、記録を残しています。
他社ブース また、会場全体を回って他社ブースも一通り確認し、展示会ブースのトレンドを把握することも意識しています。特に毎回目を引くブースや魅力的な空間づくりをしている企業のブースはマップで位置を確認して必ず拝見するようにし、新しい見せ方にチャレンジしている部分やこれまでと変化している部分がないかを確認したりしています。
会場全体
同時に、会場を回りながら来場者の動きや区画ごとの賑わいを確認したり、道幅を確認したりすることで、今後の出展検討やブース設計の際の参考にしています。
以上のプロセスを経て、Qastの展示会ブースは作られています。主催社さん、パートナー企業さん、現場の職人さん、社内のメンバー、関わる皆さんのご協力のおかげで魅力的なブースづくりが実現し、他社の方々からも評価のお声をいただけるようになってきました。
「完全版」と銘打った事例ではありますが、これはあくまでも「これまでの完全版」であり、any/Qastの展示会はこれからもどんどん進化を続けていきます。
冒頭で書いた通り、2025年中に展示会戦略を大きく変える計画になっており、それに合わせて什器などのアップデートを予定しています。また、ノベルティについても、より一層メッセージ性やデザイン性、オリジナリティのレベルを引き上げたものにアップデートしていく計画があり、現在準備が進行中です。
見た目や体験のクオリティも今までの2倍、3倍に引き上げていき、誰もが思わず立ち止まって見たくなる、ワクワクに満ちた空間にできればと考えています。
またアップデートされたタイミングで、その過程も事例化し、ナレッジ共有ができれば幸いです。