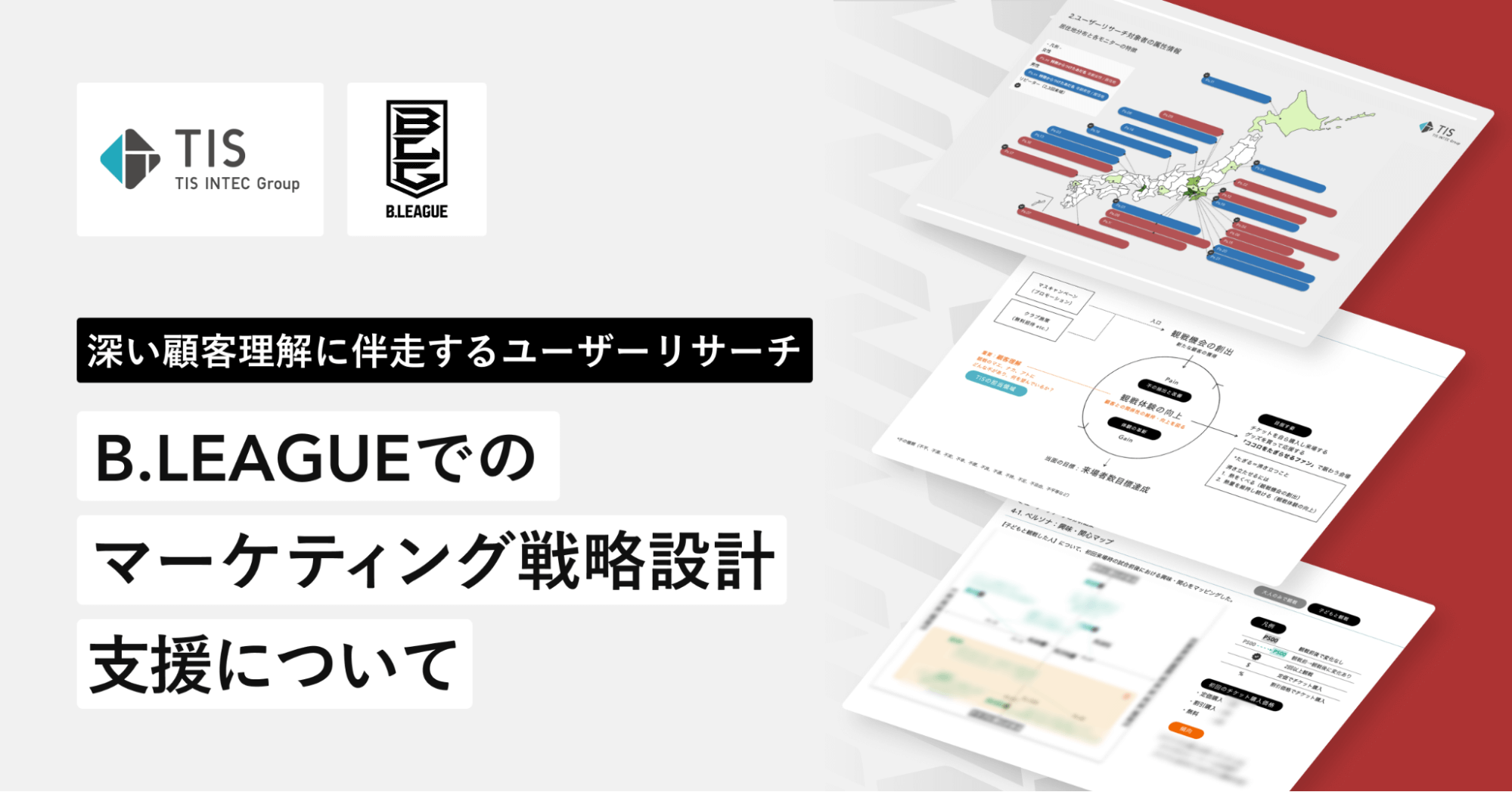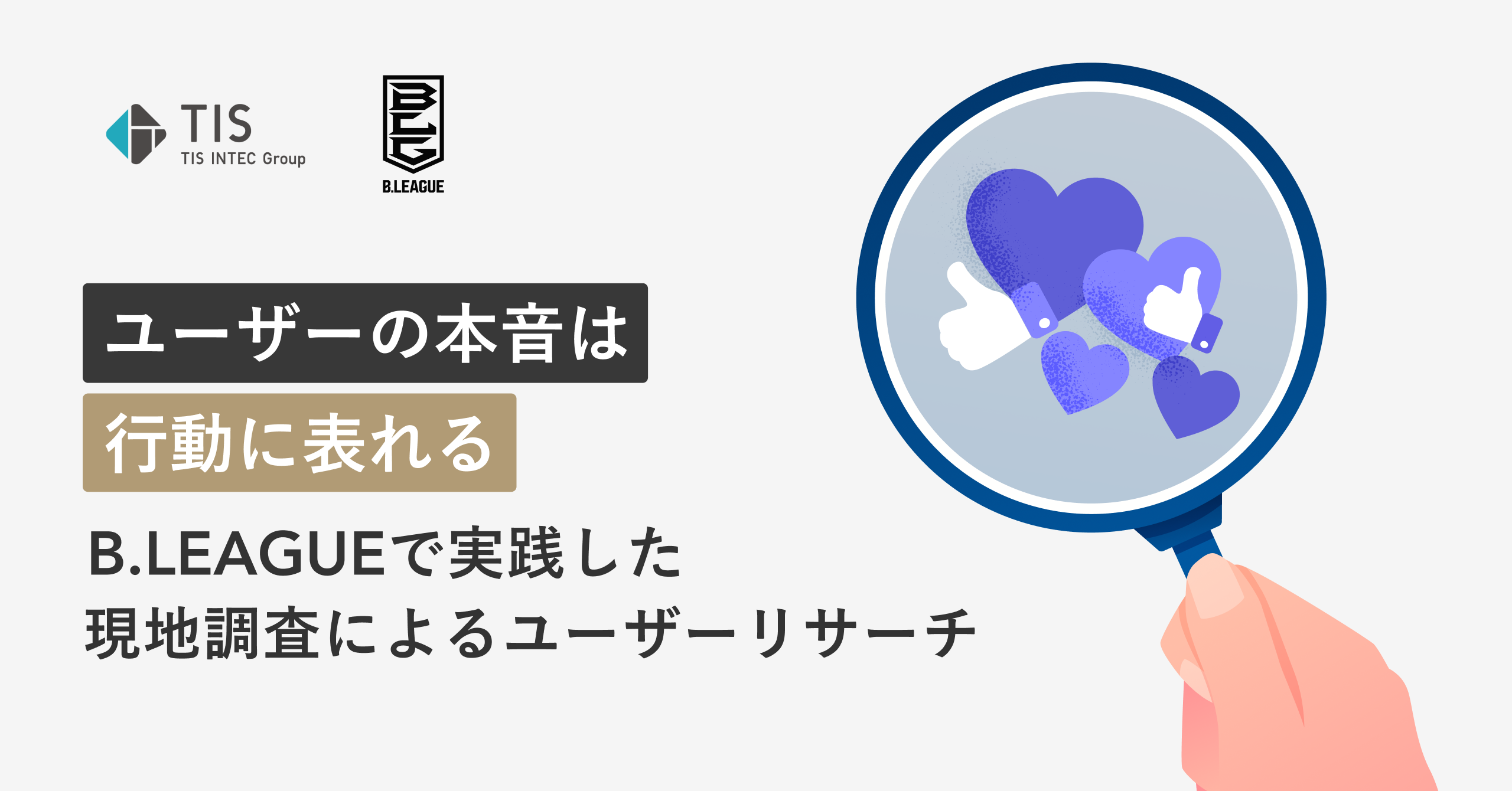TIS XD Studioは、B.LEAGUEのブランド実現に向けた共創パートナーとして、デザインの伴走支援を行っています。
その取り組みの一環として、B.LEAGUE のファン向け施策「B.旅PROJECT(以下、B旅)」において、体験設計やLPの世界観構築、ロゴやコピー制作に至るまで、PoC(Proof of Concept:概念実証)成功に向けたデザインを一貫して担当しました。
B.LEAGUEが掲げる「感動立国」というビジョンのもと、「ファンが自然と参加したくなる体験とは何か」をB.LEAGUEの皆さまと一緒に考え、そのアイデアを実際に行動を促す仕組みとしてかたちにすることを心がけました。
今回は、B旅を通じて実践したデザインの裏側をご紹介します。
B旅は、ホームタウンの「オススメ」観光スポットを、B.LEAGUE ファンやクラブチーム、選手が発信し合い、つながることで、応援や地域活動を盛り上げる参加型プロジェクトです。
B.LEAGUEファンによるおすすめスポットは、「#B旅 #クラブチーム名」のハッシュタグをつけて多数投稿されています。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
このプロジェクトが立ち上がった背景には、B.LEAGUEが2050年に創りたい世界観として掲げるビジョン「感動立国」があります。
「感動立国」には、バスケットボールというスポーツの枠を超え、地域や産業を盛り上げ、感動を通じてこの国のすばらしさを再認識できる世界を創るという、大きな志が込められています。
このビジョンを実現するうえで、バスケットボールを通じた地域活性化も重要なミッションのひとつです。こうした文脈のなかで、B.LEAGUE内で企画検討が進められていたのが、「B旅」プロジェクトです。
B旅には、地域関係人口を拡大していくことが期待されていました。
B.LEAGUEファンは、全国各地のアリーナで開催される試合を観戦するために足を運びます。特にアウェイゲームでは、県を越えて遠征することも珍しくありません。
もし、遠征中に地域の魅力をより深く知ることができれば、アリーナでの観戦に留まらず、体験の幅が広がり、さらに充実した時間を過ごせるでしょう。しかし、それが叶わなければ、せっかくの遠征も楽しみが半減し、地域への経済的な貢献も限定的になってしまいます。
こうした課題のもと、バスケットボール観戦をきっかけにファン同士の交流が生まれたり、地域の魅力を新たに発見したりできるような体験を通じて、観戦体験がより豊かに、そして楽しさを感じられるようなプラットフォームをつくれないかという考えが、B旅の起点となりました。
このような構想をどう実現していくかを検討する段階で、TIS XD Studioにご相談をいただきました。
当時は、構想はあるものの、「求められている体験とは何か」「本当に人の行動が生まれる仕組みになっているのか」「まずは何から検証を始めるべきか」といった点を模索している状況でした。
「感動立国」というビジョン実現に向けて構想されたB旅を、いかにB.LEAGUEファンのインサイトを捉え、持続可能な仕組みとして実現していくか。
そのためのデザインをXD Studioとしてご一緒に推進していくことになりました。
このような背景を踏まえ、今回は以下のポイントを意識してデザインに取り組みました。
目指すプラットフォームとしての構造を可視化
ターゲットと提供すべき価値の仮説構築
PoCによる検証の計画
参加したくなる世界観をLPに反映し、打ち出す
まず最初に取り組んだのは、B旅がプラットフォームとして目指す構造を可視化し、共通認識を持つことでした。
B旅においては、グルメ・観光・体験スポットなどの地域の魅力をB旅を通じて集約し、それを見たB.LEAGUEファンが実際にその地域を訪れ、体験に満足し、またB旅に参加したいと思ってもらう——そんな価値の循環をつくる必要があると整理しました。
これが最終的に実現すべき構造だとすると、そこに至るまでのプロセスを明らかにすることも重要です。
何もない状態から、最初のにぎわいが生まれ、参加者が増え、ステークホルダーが集まり、価値の総量も増えていくといった流れを想定した際に、まず検証すべきことは「本当に人が動くきっかけをつくれるか(最初のにぎわいをつくれるか)」です。
B旅においては、まずB旅を通じてその地域に「行ってみたい」と思い、「行ってみよう」と実際に行動する人が生まれるかどうかが、最優先で検証すべきことだと位置づけました。
このような整理を行いながら、適宜B.LEAGUEの皆さんとディスカッションを重ねることで、「何を実現するために、いま何を検証すべきか」という目線のすり合わせを行っていきました。
B旅を通じて実際に行動する人が生まれるかどうかを検証するうえで、まず取り組んだのは「誰をターゲットとするのか」「どのような価値を提供すべきか」を明確にすることでした。
一口にB.LEAGUEファンといっても、純粋にバスケットボールが好きな人、非日常の体験を求める人、子どもの喜ぶ顔が見たい人など、観戦に求めるものは人それぞれです。
そのなかでも、B旅に参加したいと思う可能性が高いのは、「これまでに遠征して試合観戦をした経験がある人」「新しい場所や人との出会いに喜びを感じるタイプの人」だと想定されました。
こうした想定を踏まえ、バスケットボール観戦に対して何を求めているかという点と、B旅に参加しやすい条件とを照らし合わせながら、ターゲットとすべき対象を絞り込んでいきました。
XD Studioはこれまで、B.LEAGUEにおけるマーケティング戦略の設計支援を行う中で、B.LEAGUE ファンに対するユーザーリサーチやペルソナの分類、ジャーニーマップの構築などに取り組んできました。
こうした取り組みによって得られた知見が、今回のターゲット選定の土台となっており、同時にB.LEAGUEの皆さんとの深い合意形成にもつながっています。
ターゲットを定めたあとは、提供すべき価値の整理に取り組みました。
B.旅でしか得られない体験とは何か、行きやすさを感じられる要素はどこにあるのか、どのような世界観であればより参加したくなるのかといった視点から価値を整理し、それらを踏まえて、B.旅におけるコアアクションである「おすすめスポットの投稿」を促す仕組みの設計にも取り組みました。
次に、設定したターゲットや提供すべき価値の仮説が正しいか、そして実際に行動が生まれるかを検証するために、PoCの計画を立てました。
アイデア段階では魅力的に思える内容でも、実際に検証してみなければ、その妥当性を判断することはできません。また、何を学ぶための検証なのかを明確にしていなければ、単に「やっただけ」で終わってしまう懸念もあります。
そこで、仮説の内容や学びたいこと、検証方法、その他の条件などを細かく設定し、効果的にB旅をリリースするためのステップとして、検証計画を構築しました。
B旅を知ってもらう接点となるLP(ランディングページ)のデザインにも、さまざまな工夫を凝らしました。
B.LEAGUE側で作成されていたワイヤーをたたき台としながら、「どのようにすれば世界観がより伝わりやすく、参加してみたいと感じてもらえるか」という視点でデザインを進めていきました。
たとえば、当初はB.LEAGUEのトンマナを踏まえた黒を基調としたデザインとなっていましたが、少し固い印象に見受けられたため、よりライトな層でも親しみやすく感じられ、ワクワク感を演出できるような明るく開放的なビジュアルへとブラッシュアップしていきました。
さらに、「投稿すると抽選でオリジナルグッズがもらえる(金銭的報酬)」「投稿内容がLPにも掲載される(社会的報酬)」など、参加するきっかけをつくるための工夫もLPに取り入れました。
B旅の公開後、多くのB.LEAGUEファンの方々にご参加いただきました。キャンペーン期間の47日間で投稿されたおすすめスポットは約200件にのぼり、ファン同士の交流や、地域の新たな魅力発見にもつながっています。
B旅が目指した体験が、B.LEAGUEファンに受け入れられ、実際の行動につながったことは、大きな成果であり、価値のある検証結果だったといえます。
さらにこのプロジェクトを通じて、「どのような人が遠征をするのか」「何回遠征すると、継続的に遠征したくなるのか」といったインサイトへの解像度も高まり、B.LEAGUEにおける今後の施策立案にも活かせる学びも得られました。
今回のB.旅PROJECTにおけるデザイン支援に対し、B.LEAGUE様からは以下のようにコメントをいただいています。
ここまで、B.LEAGUEが掲げるビジョンの実現に向けた取り組みの一例として、「B.旅PROJECT」のデザインの裏側をご紹介しました。
XD Studioでは常に、お客様が目指すビジョンに真摯に寄り添いながら、デザインを推進しています。コンセプト設計からビジュアルデザインに至るまで、一貫してユーザー中心のアプローチを大切にしています。
たとえば、ビジョンの実現と事業成長を両立させる全体戦略の設計、ユーザーインサイトを深く掘り下げるリサーチ、ユーザー中心のものづくりを実践する組織づくりなど、さまざまな伴走支援を続けています。
サービスやプロダクトの開発、デザイン組織の立ち上げなどでお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。具体的な支援ができるかどうかに関わらず、これまで培ってきた知見や経験をもとに、少しでも皆さまのお役に立てればと考えています。