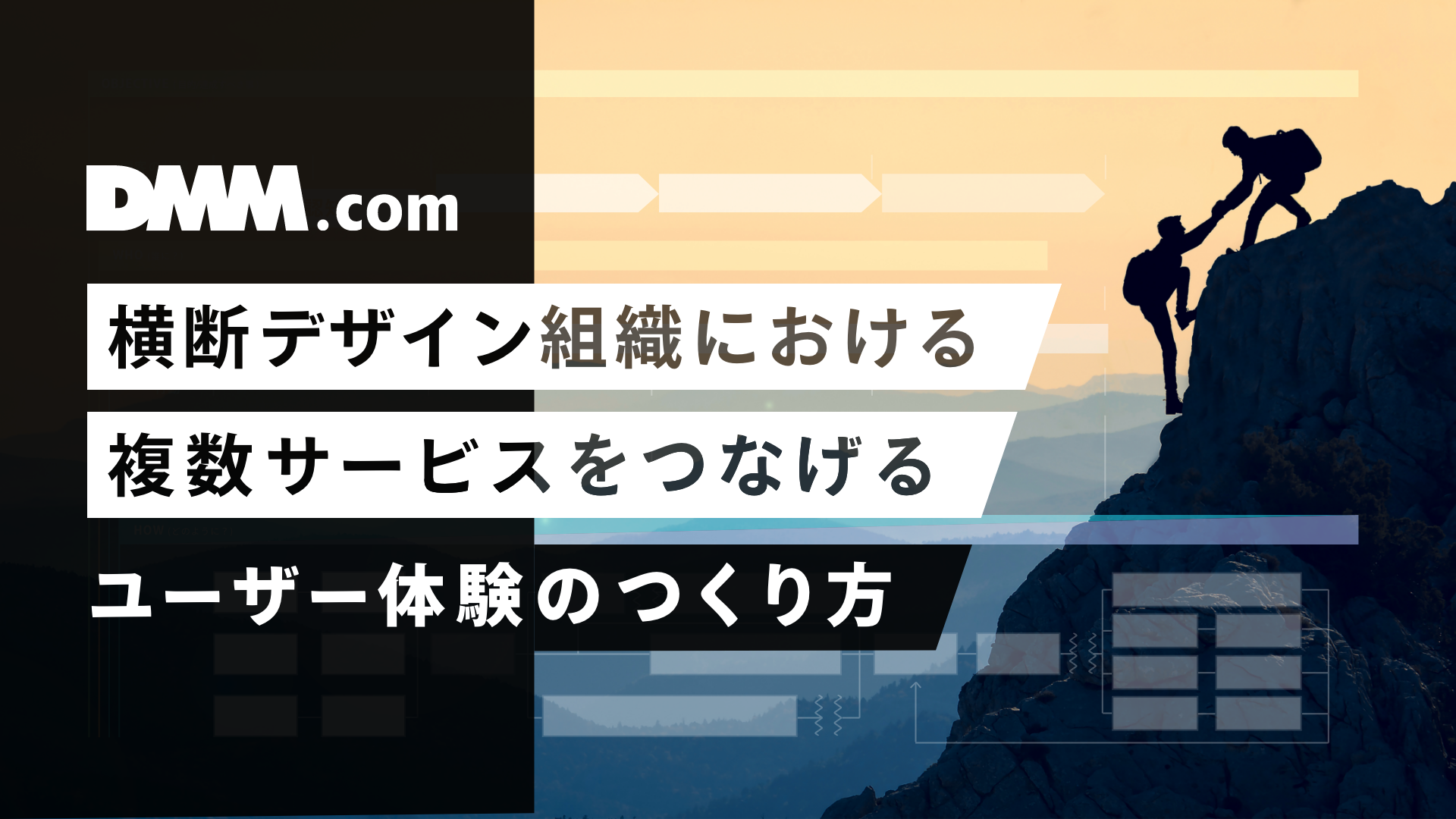DMMデザイン部 第1グループでは、DMMが展開する60以上の事業全体のユーザー体験 (以下UX) をつなぐことで、プラットフォーム全体の事業価値を高めていく役割を担っています。
第1グループの役割や過去の取り組みは、こちらに詳細にまとめているので併せてご覧ください。
2023年5月ごろから「DMM.com総合トップページ」のリニューアルデザインを、デザイン部 第1グループが推進してきました。
https://www.dmm.com/
総合トップページは、DMM.comが展開する多くのサービスへの入口となるページであり、サービスに触れるユーザーの体験や、それを通じた各事業間のシナジーを強めるうえでも極めて重要なタッチポイントです。
長らく、事業部などの多くのステークホルダーが関わるために「どんな方針で改善を行うか」を取りまとめることが難しく、 大規模な改修に手を付けられていない状況でした。
これに対し、全社横断的にプラットフォーム全体のUXを最大化させる役割を担う私たちが、企画設計から全社での合意形成、実行までを推進していきました。そのために何に取り組んできたか、まとめていきます。
総合トップをリニューアルすべきと考えた背景には、数多くの事業を抱え第二創業期を迎えたDMMにおいて、個々の事業の力をDMM全社としてのシナジーの力に増幅していくという経営方針があります。
この方針を実現していくためには、個々の事業のUXを磨くだけでなく、プラットフォーム全体でのユーザーメリットを高め、クロスセルやアップセルが自然と生まれる状態を作ることが重要です。
第二創業期の戦略に対し、当時の総合トップは様々な要因から改善が鈍化していました。
同時に、事業やサービスの拡大が続いた結果B向けの情報が多くなり、別途公開している企業サイト側での事業形態を紹介するコンテンツ拡充も追いついた状況で、「誰に向けて、何をしてもらうためのページなのか」を見直すべきタイミングに至っていました。
そこの状況を踏まえて総合トップのあるべき姿として、特にC向けにパーソナライズ面を強化することで、併売を促すためのページとしてリニューアルし、B向けのサービス一覧はコーポレートサイトに役割を移すべきだと考え、加えて開発力強化の実践場所として申し分ないことも併せて提案の考慮に入れました。
具体的には、 動画など特定のサービスのみをこれまで利用していたユーザーに対して 電子書籍など他のサービスもレコメンドしていくといった、「サービス紹介軸」でなく「商品紹介軸」へアプローチを加える方向で構想を固めていきました。
ただし、構想があるというだけでは全社にまたがるプロジェクトを実行に移し、企画目的を達成することはできません。
前提となる戦略や企画の意義、具体的な施策案や実行計画を明確化し、関わる様々なステークホルダーと合意形成することが必要ですし、これほど大きなプロジェクトを進めていくためには全社からの協力が必須です。
そのため、第1グループメンバーと横断マーケティングテクノロジー組織(以下、マーケティングテクノロジー部)の2部署で、以下のようなプロセスを経て総合トップのリニューアルを推進していきました。
ここからは、全社に合意形成を行い、実行に移していくまでに取り組んでいたことをまとめていきます。
はじめに、総合トップに紐づいているヒートマップやGoogle Analyticsなどを用いてデータを見ながら具体的な課題がどこにあるのかを可視化していきました。
実際に調査段階では、ログインしているか否か、どこ経由での流入なのかなど、ユーザーの属性を細分化しながら分析を進めています。
結果は、「ほぼファーストビューしか見られていない」「ページ内に複数カラムあるが、一番右の登録導線以外ほとんどクリックされていない」などで、現状はさまざまなコンテンツがあるにも関わらず有効活用できていないことが分かりました。
このような調査結果を基に、具体的にどのような方針で理想に近づけていくのかについて、より精緻な計画に落としていきました。
個々の改修施策を具体化する前に、「データを活用しながら、常に表示内容が最適化され続ける、総合トップの運用基盤を作る」という全体の改修方針を設定しました。
調査で分かった情報を基に、「情報の更新頻度が少ないため、ユーザーがアクセスする動機付けが弱い」「ユーザーに刺さるコンテンツ訴求ができていない」という課題の仮説を立て、以下のような解決のアプローチを示しています。
レコメンドによる更新頻度の向上・ユーザーに最適化されたコンテンツ訴求
継続的な検証・改善によるUI最適化
ここで立てている改修方針のポイントとして、現状の使われ方を基にした課題設定に加えて、継続的にデータを活用した改善ができる運用体制もスコープに含めていることがあります。
今まで、長年改善がされていなかったことも問題として捉え、表層の見た目やユーザー体験だけでなく、裏側の仕組みまでアップデートしていくことが長期的に大きな価値を生むために必要だと考えていました。
この改修方針を踏まえて、より具体的な施策案を検討するために、ワイヤーフレームを作りながら議論を進めていきました。
既存機能を有効活用しながらも、レコメンドや閲覧性を高めていけるようなUIのイメージをワイヤーフレームで可視化し、マーケティングテクノロジー部と共に利用価値があるか・実現可能かという観点から施策案を詰めていきました。
より具体的な施策案を洗い出し、以下のようなジャンル分けを通じて施策の優先度も設定しています。
改善サイクル基盤構築
経由利益獲得
サービス新規獲得
商品・サービス訴求力向上
また、各施策における具体的な狙いや、改善イメージについても詳細に資料に落としこみました。さらに、全体の開発ロードマップも作成することで、実現可能性への解像度を高めています。
このような設計と資料による可視化を通じて、社内の各事業部や、経営層とのコミュニケーションを行い、実際に企画を推進していくことになりました。
企画の承認を経て、実際に事業部と連携しながら施策を実行していきます。プロセス面では、一気に全ての施策を実施して終わりという形ではなく、1つ1つの施策を部分的に実装しながらデータを確認し、柔軟に方針をアップデートしながら進めていくことを意識していました。
実際の検証プロセスでは、必要に応じて様々なステークホルダーと連携しながら進行しています。
例えば、ABテスト設計にはデータ推進部の専門家に入っていただき、施策ごとにどんな指標を見るべきか相談しながら設計していきました。また、動画に関わる施策であれば動画事業部と連携し、要望や思いもヒアリングしながら、どんなレコメンドロジックにすべきか、技術的に可能かなどを詰めていきました。
プロジェクトとしてはまだ途中ではありますが、KPIを上回る有効な施策も生まれており、引き続き改善を進めていきます。
企業の姿勢をプロダクトに反映し続けるには、継続力が大切です。
様々な業態で事業を作っていくことと同様に、プラットフォーム全体でそれらを繋いていくことも重要であると、社内での再認知が広がっています。
関わるステークホルダーが「各専門領域や責務を通じてDMMをよくしよう」と思い努力している中で、一方的に「あるべき姿」を押し付けるだけでは物事は進みません。
会社全体の戦略を理解し、各サービスにどのような影響があり責務を全うしようとしているかを理解し、個々の専門視点や思いを理解し、それらを一度しっかり受け止める。テクノロジーも大事ですが、それ以上に社内での信頼関係の構築が大事であると強く意識し、マーケティングテクノロジー部のメンバーと本プロジェクトを推進してこられました。
結果、「市場競争力の強化」や「当たり前品質」を満たす様々なゴールを各事業やサービス利益につなげて、ステークホルダー皆で共有でき「DMMの顔とも言える総合トップ」で継続的な改善が回る状況を構築できたと考えています。
今回ご紹介した事例は、DMMのデザイナーの活躍の幅を広げる上で、様々なプロジェクトで企画フェーズのシーンで呼んでもらえる機会を増やす、さらなるきっかけとなりました。デザイン部は、ただ作るだけでなく、様々な事業やサービスのシナジーをデザインの力で増幅する役割を担っていきます。