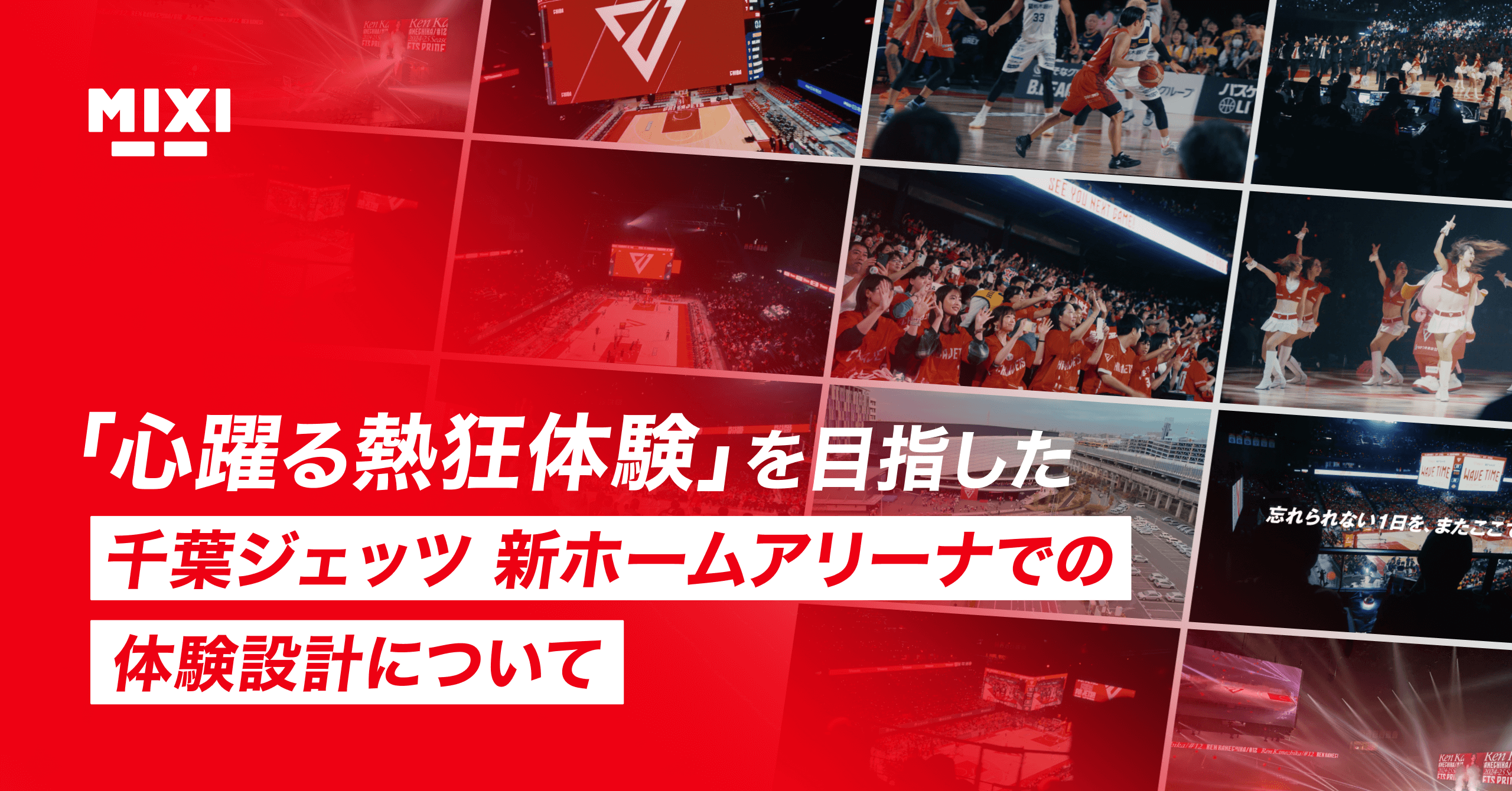2024年10月にりそなグループ B.LEAGUE 2024-25シーズンが開幕しました。今シーズンから、「千葉ジェッツ」のホーム試合は、2024年5月に開業した新アリーナ 「LaLa arena TOKYO-BAY」で行われています。
新アリーナでの試合開始前やハーフタイムには、会場に訪れたブースター(ファン)が自身のスマホで撮影した映像を、リアルタイムでセンタービジョンに映し出される参加型コンテンツ「BOOSTER’S CAM」が実施されています。
シーズン開幕に向け、多くのタスクが並行する中、MIXIのデザイン本部と開発本部を中心にシステムを構築しました。さらに、ライブエクスペリエンス事業本部、法務部、千葉ジェッツふなばしとが密に連携し、プロジェクトを進め、開幕戦で実施することができました。
今回は、BOOSTER’S CAMの実施背景やプロセスをまとめたいと思います。
この施策を実施した背景には、「アリーナという空間を共有する人同士の特別なコミュニケーションの機会を提供するとともに、より楽しく、思い出に残るような観戦体験をしてもらいたい」という考えがありました。(より詳細な体験設計の意図やプロセスはこちらの事例にまとめられています)
施設規模として、LaLa arena TOKYO-BAYは、これまでの本拠地であった「船橋アリーナ」から2倍以上の約1万人。さらに、センタービジョンやリボンビジョンを備え、多様な演出が可能となりました。
アリーナの進化に合わせ、観戦体験をさらに向上させるための施策を検討する中で、BOOSTER'S CAMの企画が立ち上がりました。
類似施策として、アリーナ内に設置されたPTZカメラ(遠隔操作可能なカメラ)を使い、運営側のオペレーターが観客席の様子を撮影してビジョンに映し出すというものもあります。
一方、BOOSTER’S CAMは、アリーナ内にいる誰もが能動的に参加できます。
PTZカメラと比較して画角が狭いセルフィーカメラで撮影するため、友人や家族と距離を縮めて一緒に映ったり、お子さんやグッズを映したりと参加者が映したい対象を選ぶことができます。また、センタービジョンに映るかもしれないと、みんなでカメラに向かってワイワイする時間を増やせるのではないかとも考えました。
加えて、アリーナには千葉ジェッツのブースターだけでなく、アウェイ(相手チーム)のブースターも来場します。その中で、アウェイブースターの方々にも当然楽しんでいただきたいですし、応援するチームは違っても、「応援」という根っこの部分で繋がっていることを、BOOSTER’S CAMを通して感じてもらい、お互いをリスペクトし合えるような応援空間にするというコンセプトがあります。
しかし、BOOSTER’S CAMを実現するためには、さまざまな専門性が求められます。
センタービジョンに表示するビジュアルや、手元のスマホで利用するWebアプリケーションなどはもちろん、アリーナ内での映像受信・再送信システムや、オペレーション時に使用する機材や運用フローの準備も必要です。
そのため、MIXIデザイン本部と開発本部、ライブエクスペリエンス事業本部などのメンバーでプロジェクトチームを組成し、密に連携しながら作り上げていくことになります。
ここからは、BOOSTER’S CAMをどのようなプロセスで作っていったかをまとめたいと思います。
遡って、バスケットボールの本場であるNBAの試合を体験する機会をいくつか設けました。BOOSTER’S CAMだけに限らず、アリーナ体験を設計するにあたって、自分の身体で体験しないことには始まらないと感じたからです。
NBAは、興行規模や注目度が日本と比べて圧倒的に高く、まさにスポーツエンタメの最高峰と言えます。ネットでも情報が得られるのですが、個人的には情報量が少ないと感じます。やはり、可能な限り自分の目や耳、身体を使って体験することを心がけています。
現地で観戦した試合でも、BOOSTER’S CAMに似たコンテンツが実施されていました。私も自身のスマホで参加してみたところ、幸運にもビジョンに映ることができました。
ビジョンに映った瞬間の驚きや盛り上がりは、とても興奮しました。帰国してからも周りに「実はビジョンに写ったよ!」という会話をしていました。ビジョンに映ったことは友人や知人にもエピソードとして共有できる特別な経験であり、それはコミュニケーションのきっかけになるということを身を持って体感しました。
このような経験も参考としながら、BOOSTER’S CAMの企画を具体化していき、デザインを作成していきます。
具体的には以下を、デザイン本部内のデザイナー・エンジニアを中心に行っていきました。
スマホやセンタービジョンに表示するUIのモックアップをFigmaで制作
スマホ側での、二次元コード読み取りによるセルフ映像撮影の実装
Next.js + MUIを使用したフロントエンドデザインの実装
BOOSTER’S CAMは、スマホ側で操作するウェブアプリや、センタービジョンへの表示ができるだけでは機能しません。
その裏側では、アリーナ内での映像の送受信や、センタービジョンに表示する映像の切り替えなど、複数のシステムが連携して動作しています。このシステム構築を、MIXI開発本部のメンバーを中心に担当しています。
システムの概要は以下のようなものです。
センタービジョンに表示された二次元コードを観客が自身のスマホで読み取る
スマホのカメラが起動し、自撮り映像がサーバーに送信される
アリーナ内の映像音響室の機材から、サーバー上の映像を受信
機材で選択された映像がセンタービジョンに表示される
スケジュールの関係上、短期間でシステムを構築する必要がありましたが、これらのシステムはすべて開発本部による内製で作り上げています。
開発本部では、MIXIのあらゆる事業に関する技術支援を行っています。また、事業に活かせる技術検証も日々行っているため、今回のようなシステムも開発本部単体で素早く構築できるという強みがあります。
参考 : MIXI、アスリートの競技力向上に活用できる自動追尾カメラシステムを開発 フィギュアスケート選手のトレーニング拠点で運用開始
2024年10月5日に実施されたシーズン開幕戦(MIXI presents)で、BOOSTER’S CAMが初めて導入されました。
実際にBOOSTER'S CAMで映し出された方々の様子を見ていると、
一緒に来ている友人や知人と映って盛り上がる
子どもや家族を撮影する
推しの選手のグッズを見せてアピールする
など、思い思いの楽しみ方をされていました。
特に印象的だったのは、自分自身だけでなく、一緒に来ている友人や家族を映す方が多かったことです。BOOSTER’S CAMを通して、その場に一緒に居る人たちとのコミュニケーションが生まれ、より楽しい時間を過ごせるきっかけを提供できたのであれば、とても嬉しいことだと思います。
BOOSTER’S CAMは、2024-25レギュラーシーズンの千葉ジェッツのホーム試合で今後も実施される予定です。実際にアリーナで観るバスケットボールは、迫力があって見応えのある選手のプレーはもちろん、会場演出や応援の一体感を味わえますので、ぜひ足を運んでいただきたいです。その際、ぜひBOOSTER’S CAMにもチャレンジしてみてください。
今回のBOOSTER’S CAM施策は、MIXIにおけるデザインと技術の共創によって生まれました。
千葉ジェッツの試合会場に訪れた方々に、ただ見るだけでなく、その場にいる人同士で共有できるコミュニケーションの機会を提供することで、より楽しく、豊かな時間を過ごしてもらいたい。このような共通の目的に向けて、デザイン本部や開発本部をはじめ、各部門が垣根を越えてアイデアを出し合い、それぞれの専門性を存分に活かすことで実現することができました。
「こういうことを実現したい」となった時に、それに共感する多様な専門家たちが社内から集まり、実現に向けて動き出す。たとえスケジュールにあまり余裕がない中でも、近い距離感で密な連携が可能だったからこそ進めることができる。 こうした要素が、今回のプロジェクトを実現させることができた要因となっています。加えて、開幕戦となる「MIXI presents」試合にむけ、社内に呼びかけたテストでは、何百人ものMIXI従業員が同時接続テストに参加してくれました。
MIXIのものづくりは、デザインや技術など、多様な分野で活躍するスペシャリストたちの存在によって支えられています。それぞれの専門性を活かしたケイパビリティが連携し、新たな挑戦を後押しするとともに、実現可能性を高め、可能性を広げています。
こうした背景をもとに、MIXIのパーパスである『豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。』という目標の実現をさらに加速していきます。
2025年5月追記 : BOOSTER’S CAMの制作秘話について、詳細にお話した内容をYouTubeにて公開しています。ぜひあわせてご覧ください。