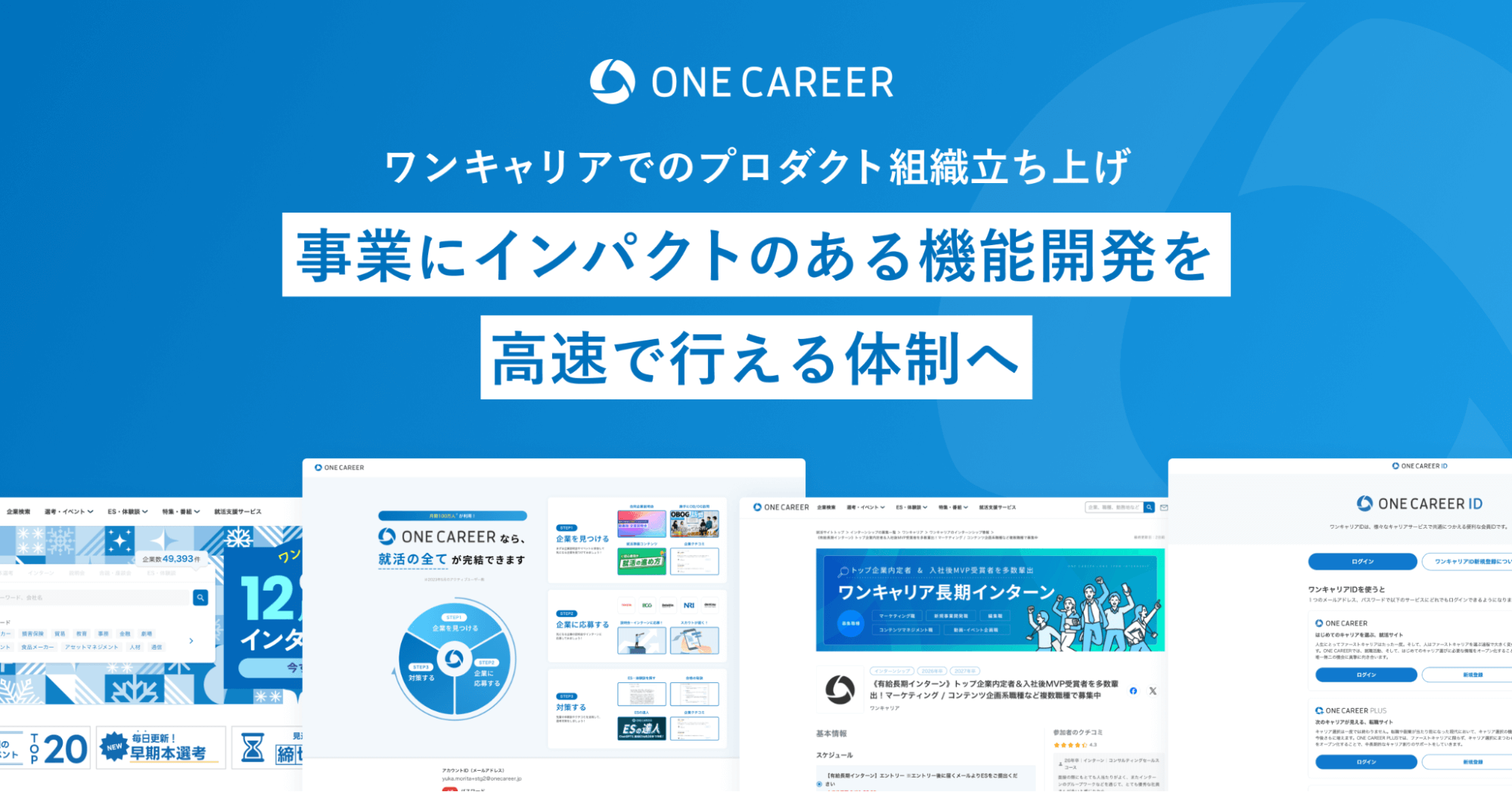ワンキャリアのプロダクト組織は、2019年からスタート。何度か組織体制更新を経て、現在は新卒採用事業・中途採用事業の全体にまたがる組織になるまで成長してきました。
私は2020年8月に3人目のエンジニアとして入社し、当初はテックリードの役割でしたが、プロダクトマネジメント組織の立ち上げ、開発組織全体の採用、ROIにつながる開発フローの整備など、必要な役割を順に担い続けてきています。
一貫して「ビジネスに貢献できるプロダクト組織をつくる」という目的に向けて、数年後の組織の理想状態に向けて “収束” させていくように進めてきたワンキャリアのプロダクト開発組織づくりの裏側を、包み隠さずお伝えします。
ワンキャリアは2015年に創業されました。当初はエンジニアがいない完全外注でスタートしています。
一方で、そもそもワンキャリアは数あるHR事業を運営する会社の中でも、データやAI活用といった「プロダクトで勝つ会社」であるのが特徴です。
HR領域は情報がブラックボックス化しており、意思決定の基準となるデータが少ないことが課題です。これを私たちは「ワンキャリア」や「ワンキャリアID」といったシステムを新たに開発し続けることで解決しようとしています。
このようなプロダクトを中心とした事業成長をより加速させていくために、2019年に現在のCIO (Chief Information Officer) 田中が1人目のエンジニアとして入社、プロダクト組織の内製化をスタートしています。
一方で、私が3人目のエンジニアとして入社した段階では、まだまだプロダクト開発の基本的な手順が身についていない組織状態となっていました。
つくりたいものはあっても、そもそもリターンへの意識が弱かったり、工数が不足してしまう、といった当たり前のプロダクト開発もできていない状況。私は入社後に、この状況を抜本的に変えて「プロダクト組織からビジネスを動かしていける」体制をつくることを決めました。
とはいえ当時のワンキャリアには、社内でプロダクトの仕様を決めるノウハウもなければ、デザイナーやエンジニアもいません。組織成熟は必須な状態でした。成熟しなければ、入社したい人も現れず、影響範囲も広げていけません。
ここで私が重視したのは “未来の組織に収束させる” ように組織づくりを進めることでした。
数年先の理想の組織状態に向けて収束していくように、さらには、自分がいなくても勝手に進んでいくような状態をつくるために、組織体制を意図的に壊しては再構築することを繰り返してきました。
具体的にやったことは、以下の2つに大きく分けられます。約5年の変遷を、2つの切り口からまとめていきます。
1. 組織体制の更新
2. ビジネス貢献できるプロダクト組織を目指した、組織成熟の仕組み
まずは、組織体制の変遷についてです。この5年間で、一見すると抜本的な組織体制変更を繰り返してきました。
その実態としては、現場の組織成熟度に合わせて、少し先の「収束させたい組織状態」を定義して、そこに合うような組織体制に変更する。組織のパフォーマンスが追いついてきたら、また同じように少し先の未来に向けて体制変更を行う...というアクションを繰り返しているようなイメージです。
大きく分けると、現在までに4つの組織成熟フェーズを辿ってきました。これらを段階ごとに整理してみます。
まずは2019年ごろ、プロダクト開発の内製化が始まりました。プロダクト組織の体制としては社員は4名程度、業務委託は数名。
「仕様を決める」→「デザインする」→「実装する」→「リリースする」→「安定的に運用する」という一般的なプロダクト開発が未熟でしたので、そこを整えていた時期です。これは、いわば「慣れのフェーズ」とも言い換えられます。
・収束点: プロダクト開発の内製化に慣れる
・HOW: まずは一般的なプロダクト開発フローを取れるようにする
そもそも内製化をしていなかった組織で、当たり前に内製開発を進めていくことができることがミニマムのステップでした。
「慣れ」が生まれてきて、普通に案件進行ができるようになりつつあったタイミングで、次のフェーズへと進んでいきます。
2022年ごろ、開発の進行がてんやわんやしなくなってきました。組織としても、新卒のエンジニアなども入社してきて、エンジニアリング業務が安定してきます。
このタイミングで、組織体制を変更しました。開発部は横断で配置しつつ、企画職種としてPdM (プロダクトマネージャー) を新たに設置しました。
この体制変更は、最終理想である「プロダクト開発組織からビジネスを動かす」という状態に向けて、さらに企画に意識を向けられるような組織成熟を狙ったものでした。
・収束点: 企画にまで入り込む
・HOW: PdM職種を新設する
ちなみに私自身もこのタイミングでPdMを名乗り始めました。社内にもPdMのロールモデルがいない状態なので、私がまず率先して成功例をつくる必要があるだろうと考えていたためです。
また、事業性質ごとにフローや難易度が変わるため、成熟が起こり切っていないこのタイミングでは、PdMの担当範囲はtoC、toBで分けるようにしています。
2023年8月、PdMも企画周りの動きに慣れ始めてきたタイミングで、さらに次の組織状態に進化させていくため、変化を加えます。
ここでの収束点は「つくったものによってROIを高める」ことだと定義しました。ROIを高めるためには、案件単位の企画ではなく、事業全体の体験を設計することが必要となります。
そもそも、フェーズ2で、PdMの担当範囲をtoC、toBと分けていたのは、「企画業務への慣れ」をつくるためでした。ただ、ワンキャリアは求職者と企業を繋げる採用プロダクトであり、本来はプラットフォームを通して事業全体の体験を扱えるようにする必要があります。
そこで、事業全体の体験を扱えるプロダクト組織へとアップデートしていくために、toC、toBで分けていた組織を統合して「プロダクト開発部」と変更しました。
・収束点: つくったものによってROIを高める
・HOW: 事業全体の体験を設計できるような体制に
ここでは、toC、toB合わせた事業全体の機能開発優先度付けや、プロダクト施策からのROIへの貢献を測定できる仕組み化など、より事業を動かせる企画を設計できるようにフローの改善を試みています。
結果としてプロダクト開発から事業を動かしていく施策が生まれていきました。
そして2025年1月、最新のプロダクト組織の変更を行いました。
事業単位でのROI向上よりも、さらに組織のステージを上げていき「事業群全体としての生産性を高める」ことを収束点として考えています。
具体的には、新卒採用事業・中途採用事業を合わせた全社としての体験設計に取り組み出しました。
・収束点: 事業群全体としての生産性を高める
・HOW: サービス群全体の体験を設計できる体制に
ワンキャリアは、新卒採用事業、中途採用事業、など複数の事業を組み合わせて、人生に寄り添ったキャリア開発をサポートしていくことを志向しています。
これらのサービスを繋ぐ「ワンキャリアID」のような、事業間をまたいだ体験設計も、今後プロダクト組織から生み出していくことが求められています。
これが、現在のワンキャリア プロダクト組織が次に辿り着くべき「理想状態 」です。ここに収束したら、また次の理想状態を置き、組織変革を繰り返していくことでしょう。
組織体制の変更をかけていく動きと同時並行で、ビジネス貢献できるプロダクト組織に向けて、組織成熟を促していくための仕組みも構築していきました。
ポイントは「ドラスティックに変えてもうまくいかない」ということです。いきなり180度変わった、と受け取られないように、先読みで変化を小さく起こすことを意識しています。
いくつか具体例を紹介します。
プロダクト組織の内製化を始めた立ち上げ当初から、「領域の線を引かない」「熱心に学ぶ」「感謝・リスペクト」という3つのカルチャーを浸透してきました。
単なる受託的な内製開発組織では、ビジネスを動かしていくことはできません。さらに、立ち上げ当初はメンバーの力も足りていません。なので、そもそも熱心に学び、領域を超えていくスタンスを内部のメンバーが取っていくことが重要でした。
私の工夫としては、「自分がいなくても回る」状態を目指すことです。これらのカルチャーを意識した行動が徹底的に浸透するように “3世代先” までの行動を細かくチェックしていました。
カルチャーを提示した私が1世代目、私が直接声かけ/レビューを行う対象が2世代目、その2世代目の先にいる直接は私が関わらない対象が3世代目です。この、自分が関与していない3世代目の行動が変わっていれば、「カルチャーは浸透している」と認識して良いだろうと考えて、Slackのやり取りなどを逐一確認しつつ、組織状態を観測していました。
組織立ち上げ段階の大きな課題の一つが、「採用」です。ここでも “収束” させる組織づくりの考え方を取り入れています。
例えば、立ち上げ当初は、ほぼ間違いなく採用競争力が低いところから始まります。ただ、採用活動を続け、社内でも組織成熟を起こしていくと、徐々に採用競争力は高まっていく性質があります。
私はこの構造を踏まえ、「採用競争力が上がってくるまで」「上がってきてから」というフェーズをあらかじめ数年越しで想定して、採用アクションをつくっていました。
例えば採用基準を年々高めていくとすると、母集団を日本だけでなく海外からつくらなければいけなくなることを早期に予測し、社内のmtgでは英語を使う / ドキュメントを英語でつくる、などの準備をかなり早期から始めていました。実際に、今はエンジニアの1/4のメンバーが日本出身ではない方となっています。
このような 未来に向けた “収束” をつくる組織づくりの結果として、ワンキャリアのプロダクト組織は5年前とはかなり遠い場所まで成長してこれたように思います。
まず、影響範囲が大きく拡大しています。初めは開発のみだったところから、企画も含めた貢献に広がり、現在では中途採用事業も含めた事業群全体のプロダクト設計を推進できています。
さらに、ビジネス的なインパクトも大きくなっています。
プロダクトは、P/Lで言うところの原価です。ワンキャリアユーザー数や売り上げは伸び続けていますが、原価率は年々改善されています。これはプロダクト組織の成熟により、無駄な開発が行われていないことを表しています。
また、この数年間の成長の結果、採用市場におけるシェアも高まり続けています。これは、ビジネスに加えて、プロダクトによる事業成長への貢献が生まれていることの証明だと思います。
(参照: IR https://ssl4.eir-parts.net/doc/4377/ir_material_for_fiscal_ym1/178733/00.pdfhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/4377/ir_material_for_fiscal_ym1/178733/00.pdf )
とはいえ、まだまだ少数精鋭のメンバーで運営しており、伸び代が大きい状況だとも思っています。さらに組織を育てていく余白があるので、企業の成長に向けてプロダクト組織をアップデートしていきます。
プロダクト組織は一般的にコストセンターと言われる部門です。ただ私は、プロダクトへの投資は、ビジネスへの投資に比べて、非常にレバレッジが効きやすい性質があると考えています。
例えば、営業の改善によって伸ばせる指標の一つに、受注率があります。この受注率は、どれだけ頑張っても10倍までしか上がりません。(100%がMAX)
一方で、プロダクトによる改善では、10倍、100倍、1000倍の事業成長を少ない人員で起こせる可能性があります。
だからこそ、自分はプロダクト組織の成熟が重要だと思っているのです。どのくらいビジネスに貢献できるか、何倍の成長を生めるのかは、プロダクト組織の成熟度にかかっています。
現在でもプロダクト組織の成熟によって、当初プロダクト組織がスコープとしていた新卒採用事業だけでなく、中途採用事業側にもノウハウを社内共有していくことが求められてきています。プロダクト組織からもっと大きな事業インパクトを起こしていくために、意図的な組織成熟をこれからもつくり続けます。