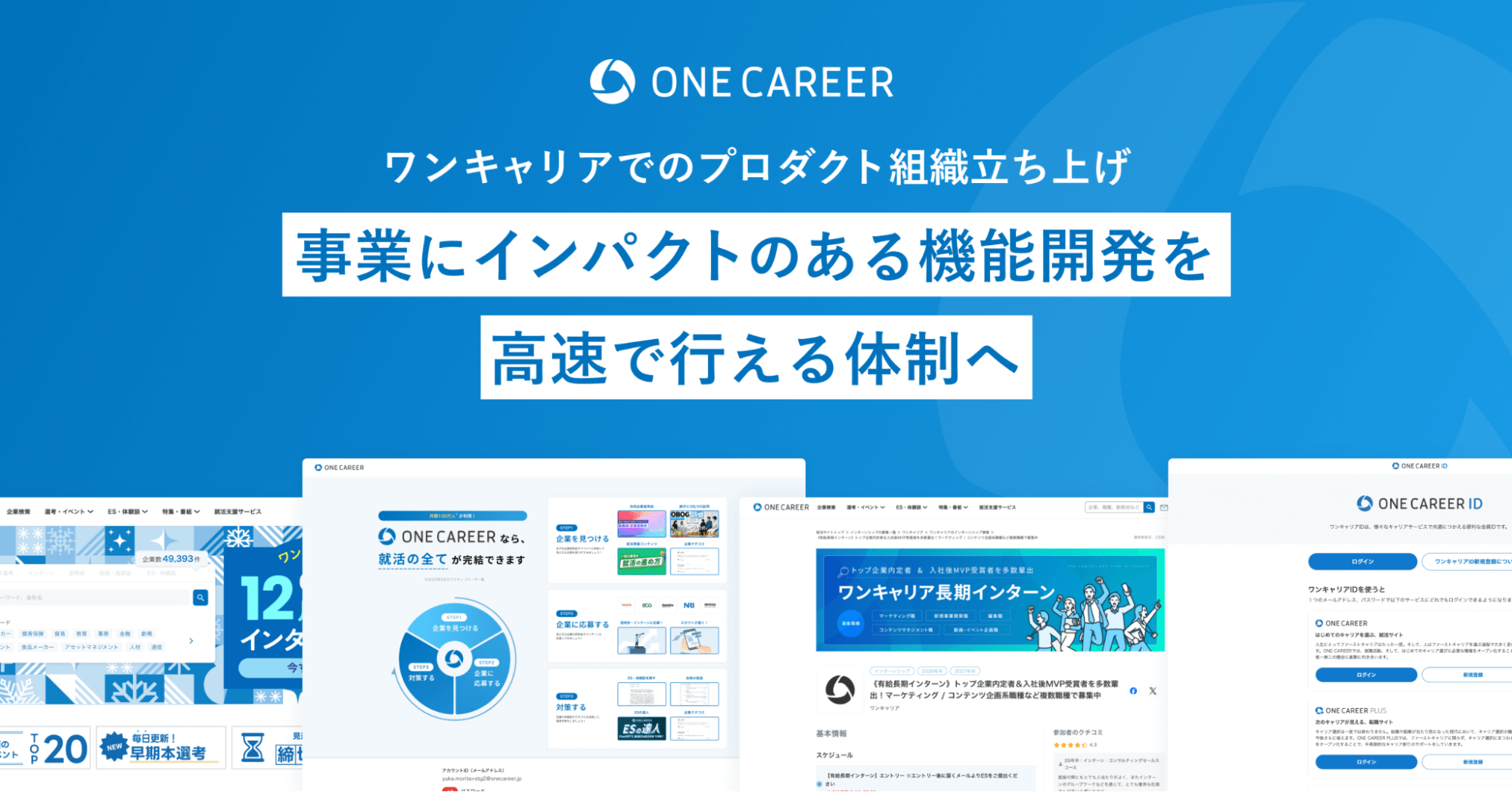ワンキャリアは新卒採用と中途採用の大きく2つの事業を運営しており、私たちは、双方を横断してプロダクト戦略・開発を担っています。
ワンキャリアでは、「エンドユーザーファースト」をコアバリュー(創業以来大切にしてきた行動指針)の1つとして掲げ、プロダクト開発においてもユーザー理解を徹底することを心がけてきました。
今回は、特にプロダクト開発の現場でどのようにユーザー理解を深め、アウトプットにつなげているのか。その具体的な取り組みを、プロダクトデザイン事業部の事例を中心にまとめたいと思います。
ワンキャリアが取り組む就職・採用領域には、いまだ多くの課題が残されています。
その大きな要因の一つは、候補者と企業間で情報の非対称性があることです。候補者は、自分に合った企業を選びたくても、企業文化や実際の働き方を十分に把握できないまま意思決定をせざるを得ないケースが多くあります。その結果、入社後のギャップにつながることも少なくありません。
一方で、新卒採用の人事担当者は一般的に1年から3年ほどで入れ替わることが多く、成果指標が短期的になりがちです。その結果、とにかく数多く施策を打つというアプローチに偏りやすく、多忙な一方で、成果が生まれにくいという構造にあります。
本来は、中長期的な視点で「XX社と言えば〇〇が魅力的である (だから、XX社で働きたい)」といった選ばれる理由を示すこと、つまり実態にあった適切な採用ブランドを構築することが求められます。
ここで、採用ブランドは、マーケットからの評価の総量によって定まるものと考えられます。
例えば、XX社は「社風・人が魅力的」「サービスが魅力的」など、候補者からの評価が集積されることで、企業の強みが差別化されたり、今まで知らなかった強みに気づくきっかけとなるイメージです。 ワンキャリアでは、このマーケットからの評価を「クチコミ」によって可視化し、収集可能にすることで、より強固な採用ブランドを構築しやすくするというアプローチを提供してきました。
さらに、この採用ブランドを向上させるには、「良い候補者体験」を生み出すことが不可欠だと考えています。候補者にとって魅力的だと思える企業ほど良いクチコミが広がり、結果として良い採用ブランドが構築されるからです。 「良い候補者体験」が共通の指標となれば、採用人事も「とにかく手数を打つ」という短期的なアプローチの繰り返しから解放されると同時に、候補者も本当に自分にあった確からしいキャリア選択がしやすくなっていくと考えています。
ワンキャリアでは、このような考えのもと、「どうすれば良い候補者体験を提供できるか ( ≒ 採用成功・就職成功をどう実現できるか)」という問いに真摯に向き合い続けています。
そのために、候補者や採用担当者の課題を深く理解し、検証しながらサービスに反映することを大切にしています。
では、ワンキャリアでどのようにユーザー理解を深めているのか。新卒向け事業領域でプロダクトマネジメントやデザインを担う私たちが実践している、具体的な取り組みをまとめます。
※ プロダクトデザイン事業部における組織体制や開発プロセスについては、こちらに詳細にまとめられています。あわせてご覧ください。
新機能の検討や既存機能の改善を進めるにあたり、社内のドメインエキスパートへのヒアリングを頻繁に実施しています。
ここで言うドメインエキスパートとは、採用業務に精通したスペシャリストを指します。ワンキャリアでは、社内の採用人事やCSが該当します。
お客様に直接ヒアリングさせていただくこともありますが、ワンキャリアでは採用業務や採用の成功要因を常に科学しているドメインエキスパートが多数在籍しているため、彼らにヒアリングを行うことで、素早く検証サイクルを回すことができます。
対面でヒアリングを行うだけでなく、実際に採用業務を行っている様子を隣で観察させてもらうこともあります。
例えば、スカウト送付をどのようなステップで行っているのか、ATSにどのような情報を入力しているのかといった作業を観察することで、業務フロー上の課題を把握できます。さらに、グッドケースをお客様も実践できるように、プロダクトにどのように反映すべきかを考える材料を得られます。
また、営業担当者から学べることも非常に多くあります。提案資料やトークには、採用担当者が何に最も課題を感じ、何に価値を感じるのかといった情報が詰まっています。それを把握することで、プロダクト改善の糸口を見つけられます。
自身が採用担当者として実際に採用業務に携わることにも、積極的に取り組んでいます。
採用業務の具体的なフローや、その中で候補者はどのような期待を持っているのか、どのようなコミュニケーションを取ると良いかといった肌感は、実践しなければ分からないことも多くあります。
例えば、プロダクトチームの採用面談はほぼすべて自分たちで担当しますし、新卒採用の面談にも参加します。スカウト送付や面談後の評価、ATSの運用なども行います。
また、新卒採用におけるインターンシップの企画運営やメンターとして携わることもあります。
扱うサービスによっては、現場の業務に触れることが難しい場合もあります。しかし、ワンキャリアは就職・採用領域のサービスを提供しているため、社内でも実際に業務に触れられる機会が数多くあります。
こうした環境を活かし、自身が採用担当者として矢面に立って業務に携わることは、ユーザー理解を深めるうえで非常に重要な機会となっています。
採用業務への理解と同様に、候補者となる学生への理解も重要です。そのため、学生を対象としたインタビューも頻繁に実施しています。
ワンキャリア上で募集をかけてインタビューさせていただく場合もあれば、社内の学生インターンにインタビューを実施することもあります。ワンキャリアには多くの学生インターンが所属しているため、社内でユーザー層である学生に迅速にリサーチが可能です。
特に、プロトタイプ検証の際にインタビューを行うことが多く、多い時には1日に2〜3件実施しながら高速でプロトタイプを更新しています。
例えば、ONE CAREERの会員登録機能をリニューアルした際には、短期間のプロジェクトでありながら30名以上の学生にインタビューを実施。並行して素早くデザイン改善を進めた結果、目標としていたKPIを大幅に上回る効果を得ることができました。
インタビューを通して得た情報は、チーム内でローコンテクストで共通認識を持つことを心がけています。
チーム内で分担してインタビューを実施した後にSlackで内容を共有することが多かったのですが、抽象化された情報では気付けない課題があったり、認識のズレが発生したりすることもありました。
そこで、対面でインタビュー結果を共有しあいながら、「なぜその課題が生まれているのか」「共通した課題を持つ方はどんな人か」といった解像度を高めるための振り返り会を実施するようにしました。
この振り返り会は不定期に行っていますが、抽象的な理解に留まらず、ローコンテクストで共通認識を徹底することは、チームでユーザー理解を深めるうえで重要だと考えています。
1〜4は、採用担当者や学生への理解を深めるためのインプットの仕組みですが、一方で、素早くアウトプットへ繋げ、検証サイクルを早めることも重要です。
チーム内で毎日開催している「ペアデザイン」は、そのための仕組みの1つです。
ペアデザインでは、PdMとデザイナーが一緒にデザインを作成します。ペアデザインのためのスケジュールが毎日1時間確保されており、その日に扱いたい論点を決定した後、お互いに意見を出し合いながら仕様・デザインを具体化していきます。
話しながらデザインを作成すると、かえって遅くなるように思われるかもしれませんが、実際にはアウトプットのスピードが大幅に向上しています。
デザイナーだけで作成していると、仕様に悩むことが多かったり、レビューのリードタイムが長くなる場合があります。しかし、ペアデザインでは迅速に問題を解決し、足りない視点を補いながらスムーズにアウトプットすることができます。
さらに、ペアデザインによって毎日アウトプットが生まれ、前述のドメインエキスパートや学生への頻繁なヒアリングを通じて、素早く検証サイクルを回せる状態になっています。
ここまで、プロダクトデザイン事業部で実践しているユーザー理解の仕組みをまとめてきました。ワンキャリアでは、こうした仕組みはプロダクト事業部だけでなく、CSや営業、人事など、さまざまなポジションで徹底されています。
このような徹底したエンドユーザーファーストによるサービス開発は、ONE CAREERにおける「学生の利用率/使いやすさ1位(*1)」「学生が最も利用した就職サイト2位(*2)」といったユーザーからの高い支持を得るとともに、事業成長を支える大きな要因となっています。
また、以前Cocodaで公開した事例のように、プロダクト組織として推進するプロジェクトで成果を上げることができています。これらの成果は、今回まとめたユーザー理解の仕組みに大きく支えられていると考えています。
就職・採用領域のプロダクトには既存の型があり、新たにプロダクトを通じて変えられる範囲は少ないと考える方もいるかもしれません。しかし、そうではありません。
この領域には依然として多くの課題があり、就職や採用の成功はまだ十分に科学されていません。それらを解き明かし、「人の数だけ、キャリアをつくる。」ことがワンキャリアのミッションです。
人生の多くの時間を投資する「キャリア」の意思決定に寄り添い、課題を深く理解し、新たな体験を提案していくことで、この領域を変えていくことができると信じています。その中で、デザインが貢献できる範囲は非常に大きいと考えています。
今後も、今回まとめたエンドユーザーファーストを体現するユーザー理解のプロセスをさらに磨き、価値あるプロダクトを提供できるよう、引き続き取り組んでいきます。