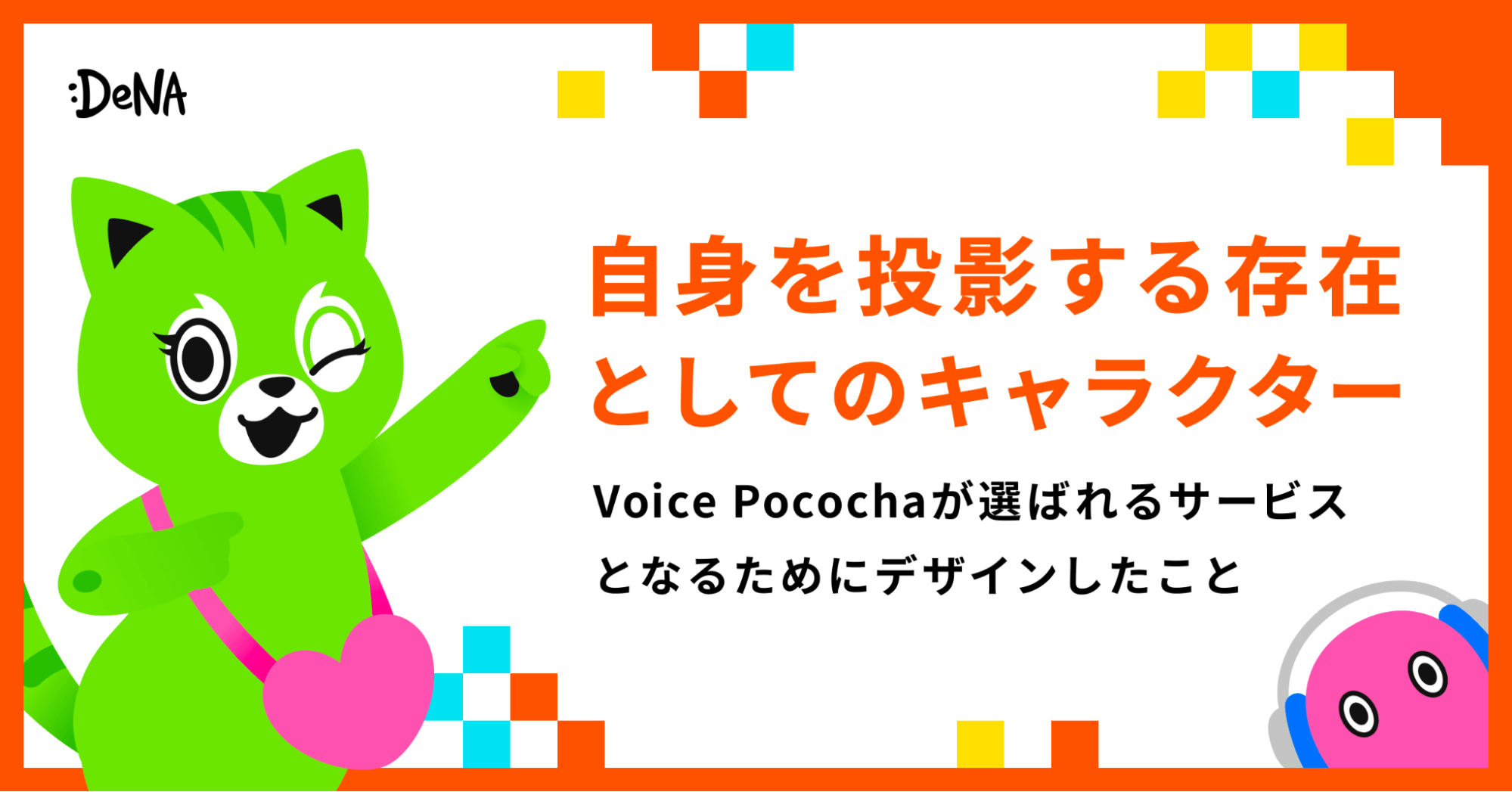DeNA デザイン統括部 プロダクトデザイン部 部長の久田です。DeNAデザイン統括部は約80名が所属し、「プロダクトデザイン部」「コミュニケーションデザイン部」「エクスペリエンス戦略室」の3つの部門で構成されています。
2023年4月にDeNAデザイン統括部におけるデザイナーの評価指針をまとめたキャリアシートを刷新し、私は特にプロダクトデザイナーを対象とした内容を策定、運用しています。
キャリアシートを刷新した主な狙いは以下であり、事業に深くコミットしながらデザイナーとしての武器を存分に活かしていけること、それらがしっかりと報われる制度となることを目指しています。
時代・環境に合わせた形で更新することで、レベルアップやキャリアパスをより具体的にイメージできるようにする
グレード毎に求めるレベル感を再定義することで、事業に貢献するプロダクトデザイナー像を認識し、PDCAを回しやすくする
組織規模も大きく、関わる事業も幅広いDeNAデザイン統括部において、なぜデザイナーの評価指針を刷新することにしたのか、どのように運用しているのかについてまとめたいと思います。
プロダクトデザイン部は「デザインを武器に、事業部と一体となって戦略を推進する」ことを役割として担い、サービスの体験設計やUIデザインに専門性を持つデザイナーが集まっています。
DeNAにはエンタメ領域から社会課題領域まで、フェーズの異なる様々な事業があり、会社の中に数多くのベンチャー企業があるイメージです。その中で、各事業部に入り込んでその事業に関わるデザインを推進していくことを役割にしています。
https://design.dena.com/filecount/pdf-culture-deck-2024/
デザイン以外の業務、例えば採用、育成、評価などはセントラルのデザイン組織となるデザイン統括部が担うことで、事業部にアサインされたデザイナーが事業推進に集中しやすいようにしています。
そのため、プロダクトデザイナーに対する評価としても「事業部と一体になって、デザイナーとしての武器を活かして成果を出せるか」が重要なポイントになります。
前提としてDeNA全体では、「成果評価 (事業の成果)」と「発揮能力評価(個人の成長)」の2軸で評価され、グレードが決まるようになっています。 その中で、4年ほど前にデザイナーを対象に目標設定や評価を適正に行えるようにグレードごとの能力定義を行ったものがキャリアシートであり、メタスキル・ハードスキル・ソフトスキルの3軸で細分化していました。
運用を開始した当初はこのキャリアシートで問題はなかったのですが、徐々にデザイナーに求められる役割が広がる中で、以下のような課題が生まれるようになっていきました。
本来は事業戦略や自身のキャリアなどを総合的に考えて目標を考えるべきだが、次のグレードで定義されたスキルだけを切り取って自分の目標としてしまうことがあった。
本来は評価するべき発揮能力だったが、その発揮能力についてキャリアシートに書かれていないという観点から評価されない事例がちらほらあった。
デザイナーの業務範囲が広がってきており、キャリアシートに書かれている項目だけでは評価しづらくなってきていた。とはいえ、書き足していってもイタチごっこになるだけの状況。
このような背景を元に、現在やこれから求められる役割からキャリアシートを更新し、現場のプロダクトデザイナーが「目指すべき方向性」をより具体的にイメージして行動できるようにしたいと考えました。
刷新したキャリアシートでは、デザイナーとしての共通スキルセットで括った内容ではなく、事業部内でどれだけ責任・裁量を広げられているかを重視した設計にしています。
元々のハードスキル / ソフトスキル / メタスキルの3軸も残してはいますが、「案件規模」「期待される役割・成果」「事業部側のカウンターパート」という軸から、グレード毎に事業部内でどれくらいパフォーマンスを発揮し、信頼を獲得しているのかというレベル感を具体化しています。
グレードが上がるごとに、案件規模、役割と成果、カウンターパートが徐々に高度になっていくような設計であり、各グレードごとのイメージ像も細かく設定しています。
各項目の内容イメージは以下のようなものであり、単純にスキル(技術)が習熟していくだけではなく、より難易度の高いことを任されたり、そこでの実績が出せていくほどグレードが高まっていくような流れとなっています。
実際の目標設定・評価のサイクルとしては、次のような運用にしています。
評価タイミングは上期・下期の年2回
期初にグループマネージャーと相談しながら個人目標を設定
期中には2回グループマネージャーとチェックインを実施し、目標に対する進捗を確認
グループマネージャーの1次評価と、部長の2次評価を総合して最終評価を決定
このようなサイクルの中で、特にポイントとなる機会について紹介します。
目標設定は上期・下期で行っており、その流れは以下のようになっています。
その期の事業戦略をもとにグループマネージャーがデザインチームの戦略を立てる
その戦略と目指すキャリアを鑑みて、メンバー自身で目標を立てる
グループマネージャーとの面談を通して目標をFIXさせる
目標設定の考え方は、事業的なMUST(求められていること) に対して、個人のCAN(できること)とWILL (自分のチャレンジとやり切る意思)が強く重なる点で設定することを基本方針としており、その重なりをうまく捉えるために、グループマネージャーとの面談やキャリアシートを活用してもらうようにしています。
この考え方は、DeNAデザイン統括部でのアサインの仕組みに関する事例でも詳しく書かれています。
上期・下期のそれぞれの期中に2回、チェックイン(グループマネージャーとの1on1)を実施するようにしています。チェックインでは、個人の目標達成や成長を促すために進捗状況や方向性についてのすり合わせを行います。
また、アサイン先の事業状況も刻々と変わっていくので、その状況に応じて個人に求められる動きも変わっていきます。そのため、事業状況と個人の目標をすり合わせていく重要な機会でもあります。
期末での評価は以下のような流れで実施しています。
メンバー自身の振り返り
振り返り内容を基にグループマネージャーとすり合わせ、1次評価を行う
周囲メンバーからのリファレンスをもとに、部長が2次評価を行う
グループマネージャーによる1次評価に加えて、部長 (プロダクトデザイナーの場合は、プロダクトデザイン部 部長である私を指します) が2次評価を行う理由は、アサイン先の事業状況に依らず、デザイナーという軸で適正な評価をできるようにするためです。
前述している通り、DeNAには幅広い領域の事業があり、立ち上げフェーズの事業もあれば、グロースフェーズの事業もあります。また、事業の成長度合いもさまざまなので、その中で個人が出せる成果の大きさにもばらつきが生まれやすいと考えています。
そのため、セントラルのデザイン組織となるデザイン統括部の部長陣が2次評価を行うことによって、デザイナーという軸できちんと評価できるようにしています。
このような方針・運用で目標設定と評価のサイクルを回すようにしていった結果、求められる役割に応じた目標設定や振り返りの解像度が高まったり、その過程で視野・視座が高まりやすくなっています。
最後にDeNAのプロダクトデザイン部で、実際にどんな方や取り組みが高い評価を得ているのかの一例をご紹介します。
例1 : コア体験の定義からUIUX・ブランドを構築することで、アプリの成長をリード 音声ライブ配信アプリ「Voice Pococha」の立ち上げにおいて、VIやUIUXデザイン、Webデザインなどをほぼ一人で担当。さらに、Voice Pocochaが選ばれるサービスになるためには「自身を投影する存在としてのキャラクターが必要」と定義してキャラクター開発も推進。リリース以降、DL数やDAU数など各種KPIも順調に成長し続けています。
例2 : 可視化の強みを活かしてMVP構築・顧客理解をリードし、チームのレバレッジを向上 事業責任者ほか数名のチームで、エニカオーナーズボードのプロダクト立ち上げを推進。プロトタイピングやカスタマージャーニーなど、デザイナーとしての可視化の強みを活かしてチーム内での議論を活性化することで、リリースやその後のグロースに対しても大きく貢献しています。
例3 : 領域を越境し、ステークホルダーを巻き込んで価値貢献を行う DeNAヘルスケア事業部において、プロダクトデザイン領域に留まらず、組織課題の解決のためにカルチャーデッキの企画・制作を推進。デザイナー、人事・広報、事業部長、部長など、さまざまなステークホルダーを自律的に巻き込んでいくことで、採用・広報面での価値貢献に繋がっています。
それぞれ強みとする領域もアサインされた事業の状況も異なりますが、事業成長に目線を向け、デザイナーとしての武器を活かすことで大きな価値貢献に繋がっている例だと考えています。
DeNAデザイン統括部のミッションは「DESIGN FOR DELIGHT」であり、DeNAにおけるあらゆる事業戦略をデザインという切り口で推進することを役割としています。
今でこそ全体で約80名が所属し、プロダクト・マーケティング・ブランドなど様々な領域で、デザインの重要性が浸透してきていますが、これらはDeNAにデザイン組織ができてから10年以上にわたって、事業への貢献方法を模索し、実践を積み重ねてきた結果に他なりません。
https://design.dena.com/filecount/pdf-culture-deck-2024/
プロダクトデザインという領域に絞って見てもその位置づけは変わりませんし、事業会社に所属する以上、スキルをどれだけ高められるか、どれだけ多くのタスクを消化できるかよりも、どれだけ事業をグロースさせられるかに目線が向いているべきです。
ただし、どのような振る舞いや成果が求められるかは、時代や会社・事業のフェーズによっても変わっていきます。そうすると、組織と個人の期待値が少しずつずれていって、どんなものさしで良し悪しを測っているのかがあいまいになってしまいます。
適正な期待値で、組織としても個人としても良いパフォーマンスができるようになり、その努力に対してしっかりと報えるような状態にするためにも、今回のような評価の仕組みをアップデートしていく試みは重要だと考えています。
評価やキャリアパス設計も1つのプロダクトと捉え、これからも事業とデザイナーがうまくフィットしながら進んでいけるようにしていきたいと思います。