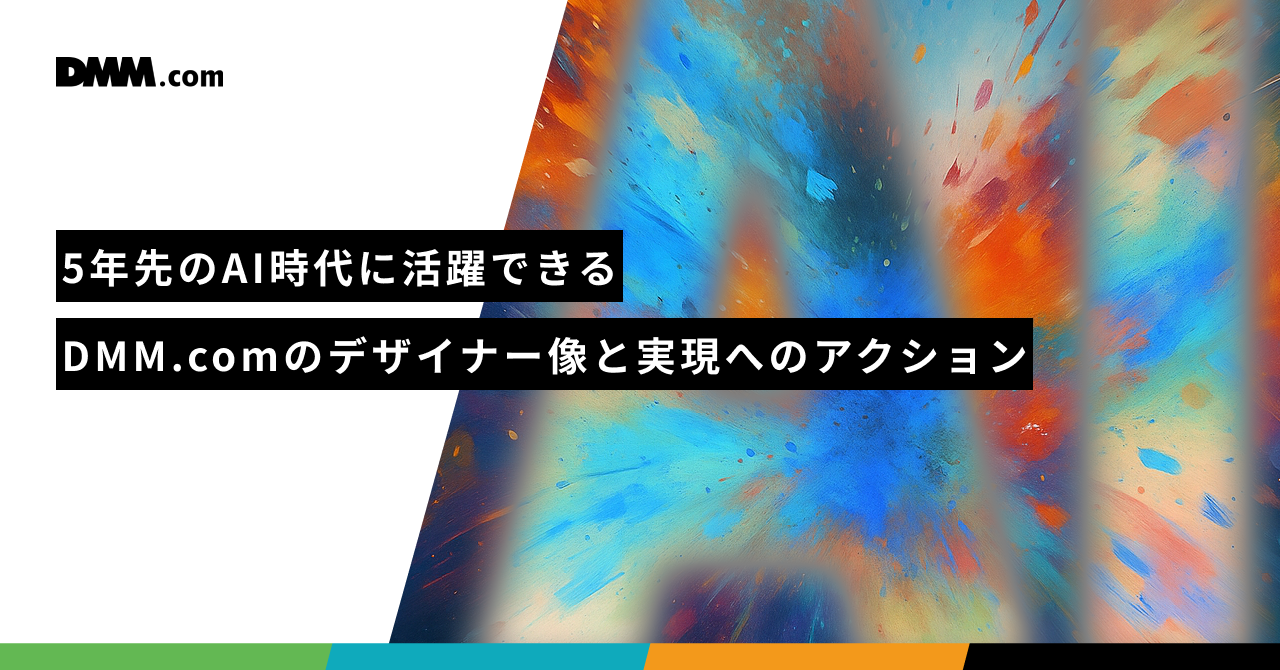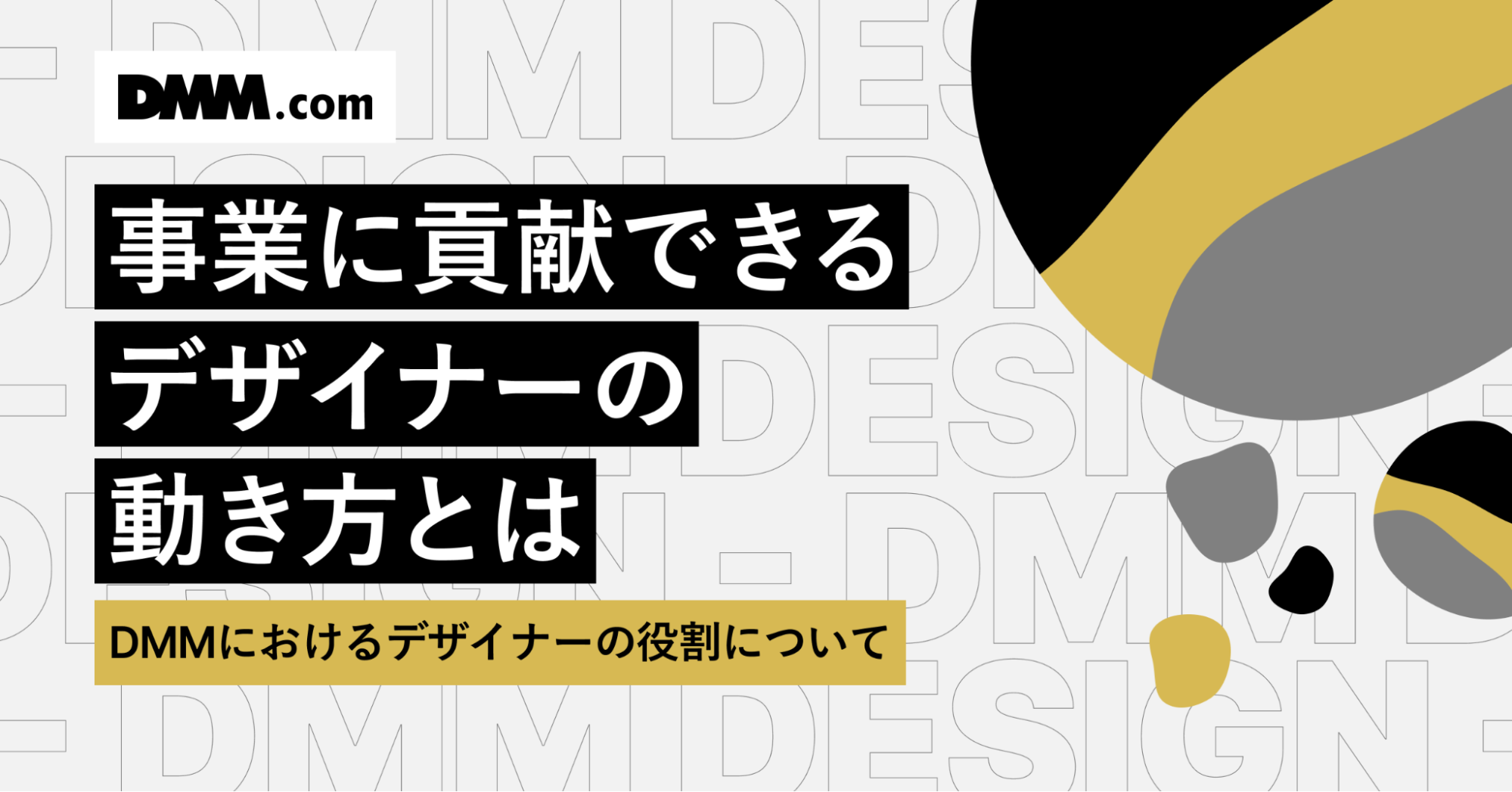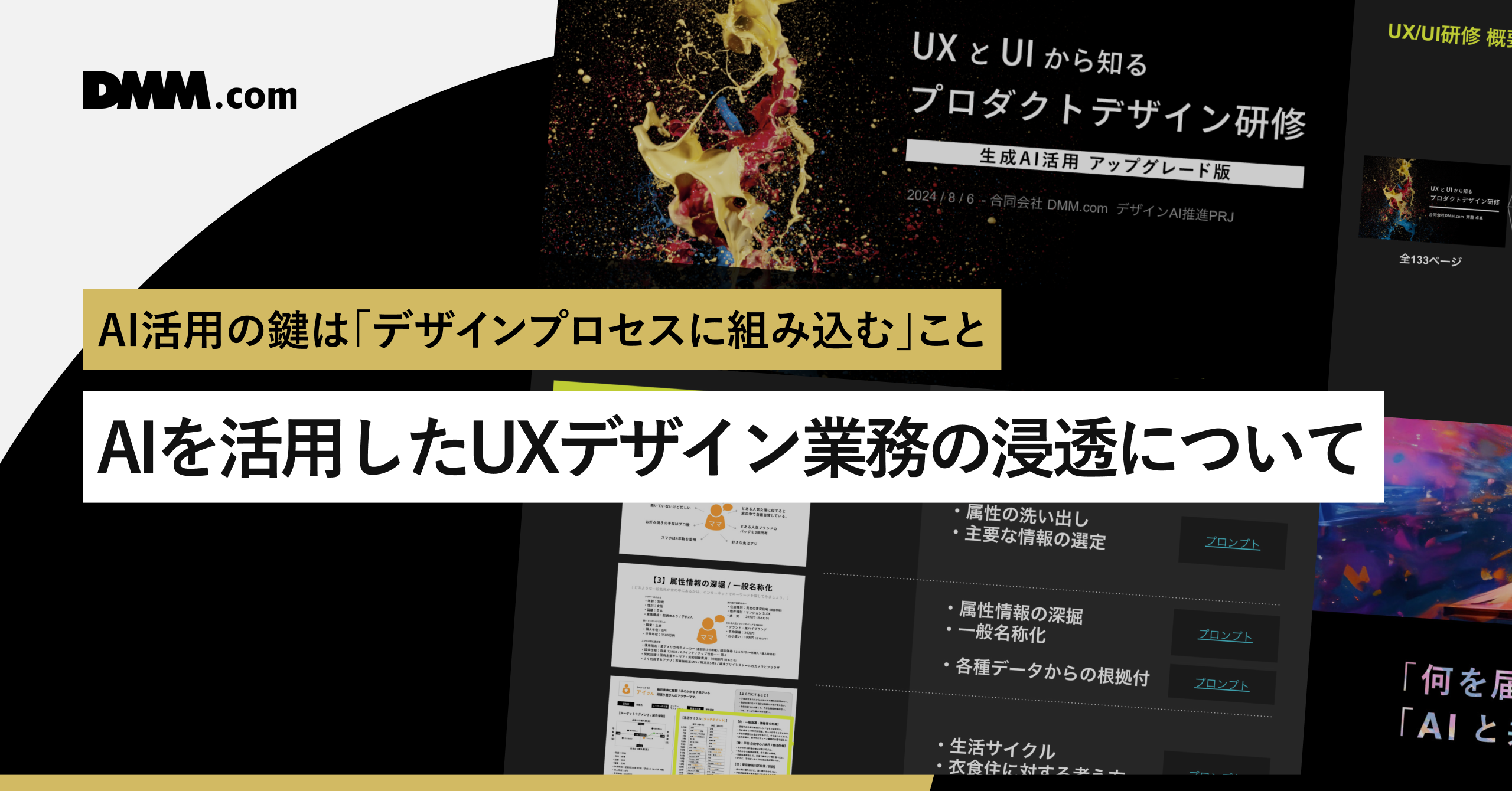DMM.com (以下、DMM)では、デザイナーが生成AIを積極的に試すことを促し、使える部分で積極的に活用する文化を推進しています。
前回は、Cocodaに5年先までの「デザイナーAI活用人材ロードマップ」の設計背景や、その内容についてまとめた事例を公開しました。
今回は前回の事例に引き続き、DMMデザイナーのAI活用状況の進展をご紹介できればと思います。
テーマは「AIを活用してデザイナーの商売的な想像力を拡大するための、AI時代のワークフロー」です。
とりわけデザイン領域で、2024年に設計したAI時代における「デザイナーAI活用人材ロードマップ」での想定と市場動向は似たように推移していると考えています。(詳細については、前回の事例をご覧ください。)
例えば、動画でのAI生成のハードルが下がり、短時間で生成を試す方が増えたり、多くの生成AIでの画像や音声の解析または認識、自然言語の意図を組んだ生成精度が順調に向上していたり、またデジタル広告での販促物の量産化については、作業効率化を念頭においた機能の改善や追加の動きも一部見られていることが挙げられます。
一方で、LLMやマークアップ領域のような、言語情報を前提とした生成AI の業務導入範囲の大きな拡大はまだ起こっておらず、背景としてAIによってデザインデータを開発へ反映しやすくする、ノンコード実装の可能性の追求するといったデザインソリューションがいかに作業効率化を上げられるかに注力しているからではないかと見ています。
DMMではこのような状況も想定した上で、デザイナーが追う2025年のテーマに「“ 商材・事業・市場 ” の理解をAIで強化し、中期洞察をインハウスデザイナーならではの視点で行う。」を掲げており、デザイン部 部長の齊藤が運営する複数の全社のデザイナーの横断的な枠組みを通じて浸透しています。
まずは、テーマの前半である “「商材・事業・市場」の理解をAIで強化する” という部分について解説します。
DMM.comでは、「商材・事業・市場」の理解とは、デザイナーが複数の領域の“プロ”と正しく意見交換し協業する上で組織力を正しく発揮できる力と定義しています。
私たちは、AI活用以前から、この「商材・事業・市場」の理解にチャレンジしてきています。さらに、社内研修やOJTを実施しながらこの考え方を浸透させてきました。
昨年は、LLMの生成AIを活用したUX検討フローの社内研修を行い、AIによってこの「商材・事業・市場」の理解をさらに押し進められる手応えを感じたことから今年の方針決定に至っています。
では、なぜ「商材・事業・市場」の理解を強化する必要があるのでしょうか。
それは、AI時代では、事業とデザインを「俯瞰する力」と「接続する力」がさらに求められるようになると考えているためです。
これまでもデザイン業界は、印刷からDTP へ デジタル媒体へと進化し、マルチメディアの媒体の多様化に加えてリアルタイム性やインタラクティブ性の向上に伴いながら、世の中の進化の中でデザインは活躍の幅を広げてきました。
そしてAI時代となった今、目の前で作っているデザインが影響を及ぼせる接続範囲は「AIからAGIに進化する中で格段に広がる」と考えています。
このような状況下で、仮にデザインの影響範囲を俯瞰する力がないとすれば、 成果が期待できる領域にデザインが接続できなくなることが予想され、利益に響きづらいデザインを作り続けてしまうリスクが高まると考えています。
特にDMMデザイナーはインハウスであることから、より一層つくるだけでなく、AIを活用して「デザイナーの商売的な想像力」を拡大させていくことが期待されているはずです。
AIからAGIに進化する中で考えるべき事が格段に広がる、といっても「どの商材」を「どの事業(サービス)の戦術」で「どのように市場に戦略的に展開」して利益貢献するか?を全て理解または把握することは困難です。さらにAIが進化すると、その前提や状況が変わるスピードがどんどん上がっていくと予想しています。
では、どうすべきなのか。「どの部分が事業(サービス)にとって重要な点なのかを知るために、事業計画書を読み込む」ことから始めていくのがよさそうです。
“商売を考えるプロ”にもさまざまな職種の方がいて、毎年作ったり、アップデートしたりする、アレです。事業がどのようになっていきたいかが、かならず書いてあるはずです。もし、書いていないのであれば追加で聞いて書き足していきましょう。
その上でわかった注力ポイントに対して、どのような販売手法やデザインが最適かを考えていくことで有効なアプローチになる可能性が高まります。
このようにAGIのサポートを受けながら「商材・事業・市場」の理解を進めていくことで、デザイナーの役割は、より抽象度の高い領域へとシフトしていくと考えています。
次に、 後半のテーマ「中期洞察をインハウスデザイナーならではの視点で行う。」についてです。
ここでは、「中期」とは2〜3年後を指しています。では、なぜこの中期洞察を行う必要があるのでしょうか。
それは、近い将来AGIによって見ようと思えば「広く・速く・細かく事業全体を見れる状態」に至った時に、デザイナーもその力を使い、議論に参加し続けるためです。事業サイクルや、AI技術の進展のスピードは速く、いざ時が来てから始めるのでは遅いはずーー。だからこそ、今から準備を開始しました。
具体的な中期洞察の観点は、「3年後の事業」「3年後のAI」の2つに分けられます。
まず中期洞察すべきなのは、事業(サービス) にとっての3年後です。
事業における3年サイクルとは、「PoC(概念実証)」のような事業を除くと、要するに「3年後に儲かっているために、逆算すると今何をすべきか」という考え方です。
今作ったものが来年も有効な資産になる、もしくは2、3年後の完成に向けた最初の一歩であるようにしなければ、事業運営の責任者からすれば、限りあるお金を刹那的にデザインや開発へ投資する理由は薄くなってしまうでしょう。
例えば、毎年の事業のキックオフなどで「毎年言っていることが変わっている」と思う方もいらっしゃるでしょう。それは方針転換であり、事業を取り巻く「商材」「市場」の変化に対応するための事業計画のチューニングであることが多いため、このズレを補正しないのは危険です。
さらに変化は1年に1度であるとは限りません。常日頃起こりうることです。だからこそ、なぜ事業計画が変わったのか、デザイナーの立ち振る舞いをどう変化させるかは、常に意識し、振り返れるようにしておくべきなのです。
同時に、AI(技術) にとっての3年後も予測していく必要があります。
これは、冒頭にお見せした「デザイナーAI活用人材ロードマップ」がベースにあるものの、本当にその通りになるかわかりません。もちろん、真面目に考えて作ったものの、AIの技術の進展のスピードが早く突飛なのです。
事実、AIに向き合い始めた2023年当時と現状とを比較すると、技術が進んだ領域も、思った以上に進まなかった領域もあります。ただ、現状では冒頭にお見せした「デザイナーAI活用人材ロードマップ」と市場動向は大体予想通り推移しています。
今後、「デザイナーAI活用人材ロードマップ」の2026年以降の見通しを変更する可能性もあります。だからこそ、3年後を起点に未来を見通すことを継続し、どのようなデザインを世の中に届けられることに価値があるのかを先読みすることが、年を増すごとに重要になっていくと考えています。
「商材・事業・市場の理解を強化し、中期洞察をインハウスデザイナーならではの視点で行う。」というテーマに対して、DMMのデザイン組織で行っている具体的なアクションについてもお話しします。
現在はAGIを活用して、さまざまな事業の中期計画を収集しつつ、デザインニーズやアプローチを見つけていくことから実施しています。
1. 【担当割】事業戦略の収集と再確認
2. 【俯瞰】デザインニーズの把握
3. 【接続】有効なデザインアプローチの分析
実際の作業は以下のようなシートで行っています。画像に黒塗りが多い理由は、DMMの多種多様な事業戦略に基づく「機密情報 」であるため、ご了承ください。この表の1行が1事業となっており、AIの力を借りて「商材・事業・市場」の理解を深めるフローとなっています。
実は、このキャプチャは全工程の前半であり、1年を通し後述する後半の工程も含めて推進しています。
齊藤直轄のデザインセンター、デザイン部は、年間40以上の組織へデザイン管轄や支援をしており、3つのグループのうちの1つのグループ(ここだけでも20近くの事業体と向き合っている)のドキュメントで、残りのグループも類似の取り組みを行っています。
デザイン部の中でも支援規模の差はありますが、年間40以上の組織とお仕事しておりデザインの管轄をしている事業やプロダクト、支援をしているケースもありその関わり方も多種多様です。
ここからは各工程(シートの列の内容)で何を行なっているのか?を解説したいと思います。
まずは、事業戦略を収集し再確認することから始まります。
ここでの工程は大きく分けると2つに整理できます。
▼ 工程1: 向き合いの洗い出し
工程の狙い:情報収集漏れの防止と、デザイナーの当事者意識の醸成
集める情報
事業情報:所属本部・事業(またはグループ会社)体 / 事業名
サービス情報:保有プロダクト(サービス) / 主要商材
デザイン担当者(情報収集担当者):デザイン担当者 / デザインリードのサポート担当
事業担当者:ヒアリング先担当者名
▼ 工程2: 事業情報の収集
工程の狙い:年単位で事業変化を確認
集める情報
昨年度まで狙っていた市場のポジション (As-Is):昨年度事業戦略の概要 / 事業戦略資料
今年度から狙うポジション (To-Be):今年度事業戦略の概要 / 事業戦略資料
昨年対比の情報:影響規模 (売上・利益 / 年+成長率)
次に、事業状況を俯瞰して、デザインニーズがどこにあるのかを把握します。
ここでの工程も2つに分けられます。
▼工程1: 今年度方針の比較
工程の狙い:事業状況としてデザイナーが寄与できる場面か確認
集める情報
昨年度から今年度の主要な方針の変更内容
▼工程2: 期待の把握
工程の狙い:事業が現在想定するデザイナーの活動範囲を整理
集める情報
今年度の重要なデザインの業務内容
今年度予定されている予算上の稼働時間(想定)
最後に、中期的な事業予測やデザインニーズに対して、どのようなデザインアプローチを行うことでインパクトがあるのかを分析します。
▼工程1: 向き合い(情報収集する担当者)の洗い出し
工程の狙い:利益につながるデザインのヒントを見逃さない
ここで実施すること
「商材・事業・市場」のAI補助による考察
ここまでの情報収集・分析に基づいて、適切な担当者とコミュニケーションを取り、デザイン主導で中期的なデザインアプローチを実践していきます。
すでにこのようなプロセスを体現できているメンバーを中心に、すべての工程で、各グループの特性や業務内容・前年度までに積み重ねた実績を踏まえたロジックとプロンプトを構築し、実施してもらっています。
ここまでお読みいただいた方の中で、「これは責任者またはリードの仕事では?」と考えられる方もおそらく多くいると思います。
しかし、DMMではこれを全てのインハウスデザイナーに求める基準として設定すべきだと考えています。なぜ担当者までやるべきなのでしょうか。その理由は3つあります。
近い将来、これらの工程はAGIが代行してくれるようになると考えています。情報収集と集約をものすごい量とスピードでAGIが行うため、個人が情報を占有できなくなる時代です。
一部の責任者やリード人材が、暗黙知で理解と整理をし、タスク化とデザイン担当者へ依頼していた一連の流れは、これからは「デザイン担当者一人一人がAGIとペアを組んで自律的にできる事が当たり前」になることを想定しています。
そうなれば、このプロセスを実行する難易度は低くなり、責任者またはリードでなくても、業務を担うことができるようになるはずです。
AGIは情報収集、集約、さまざまな観点からの提案をしてくれるようになるでしょう。しかし、その内容を精査し「意思決定」するのは、デザイナーの一人一人になると考えているからです。
例えば、人の意思を無視してAIが暴走し続けたらーー。大変ですよね。 そうならないように、意思決定は人間がするように、AIの開発者は幾重にも厳重なセキュリティを施しています。
つまり、AGIがどれだけ発展しても、そこを判断する人間は必要になるのです。となると、現場も含めて、全てのインハウスデザイナーに数年後の事業全体まで見通したデザインアプローチの提案ができる力が必要だと思っています。
DMMには60以上の事業が存在していることも、この構想が実現可能だと考える理由の一つです。
多種多様な事業と、そこの中での試み。成功も、失敗も、得られたものを支援先の事業や社内各所にいるデザイナーの皆さんとも協業を通して広げていくーー。このようなことが実現しやすくなるのがAGIです。
機密情報は慎重に取り扱うべきですが、業務上で共有可能な組織設計を通じて得られる成果への期待が大きくなっています。(情報が貯まれば貯まるほど、AGIの精度が高まるため)
「領域とわず、何でもやる」「60事業以上を展開する」DMMという環境だからこそ効果が最大化できるのです。
このような取り組みを経て、DMM.comdデザイン組織ではAI活用の文化醸成が大きく進んでいます。
デザイン組織全体でアンケートを実施したところ、約半年前の調査時に比べ、AIの業務活用に大きな伸長が見られました。本事例でご紹介した取り組みに関連する部署や生成AIサービスで特に、顕著な変化が確認できました。
さらに、現在取り組んでいる「中長期を見据えた取り組み」についても軽く触れておきます。今回は詳しく紹介できませんが、今後可能な状況になった際に、事例としてまた公開していきますのでお楽しみに。
前述の通り、この考え方に則りOJTを行ってきたことで、既に実施が進んでいる事業/プロダクトもあります。再点検も兼ねて本フォーマットに情報集約し、他者の知見とする動きをしています。
現段階では公表は難しいのですが、生成AI活用を念頭においた複数の中期UX検討やPoC施策に、私も優先的に時間を確保し、選抜されたデザイナーユニットと挑んでおり、得られた知見の横展開も進めています。
モデルケース人材が「戦術サポート」として、各担当デザイナーのサポートについて、AIによる「商材・事業・市場」の理解とインサイトの獲得を支えています。
まずは、今年度を想定した短期アクションで成功体験を増やす予定であり、この領域からのデザインによる牽引活動の多くは、既にデザイナーが経験している事柄と大きく変わりません。
モデルケース人材を中心にした次のチャレンジとして、中期洞察をできる人材を増やしたいと考えています。既に短期アクションでの実績は十分な方々ということもあり、来年度以降につながる事業やプロダクトの接点の拡充や、関連する複数年度を念頭においた提案、そして予算獲得協力などを強化していきます。
今回は、事例の一つをご紹介しましたが、デザイン組織の方針に基づき、 全社横断の枠組みや参画してくれているリードデザイナーの皆さんの所属元でも試してもらっています。
DMM.comには、新しい時代のデザイン業務にチャレンジしていける土壌があります。ご興味があれば、DMMのデザイン組織についてお話しの機会をいただけますと幸いです。