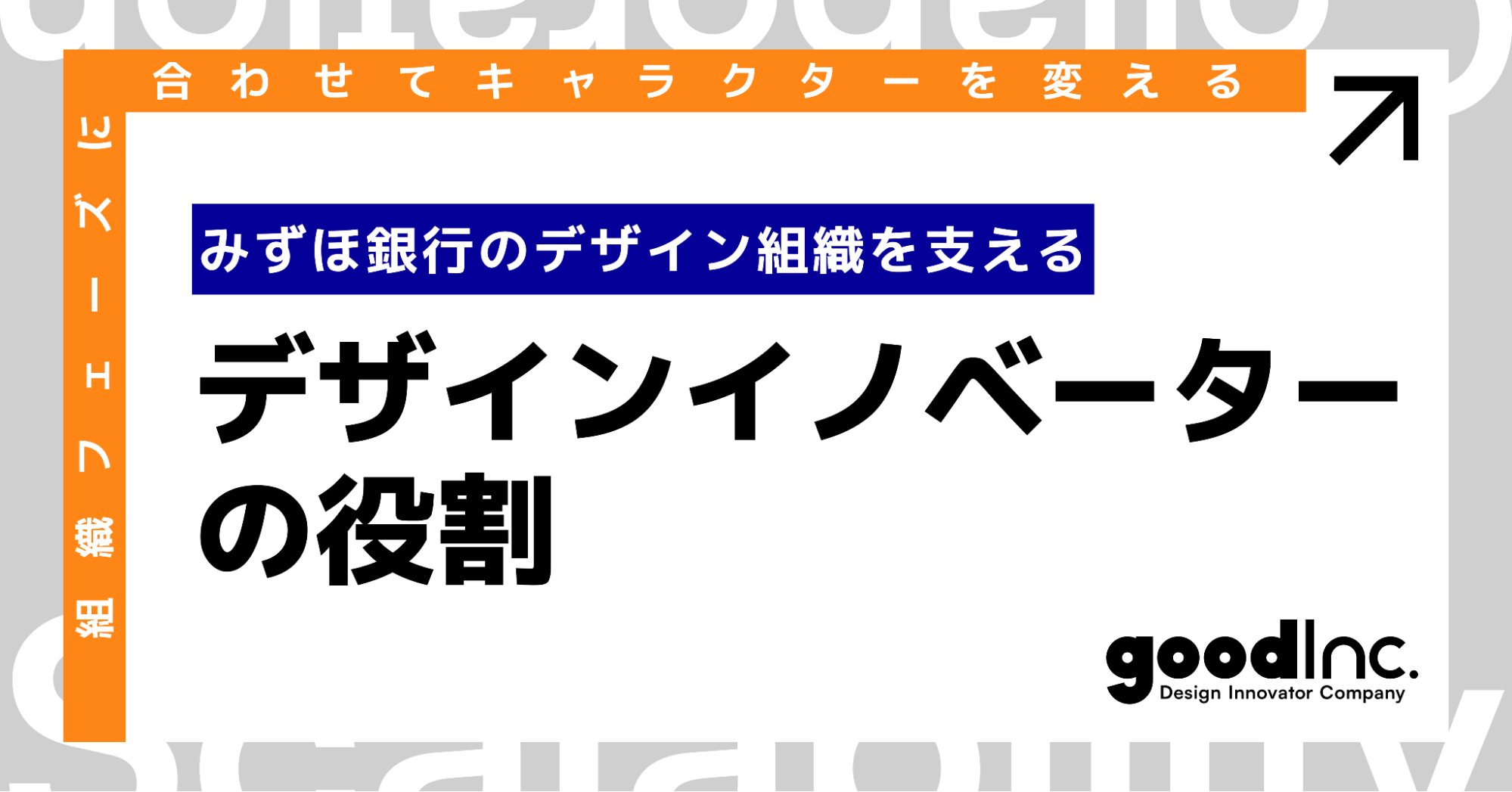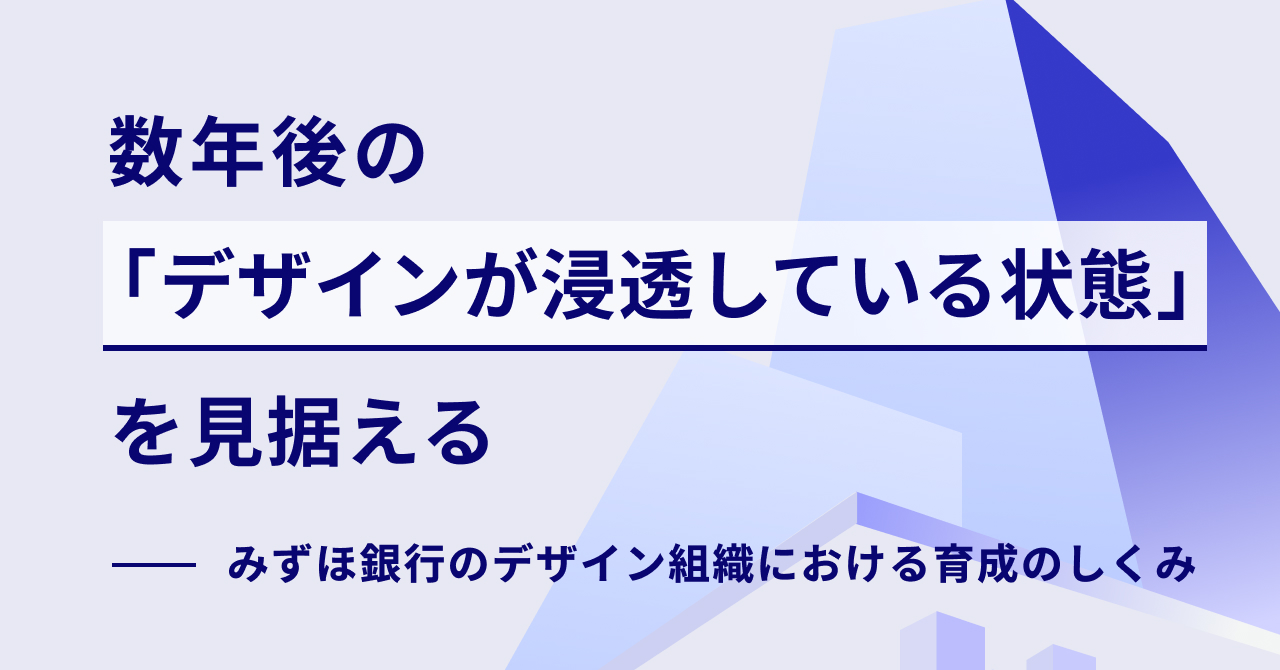みずほ銀行のデザイン組織が立ち上がったのは、2021年の7月です。そこから着実に組織としての規模を広げ、関わる領域も徐々に拡大してきました。
この広がりの裏側では、大企業特有の前提や文脈を踏まえたうえで、ひとつひとつのプロジェクトを丁寧に設計していく案件マネジメントの力が不可欠でした。
社内には多くのステークホルダーがいて、それぞれの立場や目的も異なります。そうしたなかで、どのようにデザインの必要性を伝え、共に進めていける状態をつくるか。そのコミュニケーションと設計の積み重ねが、今の広がりにつながっています。
この事例では、みずほ銀行という大企業のなかでデザインを浸透させていくために、どのような考え方やアプローチが必要だったのか、その取り組みのエッセンスを紹介します。
みずほ銀行のデザイン組織では、立ち上げの段階から「どうすれば全社にデザインの観点で影響を広げていけるか」という視点で設計を進めていました。
というのも、みずほの中では本当に多くのプロジェクトが同時に動いていて、ひとつひとつに闇雲に取り組んでいっても、結果としてデザインの価値が全体に伝わっていくとは限りません。むしろ、個別最適な施策の連続になってしまいかねない。
だからこそ、最初のフェーズでは「どこを起点に体験を変えていくのか」をしっかりと定める必要がありました。そこで、「立ち上げ時点ですでに関わっていた、みずほダイレクトアプリを中心とした体験に近い範囲から順に影響範囲を広げていく」という方針を取っています。(ここについては、Cocodaで最初に公開した事例でも詳しくまとめられています。)
とはいえ、順調に影響範囲を広げていくためには、社内のさまざまな部署から「この人たちに相談したい」と思ってもらえるような存在感を、日々の取り組みのなかで示していく必要がありました。
そのためには、単に表面的にアドバイスをするのではなく、依頼を遂行するだけでもなく、プロジェクトに深く入り込み、本当に必要とされる動きを提供していくことが必要になります。
ただ、みずほのプロジェクトは本当にさまざまで、それぞれ進度も構成メンバーも違います。
例えば、まだアイデア段階の企画もあれば、すでにベンダーに対してデザインタスクの依頼が進んでいるものもある。企画側のメンバーがどれだけデザインの扱いに慣れているかも、プロジェクトによって異なります。
だからこそ、そういった一つひとつの状況を丁寧に捉えたうえで、自然な形でプロジェクトの中に入り込み、価値を発揮していくことが大切だと考えています。
このような環境の中で、みずほのプロパー社員であるデザインマネージャーとして、ステークホルダーとの日々のコミュニケーションを通じて、適切なプロジェクトへのアサインに取り組んできました。
案件マネジメントにおいては、具体的には、以下の3つを地道に回していくことが鍵になっています。これは、どのデザイン組織にも当てはまることだと思いますが、特にみずほのような大企業の中でデザイン活用を進めるならば、必須のアクションだと考えています。
関わるべきプロジェクトの優先度づけ
案件化のための詳細なヒアリング
最適なプロジェクト定義とアサイン
この3つを適切に回していくことで、UX/UIデザインチームとして、より意義のあるプロジェクトに関わることができ、同時に、それぞれの案件に合った支援を提供できるようにしています。
1. 関わるべきプロジェクトの優先度づけ
2. プロジェクトの現状を詳細にヒアリング
3. 最適なプロジェクト定義とアサイン
UX/UIデザインチームとしてどんな領域で実績をつくっていきたいのかは当初から設計していました。その方針をベースにしながらも、より具体的に「今、自分たちが受けるべきプロジェクトとは何か」を定義し、優先順位をつけていくことが重要だと考えていました。
特に初期フェーズで大切にしていたのは、「自己紹介」になるようなプロジェクトに取り組むことです。
そもそも、みずほの中で内製のデザイン組織が立ち上がったのは初めてのこと。行内の誰もが「何をお願いすればいいのか」がはっきりイメージできていない状態からのスタートでした。だからこそ、わかりやすく「こういう支援ができる」という姿を見せることが、信頼や相談のきっかけになると考えました。
シンプルにまとめると、3つの観点で優先度は考えています。
1. みずほダイレクトアプリとジャーニーがつながるか
2. ビジネスインパクトが大きいプロジェクトか( *飛び地でも可 )
3. 「面白そう」なプロジェクト(≒ ケイパビリティ拡張に繋げる)
まず重視すべきは「みずほダイレクトアプリとジャーニーがつながるか」という視点です。
無数に依頼が来ると、どうしてもそれぞれのプロジェクトを別々に考えてしまいがちですが、根本的にみずほ銀行のユーザー体験をより良くしていくことを考えると「ダイレクトアプリを軸とした顧客体験のジャーニー全体」を強化できる案件に取り組むべきです。
だからこそ、どのプロジェクトがその流れに接続しているかを意識し、ジャーニーベースで優先度を判断するようにしていました。
具体例としては、みずほダイレクトアプリの新機能開発などが当てはまります。2025年4月にリリースされた「みずほポイントモール」など、いくつもの新機能を開発し続けてきました。
また、このような新機能開発に加えて、みずほダイレクトアプリでは、日々さまざまな規模感の機能改善が並行して走っており、この運用を支えるために、デザインガイドラインの構築や運用にも取り組んでいます。
2つ目の観点は「ビジネスインパクトが大きいプロジェクト(飛び地でも可)」に取り組むことです。
みずほダイレクトアプリと直接関係がなくても、社内外で注目度の高いプロジェクトやみずほ銀行全体に大きく価値が起こるプロジェクトには積極的に関わるようにしていました。
ここで大事なのは、本当にビジネスインパクトがあるならば、これまでのプロジェクトから離れた「飛び地」でも良いと判断すること。とにかく、デザイン組織としての存在感を示せる場所には力を入れていくスタンスです。
例えば、みずほ銀行のウェブサイトリニューアルの支援はこの観点に当てはまるプロジェクトです。
みずほ銀行におけるウェブサイトは、約3400もの画面を持っており、店舗情報、みずほダイレクトアプリ、投信、宝くじ...など、複数の機能の情報を扱う大規模なサイトです。
このような大規模なサイトのリニューアルに際して、ユーザーの体験品質を高めるために、コンポーネントの統一や、デザインルールの整備に取り組みました。
最後に、特にデザイン組織の価値を高めるために重要だと考えているのは、「面白そう」なプロジェクトに取り組むことです。これは、言い換えると、組織として発揮できるケイパビリティを広げられるような案件とも言えます。
UX/UIデザインチームとしての支援領域が固定化してしまうと、チームとしての成長が鈍化してしまいます。まだやったことのない領域に挑戦していくことで、スキルや視野を広げていけると考えています。
例えばその観点で、「M`s Palette」という新規事業のリリースに向けたロゴデザインに取り組みました。
これは、UX/UIチームとしては初めてのアートディレクション中心の案件であり、「ダイレクトアプリだけでなく、新規事業にも関われる」ということを示すためのチャレンジングな案件でもありました。
このように入りたいプロジェクトの優先順位はあらかじめ定義していましたが、実際に理想的な案件を受けていくためには、ステークホルダーとの丁寧なコミュニケーションが欠かせません。
この部分は、多くのステークホルダーと連携が取りやすいプロパー出身のデザイン組織メンバーとして特に力を入れるべきポイントだと考えていました。
このコミュニケーションの内容をあえて整理すると「ヒアリング」と「アサイン」の2つのステップで工夫を積み重ねていました。
まずはヒアリングについてまとめます。
まずは、事業部側からデザインに関する相談をもらうところからプロジェクトの会話はスタートします。(わかりやすい依頼ではなく「こういうことに悩んでいるんだけど」という相談が多いです)
とはいえ、待っているだけではなかなか声がかからないこともあるので、自分たち側から「動きそうなプロジェクトの気配」を察知して雑談を仕掛けにいくようなケースも多くありました。
そのうえで、実際に話を聞く場面では、以下のような観点を丁寧に確認していきます。
すでに案件としてどの程度固まっているのか?
PM(プロジェクトマネージャー)や関係者の陣容はどうなっているのか?
これまでの進捗や、その内容は?
デザインを進めるうえで必要なファクトがどのくらい揃っている?
この時点で動いているプレイヤー(社内外)は誰か
予算はどのくらい見込まれているか
より具体的には、以下の画像で表したような内容を確かめています。こうした点をヒアリングしながら、プロジェクトにおいてUX/UIデザインチームがどこを埋めるべきかを整理していきます。
ヒアリング結果を踏まえた支援イメージを、PMや企画側のステークホルダーにも伝えることで、デザインの関与がプロジェクトにとって「必要である」と自然に受け入れてもらえるようにしていました。
ヒアリングを通じて、プロジェクトのなかでどこを埋めていくべきかが明確になったら、その内容がUX/UIデザインチームとして本当に取り組むべき案件かどうかを見極めつつ、必要に応じてプロジェクトそのものの形を柔軟に組み立てていきます。
ここで、支援の形をあらかじめパターン化しておく、という方法もあるとは思います。たとえば「リサーチ支援」「UIデザイン支援」など、いくつかのメニューを用意しておけば、相談を受けたときにスムーズに話が進むように見えるかもしれません。
ただ、みずほ銀行においてはそれぞれのプロジェクトのシチュエーションは本当に多様で、一つとして同じ形はありません。
そのなかで支援内容をパターンに当てはめてしまうと、かえって柔軟性を損ない、結果的に価値を発揮しづらくなってしまうと感じていました。
だからこそ、「どこまで関わるか」についても固定化せず、関わり方をいくつかの幅で捉えるのみに留めるようにしています。例えば、以下のような分け方を想定しつつ、プロジェクトに合わせてベストなアサインを行います。
自分たちで手を動かす(完全に入り込む)
ディレクションとして入り、ベンダーや他チームと連携する
完全にお任せし、品質レビューのみに関与する
こうしたスタンスの幅を持ちながら、プロジェクトの状況やチームの余力も見極めつつ、前述した「理想的なプロジェクトかどうか?」という観点を踏まえて、都度アサインの形を柔軟に設計しています。
例えば、自分たちで手を動かすパターンだと、すでにCocodaに出している事例の中では、「みずほダイレクトアプリ」関連の事例が当てはまります。
このような案件では、自分たち自身が企画から入り込める余地も大きく、具体的なデザインタスクを自分たちも手を動かして実施します。(その中で、ベンダーの方に一部デザインタスクを依頼する場合もありますが、基本的にオーナーシップを自分たちが持って進めます。)
逆に、ディレクションに関わりつつも、品質レビューを中心に関与していくような入り方だと、「みずほウェブサイトのリニューアル」の案件が当てはまります。
これは、すでに私たちに相談が来た時点で、ベンダーの方も固まっており、デザインタスクがすでに進捗している状況だったので、私たちは「その後の運用も含めて、ユーザー体験を維持する」ことに注力し、コンポーネントやデザインルールの整備に取り組んでいくようにしました。
このように、柔軟にプロジェクトの体制や進捗に合わせてデザインの専門性を活用し、どんな場合でもより良い結果に持っていけるように関わることを続けています。
また、こうした “オーダーメイドのプロジェクト設計” にいきなり飛び込むには、立ち上げ段階だった当時のUX/UIチームにはまだ専門性が足りないという自覚もありました。
最初から、外部のシニアなデザインパートナーを巻き込み、案件支援に入ってもらうことで、プロジェクトの質を担保しつつ、チームの成熟も並行して進めていけるようにしていたのは、このような専門性不足というストッパーをかけないためでした。
こうした取り組みを積み重ねていくなかで、UX/UIデザインチームとして、みずほの中で関われる領域は少しずつ、しかし確実に広がっていきました。
当初は想定していなかったようなプロジェクトにも声がかかるようになり、たとえばコーポレート全体のHP刷新プロジェクトや、新規事業における体験設計・クリエイティブ領域などにも関与できるようになってきました。
それに伴って、チームとしてのスコープも自然と拡大し、メンバーの人数も増え、スキルの向上にもつながっています。
現在では、立ち上げ当初には難しいと思っていた「行内全体を貫くUXガイドライン」の設計にも着手しており、より広い視点から、みずほ全体におけるデザイン活用を促していける状態が見え始めています。
ここまでの取り組みの裏側は、Cocodaで公開されている事例をぜひご覧ください。
みずほの特徴のひとつとして、「ボトムアップでプロジェクトが進んでいく文化」があると感じています。
だからこそ、デザイン組織としても、トップダウンで「こうすべき」と一方的に示すのではなく、プロジェクトごとの状況を丁寧にヒアリングしながら、その都度、必要な支援を柔軟に届けることを大切にしてきました。
こうしたスタンスは、単なる手段ではなく、みずほという組織文化に対する理解に基づいたアプローチです。文化を無視してデザインを進めようとしてもうまくいかない。だからこそ、みずほにおいてはこのやり方が有効だったのだと思います。
みずほ銀行においては、社内のデザイナーの役割も、いわゆる「インハウスデザイナー」というよりは、デザインディレクターやデザインコンサルに近い立ち位置にあるのかもしれません。
多種多様なプロジェクトが同時に動いているなかで、それぞれに向き合い、場面に応じた最適な支援を行っていくことが求められます。クライアントワークのように多様な案件に関わりつつ、インハウスデザイナーのようにじっくりと案件に向き合えるいいとこ取りのポジションだと思います。
もし支援の形をパターン化してしまっていたら、きっとそうした組織の余白は生まれなかったと思います。あえて型にせず、プロジェクトに寄り添い続けたからこそ、今のような状態をつくることができたと感じています。
現在は、自分自身はUX/UIデザインチームから別のプロジェクトに異動し、デザインチーム外から行内に対する「デザインの触媒」として振る舞い続けています。一方、UX/UIデザインチームは新体制として、また次のフェーズに入ろうとしています。これからは、デザイン活用の担い手がさらに行内に広がっていき、みずほ全体の体験をより良くしていく構想を、チーム全体で引き続き推し進めていきます。